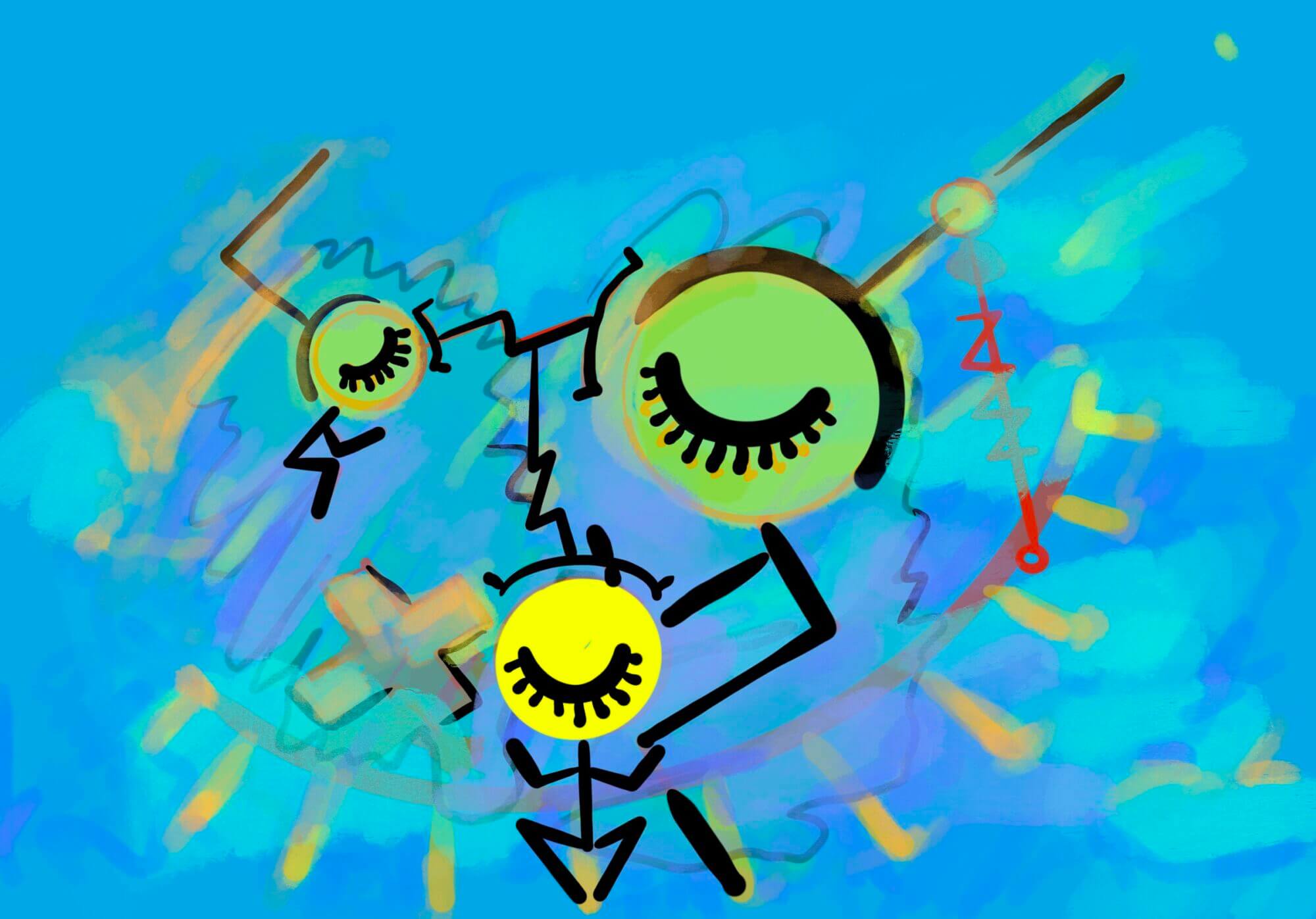はじめに
Ribonuclease Aのアセントン沈殿の条件検討につい、学生さんが精力的に実施されている文献の紹介をして、その後、昔から知られている一般的な沈殿法について紹介してします。
Ribonuclease Aの沈殿精製
界面活性剤による沈殿生成とアセトンによる 沈殿溶解を利用したタンパク質の回収・分離 - 新居浜工業高等専門学校 第51号 (2014)
先ず定義から
- ミセル化に出てくる役者は,水中での界面活性剤の疎水領域と目的物質の疎水性域.これらが結合することで蛋白質の親水性が増加する.
- 逆ミセル化に出で来る役者は,有機溶媒中での界面活性剤の親水領域とタンパク質の親水領域.界面活性剤は,表面が疎水性,内側が親水性となるような内側に水溶液を内包できる小さな構造を作るとき,親水性であるタンパク質をその内側に閉じ込める.
AIくんに詳しく説明してもらおう>
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
ChatGPT: 核酸やタンパク質の抽出や沈殿化の工程では、界面活性剤や有機溶媒の性質を利用する場面が多く、その原理の一つとして「ミセル化(micellization)」や「逆ミセル化(reverse micellization)」が関与します。以下にそれぞれの概念と、核酸・タンパク質の操作との関連を解説します。
🔹 ミセル化(Micellization)
【定義】
ミセル化とは、界面活性剤(両親媒性分子)が水中で疎水性相互作用により、疎水基を内側、親水基を外側にして球状構造(ミセル)を形成する現象です。
【核酸・タンパク質抽出との関係】
- タンパク質の可溶化:細胞膜を構成する脂質を溶解するためにミセル化が用いられ、**SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)**などのアニオン性界面活性剤が、タンパク質と結合してその疎水領域を覆い、水に溶けやすくします。
- 核酸抽出の前処理:細胞膜破壊にもミセル形成界面活性剤が使われることが多い(例:Triton X-100など)。
🔹 逆ミセル化(Reverse Micellization)
【定義】
逆ミセル化は、有機溶媒中で界面活性剤が親水基を内側、疎水基を外側にして形成する構造です。これは**疎水性溶媒中で極性分子(例:水分子やタンパク質)**を包み込むための仕組みです。
【応用】
- 水/有機溶媒抽出法:タンパク質や核酸などの極性物質を有機相に溶け込ませるために、逆ミセルを形成させる手法がとられます。
- クロマトグラフィー前の精製:逆ミセル構造を利用して疎水性溶媒中から親水性タンパク質を選択的に抽出できます。
- 細胞内成分の選択的抽出:逆ミセル化技術は膜タンパク質などを環境制御下で抽出・保持するのに応用されます。
🔹 まとめ:核酸・タンパク質操作での活用イメージ
| 原理 | 溶媒環境 | 構造 | 応用例 |
|---|---|---|---|
| ミセル化 | 水相(極性) | 疎水基:内側 親水基:外側 | 細胞膜破壊、タンパク質の可溶化 |
| 逆ミセル化 | 有機相(非極性) | 親水基:内側 疎水基:外側 | タンパク質の選択的抽出、精製 |
補足:他の関連原理
- 塩析(例:硫酸アンモニウム):タンパク質の沈殿化に用いられ、疎水相互作用を強める。
- エタノール沈殿法(核酸):有機溶媒により核酸の水和シェルを崩し沈殿させる。
- PEG抽出法:高分子の浸透圧効果で核酸を選択的に沈殿。
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
逆ミセル抽出法
- 逆ミセル
- 無極性溶媒中、極少量の水をコアとして、界面活性剤が会合したナノスケールの分子の集合体
- 微小水槽が、界面活性剤分子によって、有機溶媒から隔離されている状態
- この状態では、タンパク質は変性することなく逆ミセルの内部にとじこめられる
- 操作法
- タンパク質水溶液を用意
- 逆ミセルを形成した有機溶液を用意
- 2つを接触させる
- タンパク質の逆ミセルへの移行の原理
- タンパク質と界面活性剤の親水基との静電的相互作用
逆ミセルからタンパク質の抽出
- タンパク質を含む逆ミセルに
- 水溶液を接触させ、界面活性剤との相互作用を弱くする
- タンパク質は、水層に移動するが、その効率は低い
逆ミセル抽出法の改良 (Shinらの方法)
検討タンパク質 : 鶏卵白リゾチーム (14.3kDa, pI:11), 牛膵臓リボヌクレアーゼ(13.7kDa, pI9.6)
- 界面活性剤による沈殿形成
- 原理 : タンパク質は水中でイオン性界面活性剤により沈殿形成する
- 2-エチル(ヘルシル)スルホコハク酸Na(AOT)
- 等量(5mL)を5sec混和、静置→遠心→ppt→蒸留水で洗浄→Acetone 1vol(5mL)で溶解→0.1M NaCl 10μL→沈殿化→静置→遠心→ppt→Acetone洗浄→乾燥→蒸留水溶解
- 極性有機溶媒による回収
- 形成した沈殿を溶解
- acetone (solubilization◯、precipitation◯)
- 1-propanol, 2propanol (solubilization◯、precipitation×)
- ethanol/ethylene glycol (solubilization△/×、precipitation-/-)
- 電解質水溶液を極少量添加
- NaCl 水溶液(電解遮断効果、濃度が高いほど沈殿↓)
- 極性有機溶媒は、タンパク質から外れ、界面活性剤は、極性有機溶媒と混和
- タンパク質は沈殿のまま回収できる
- 低い界面活性剤の濃度で処理可能
硫安、アセトン、TCAなど、タンパク質の沈殿法プロトコールまとめ – ThermoFisher -より
https://www.thermofisher.com/blog/learning-at-the-bench/protocols-of-protein-precipitation/
トラディショナルな沈殿法
- 硫酸アンモニウム(硫安)沈殿法
- マイルドなタンパク質沈殿化法
- 飽和硫安濃度33%でIgGが沈殿、アルブミンは50%程度で沈殿する
- アセトン沈殿法
- 昔の血漿分解製剤で使用
- トリクロロ酢酸(TCA)沈殿法
- 酸性等電点を持つタンパク質に適用できる
- グリシン塩酸法
- TCA/アセトン沈殿法
- クロロホルム/メタノール
- SDSなどを除けるMS(質量分析)用のタンパク質の回収
- 酸性pH処理
- pH3~pH5にすることで、沈殿するものもあります。DNAなどの核酸が沈殿します。DNAでなくタンパク質も沈殿するものもあります
- DNAとタンパク質が共沈したとしても、その他の不純物と分離ができていれば、よしとします。後の処理でDNAとの分離を考えましょう
- 添加する酸は、タンパク質にマイルドな酢酸を使用します。塩酸は決して使ってはいけません。タンパク変性しやすいためです
- 食塩(NaCl)添加
- 3~5MのNaCl溶液を少ない量から適当添加していく方法で、スモールスケールの検討を行います。
- 酢酸を添加して酸性pHにしても沈殿が生じない場合に、追加的にNaClの添加をすると沈殿することもあります
- EtOH分画
- 血漿分画製剤で使用される実製造に使われている
- この技法は高度である。再現性を得るには、温度管理、pH管理、及び伝導度管理を厳密に制御する必要がある
参考
タンパク質精製は、SDS-PAGE分析で検出できる狭雑タンパク質の分離だけでは不十分です。endotoxnや核酸も不純物です。タンパク質から核酸を除去する目的ではないですが、沈澱法としてCTAB沈澱法についても以下に紹介します。この方法も昔から行われていた沈澱法です。
- CTABによるplasmid DNAとRNA/endotoxinの分離 2)
検討方法
マイクロサイズ法
沈澱化の検討は、200μL程度のガラス製のバイアルを使えば効率的です。Biacore用のサンプルチューブがいい感じに使えます。透明度と数百μLで検討ができて、サンプル量も効率的です。
操作法
- 100μLのサンプルをGlass vialに分注
- 酢酸原液を数μLずつ添加
- 別途、添加量とpHを確認しておく
- 酢酸は、タンパク質の溶解性を高めるので、入れすぎは逆効果です
- ですが、酢酸で低pHのタンパク質溶液にNaClを添加して塩濃度を高めると疎水性がより高まるためタンパク質が沈澱化しやすくなります
- 分子量が大きいて沈澱化効率は高まります
- 以上のことを踏まえて、沈殿化条件を決定していきます。
分析
- UVスペクトル(A200~700, NanoDropが便利)
- A260/A280比率は、タンパク質と核酸のコンタミ具合の指標
- SDS-PAGEによるタンパク質の純度分析
- 目的物の分子量を指標に評価
- Endotoxin分析 (option)
- LAL法 (Kit)
- DNA分析 (option)
- PicoGreen (Kit)
1) Glass vials
Borosilicate glass vials in a range of sizes and volumes. For use with Biacore systems.
沈殿化検討に使用する透明なガラスバイアル。ゴム栓も購入できるので、それを使えばしばらく保存が可能。検討である程度たまったら写真を撮ってから廃棄です。
https://www.cytivalifesciences.com/en/us/shop/protein-analysis/spr-label-free-analysis/accessories-vial/glass-vials-p-05546
2) Milligram scale parallel purification of plasmid DNA using anion-exchange membrane capsules and
a multi-channel peristaltic pump (2007)低濃度CTAB (0.1-4g/L) 沈殿法によるpDNAとRNA/Endotoxinの分離 : 2g/L or 10g/L CTAB/50mM NaCl溶液を添加し、Incubation20分, cfg(38,000xg 20min, 20℃)/pptを70% EtOHで洗浄し、0.6M NaCl, 25mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH7.4で氷冷下で溶解。
https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Schmidt15/publication/6232344_Milligram_scale_parallel_purification_of_plasmid_DNA_using_anion-exchange_membrane_capsules_and_a_multi-channel_peristaltic_pump/links/59de01f545851557bde325bd/Milligram-scale-parallel-purification-of-plasmid-DNA-using-anion-exchange-membrane-capsules-and-a-multi-channel-peristaltic-pump.pdf?origin=publication_detail
まとめ
今回、タンパク質の沈殿化方法の色々を紹介しました。これらの方法で、タンパク質を純度よく精製するには、条件をもっと厳密にコントロールしなければなりませんが、今回紹介した中では、そこまで条件を詰めて設定されたものはありません。
沈殿化法で、更にタンパク質の精製を極めたいと思っているなら、エタノールを使用した沈殿化による血漿タンパク質の精製方法として、Cohn Ethanol Fractionationが知られているので、それを当たるのも手です。Cohn法では、厳密な条件のコントロールが必要です。例えば、温度(4℃)、pH(酸性から中性に徐々に上げていく)、塩濃度、EtOH濃度(徐々に上げいく)により、血漿から段階的にタンパク質画分を沈殿させていきます。大雑把に言うと、最初に沈殿化する画分には、高分子(Fibrinogenなど)、続いて免疫グロブリン(IgGなど)、最後に、血漿タンパク質として最も多いアルブミムです。少しの条件設定のミスで、純度・回収率が悪化したり、タンパク変性したりします。機会があれば、Cohn Ethanol Fractionについてもご紹介したいと思います。
今回、紹介したタンパク質の沈殿化法でも、回収率が悪いとか、純度が悪いとかいった場合は、pH, 塩濃度、温度などを見直してみてください。
編集履歴
2020/04/09 はりきり(Mr)
2020/05/23 追記 (はじめに、まとめ)
2020/09/23 追記 (酢酸の添加、NaClの添加、検討方法)
2020/11/05 追記 (CTAB沈殿法によるpDNAとRNA/endotoxinの分離)
2020/12/11 追記 (操作法 by Mr.HARIKIRI)
2025/04/21 追記 (ミセル化・逆ミセル化の詳細 with AI)
以上