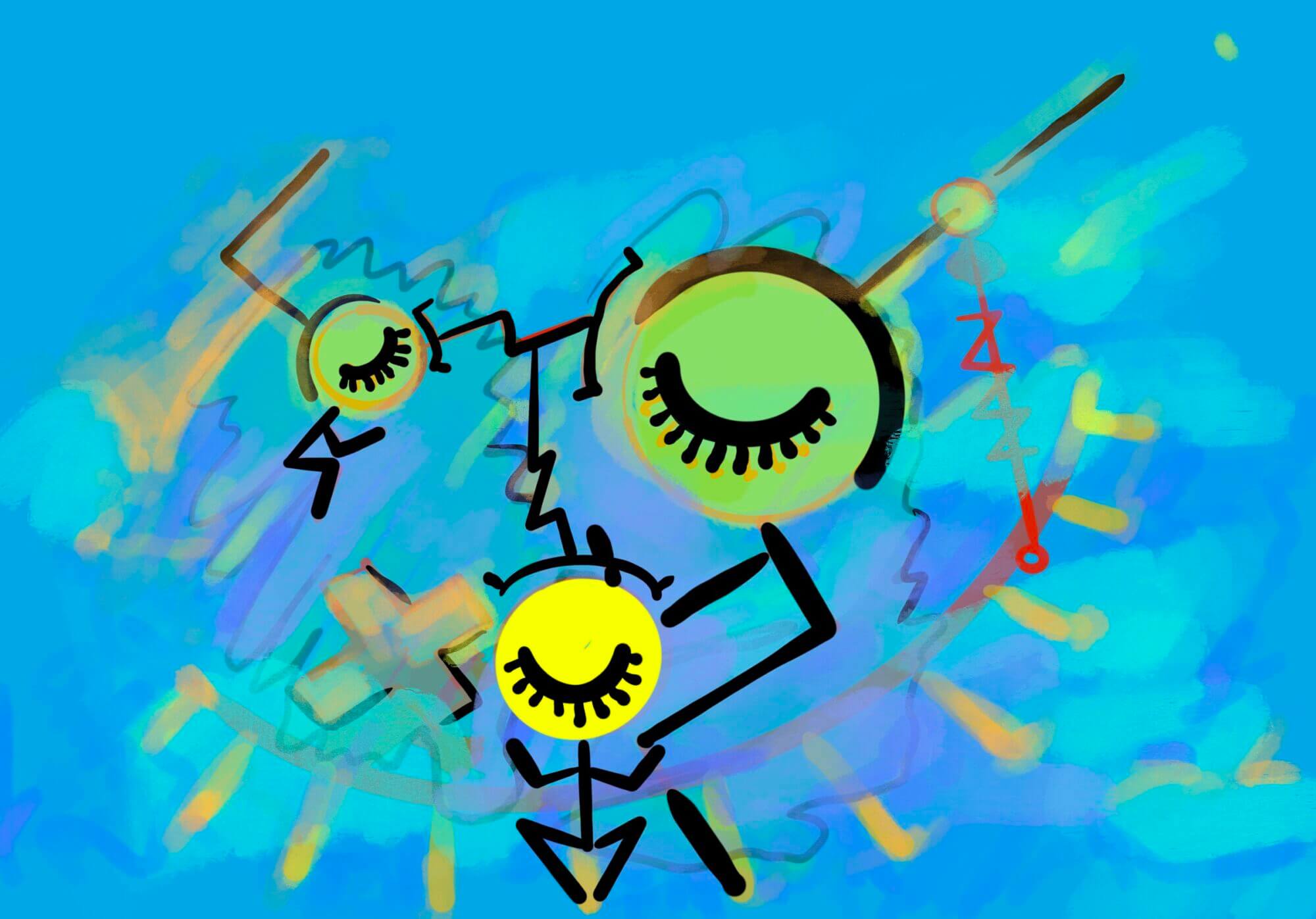はじめに
日本薬局方の微生物限度試験法(4.05)と無菌試験法(4.06)に必要な菌種の調達,操作法について示す.
先ずは,菌種の調達先
- 日本薬局方に規定される菌種がnite (製品評価技術基盤機構)のホームページに記載があります.リストに無い菌種についても協力してくれるようです.菌種の供給元はほとんどがNBRCがリストされています.
- 日本薬局方に規定された供試菌株 | バイオテクノロジー | 製品 …
- NRBC株を購入するには,以下のリンクからアカウント登録,オンラインカタログによる申し込み,支払いとなる : NBRC株の入手方法
- ATCCとNBRCの番号の関係(FAQ by nite) : FAQ | バイオテクノロジー | 製品評価技術基盤機構 – NITE
- フナコシから購入 : ATCC®製品の選択から納品まで | ATCC®製品ご利用( …
- 住商ファーマから購入 : ATCC | 取り扱い商品 | ATCC分譲サービス | 住商ファーマ …
- 関東化学から購入 : 標準菌株 | 標準菌株 | 標準菌株・精度管理 | 微生物検査 …
- レーベンジャパンから購入 : レーベン・ジャパン株式会社 | Microbio logics® ATCC | 標準菌株
- 製品の特長
- ATCC®社と同等製品(ライセンス契約取得)
- 冷蔵保存(2~8℃)が可能な凍結乾燥品
- 継代数は3世代以内(1~2世代もあり)
- 簡易包装でユーザーフレンドリー
- 微生物試験のコントロールに最適
- 製品の特長
培地は何を使うか
【共通で使用できる培地】
これらは 微生物限度試験と無菌試験の両方で使用可能または類似した形で利用される培地です。
| 培地名 | 主な用途 | コメント |
|---|---|---|
| Soybean-Casein Digest Medium(SCDM) (大豆-カゼイン消化培地) | 微生物限度試験:TAMC(総好気性微生物数) 無菌試験:好気性・真菌検出 | 両試験で汎用的に使われる代表培地(固体 or 液体で形状が異なる) |
| Sabouraud Dextrose Agar(SDA) (サブロー・デキストロース寒天培地) | 微生物限度試験:TYMC(酵母・カビ) 無菌試験:真菌用培地として類似品(SCDM) | 微生物限度試験では公式に使用される。無菌試験ではSCDMに集約される傾向。 |
【微生物限度試験 専用の培地】
これらは 微生物限度試験(4.05)に特有で、無菌試験では使用されない培地です。
| 培地名 | 主な用途 | 備考 |
|---|---|---|
| MacConkey Agar | 大腸菌の選択分離 | 胆汁酸塩含有、グラム陰性菌選択 |
| Mannitol Salt Agar | 黄色ブドウ球菌の選択分離 | 高塩濃度で選択性あり |
| Cetrimide Agar | 緑膿菌の選択分離 | 色素・蛍光の産生で確認 |
| XLD Agar / Selenite Cystine Broth | サルモネラ属菌検出 | 増菌・分離用 |
| Violet Red Bile Glucose Agar(VRBGA) | 腸内細菌科(胆汁酸耐性グラム陰性菌) | 特定微生物試験用 |
【無菌試験 専用の培地】
こちらは 無菌試験(4.06)でのみ使用される培地です。
微生物限度試験では使われません。
| 培地名 | 主な用途 | コメント |
|---|---|---|
| Fluid Thioglycollate Medium(FTM) (チオグリコール酸液体培地) | 通性嫌気性菌・嫌気性菌の検出 | 30~35℃で14日間培養。酸化還元指示薬入り |
| Soybean-Casein Digest Medium(液体SCDM) | 好気性菌・真菌検出 | 無菌試験では液体形態で使用 |
| ※補助培地:Tryptic Soy Broth(TSB) | バリデーションや予備試験に使用 | 日局には明記されていないが実務で使用例あり |
まとめ表:培地の分類
| 培地名 | 微生物限度試験 | 無菌試験 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Soybean-Casein Digest Medium(固体/液体) | ✅ | ✅ | 主に固体(限度試験)/液体(無菌試験)で使い分け |
| Sabouraud Dextrose Agar | ✅ | △(公式ではない) | 真菌用。限度試験では公式、無菌試験ではSCDMが推奨される |
| Fluid Thioglycollate Medium(FTM) | ❌ | ✅ | 無菌試験専用(嫌気性菌も対応) |
| MacConkey Agar、XLD Agar など | ✅ | ❌ | 特定微生物試験で使用(限度試験専用) |
| Mannitol Salt Agar、Cetrimide Agar | ✅ | ❌ | 限度試験の選択分離用 |
微生物限度試験の具体例
- 微生物限度試験や無菌試験に用いる培地は、**適格性確認(Growth Promotion Test)**を行って、有効な培地であることを確認する必要があります。
- この試験では、所定の微生物を少数(通常≦100 CFU)添加して、適切に増殖するかを確認します。
試験菌の調製 :
(参照: 日本薬局方(第十八改正)「4.05 微生物限度試験」および関連のガイダンス(例:JP解説書、USP、ICH Q6A等)
- マスターシードロットから継代数5回を超えないこと(シードロットシステム)
- 細菌及び真菌の各試験菌は,表中に記載の自要件で個別に培養し試験する.
- 試験菌懸濁液の調製には,ペプトン食塩緩衝液 pH7.0,又はリン酸解消液 pH7.2を用いる.
- カビの一種にはPolysorbate 80を0.05%加えても良い.
- 懸濁液は2時間以内,又は2~8℃で24時間以内に用いる.
- など.
「日本薬局方 一般試験法4.05 微生物限度試験」の概要
Ⅰ.非無菌製品の微生物学的試験:生菌数試験Ⅰ. 非無菌製品の微生物学的試験:生菌数試験
- **TAMC(Total Aerobic Microbial Count)**は、総好気性微生物数のことであり、製品中に存在する好気性の生菌(細菌や一部真菌)を測定するための指標です。
- **TYMC(Total Yeasts and Molds Count)**は、総酵母・カビ数のことで、製品中に含まれる真菌(酵母およびカビ)の生菌数を測定します。
- これらは、製品の種類や投与経路に応じて、許容される限度内であることが求められます。
Ⅱ. 非無菌製品の微生物学的試験:特定微生物試験
非無菌製品には、製品の性質や使用目的に応じて、以下の特定微生物の存在が検査されることがあります。
- 大腸菌(Escherichia coli)
- サルモネラ属菌(Salmonella spp.)
- 緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)
- 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)
- 胆汁酸塩添加培地で選択される腸内細菌(Enterobacteriaceae)
※上記は製品のカテゴリー(経口用、経皮用、小児用など)によって検査の要否が異なります。
【補足:日本薬局方で通常対象とならない微生物】
以下の微生物は、日本薬局方における微生物限度試験の特定微生物には含まれていません(他の国の薬局方や食品分野などでは対象となることがあります):
リステリア・モノサイトゲネス(Listeria monocytogenes)
クロストリジウム属(Clostridium spp.)
カンジダ・アルビカンス(Candida albicans)
培地の種類 :
日本薬局方「4.05 微生物限度試験」で使用される主な培地一覧
【1】生菌数試験(TAMC・TYMC)
| 用途 | 培地名 | 説明 |
|---|---|---|
| TAMC(Total Aerobic Microbial Count) 総好気性微生物数 | Soybean-Casein Digest Agar(SCDA) (大豆-カゼイン消化寒天培地) | 好気性細菌の増殖に使用される汎用培地 |
| TYMC(Total Yeasts and Molds Count) 総酵母・カビ数 | Sabouraud Dextrose Agar(SDA) (サブロー・デキストロース寒天培地) | 酵母・カビなどの真菌検出用 |
【2】特定微生物試験(例:大腸菌、サルモネラなど)
| 微生物名 | 使用培地(例) | 補足 |
|---|---|---|
| 大腸菌(Escherichia coli) | MacConkey Agar または Lactose Broth(乳糖ブロス) | 発酵試験・選択分離に使用 |
| サルモネラ属菌(Salmonella spp.) | Selenite Cystine Broth Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar | サルモネラ選択培地 |
| 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus) | Mannitol Salt Agar | 耐塩性・マンニトール分解能を利用 |
| 緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa) | Cetrimide Agar | 選択培地(緑色の色素産生) |
| 胆汁酸塩添加腸内細菌(Enterobacteriaceae) | Violet Red Bile Glucose Agar(VRBGA) | 胆汁塩に耐性を持つ腸内細菌群の検出 |
| クロストリジウム(参考) | ※日局では規定なし(食品向けにReinforced Clostridial Mediumなどが使用されることあり) | — |
【3】その他補助培地(特定微生物試験で使用)
| 培地名 | 用途例 |
|---|---|
| Tryptic Soy Broth (TSB) | 一般的な増菌用液体培地 |
| Buffered Sodium Chloride Peptone Solution | 試料の懸濁・希釈用 |
| Bile Salt Broth | 胆汁酸塩耐性菌の検出(例:Enterobacteriaceae) |
備考
- 日局では「指定の培地を使え」と明記されている場合と、「適切な培地を使用すること」として自由度があるケースの両方があります。
- 特定微生物試験では、「増菌 → 選択培地で分離確認」という流れが一般的です。
培地の調達先
無菌試験法の具体例1(膜ろ過法)
「日本薬局方 一般試験法4.06 無菌試験法」の概要
Ⅰ. 無菌製品の微生物学的試験:無菌試験の概要
- 無菌試験(Sterility Test)は、注射剤、点眼剤、透析液などの無菌製品に対して実施される試験です。
- この試験の目的は、試験対象製品に生きた微生物が存在しないことを確認することです。
- 試験は、製品の滅菌法の妥当性を確認し、製品が汚染されていないことを保証するために行われます。
Ⅱ. 試験法の種類と実施方法
日本薬局方では、以下の2つの方法が規定されています:
1. 直接接種法(Direct Inoculation Method)
- 試料をそのまま滅菌培地に接種し、微生物の発育を観察する方法。
- 接種後、30~35℃の好気性細菌用培地(FTM)と20~25℃の真菌用培地(SCD)の両方で14日間培養します。
2. 膜ろ過法(Membrane Filtration Method)
- 液状製品に用いられる主な方法で、製品を滅菌膜でろ過し、膜上の微生物を2種類の培地に移して培養します。
- 濁度や着色などで直接接種が困難な製品にも適応可能です。
Ⅲ. 培地および培養条件
| 培地名 | 培養温度 | 培養日数 | 対象微生物の例 |
|---|---|---|---|
| FTM(Fluid Thioglycollate Medium) | 30~35℃ | 14日間 | 好気性および通性嫌気性細菌 |
| SCD(Soybean-Casein Digest Medium) | 20~25℃ | 14日間 | 真菌(酵母・カビ)など |
※ 両培地とも、事前に**培地の適格性試験(Growth Promotion Test)**を実施し、有効性を確認する必要があります。
Ⅳ. 試験の適用対象
無菌試験は、以下のような製品に義務付けられています:
- 注射剤(バイアル、アンプルなど)
- 点眼剤
- 透析液
- 一部の手術用洗浄剤や注入液
※製品ごとに試験法の選択(直接接種 vs 膜ろ過)は、その性状・使用目的に応じて判断されます。
Ⅴ. 注意点・補足
よって、製造工程の**無菌保証(例:滅菌バリデーション、環境管理、無菌操作)**と組み合わせて使用される必要があります。
無菌試験は、無菌性を完全に保証するものではなく、統計的確認手段とされています。
試験対象例:バイアル注射剤(液体)
使用する材料・培地
| 材料 | 目的 |
|---|---|
| 膜ろ過装置(0.45μm以下) | 試料中の微生物を捕集 |
| 流加チオグリコール酸培地(FTM) | 嫌気性菌の培養用(30±2℃・14日間) |
| 大豆-カゼイン消化物液体培地(TSB) | 好気性菌の培養用(20~25℃・14日間) |
| 陽性対照菌(性能確認用) | 培地の性能検証(例:S. aureus, C. sporogenes など) |
ステップ①:試料の準備とろ過
- 滅菌済みの膜ろ過装置を組み立てる。
- 試料(例:注射剤1本)を装置に通して膜フィルターに微生物を捕集。
- 捕集後、フィルターを滅菌ピンセットで2枚に分け、
- 1枚:FTMに入れる(嫌気性)
- 1枚:TSBに入れる(好気性)
ステップ②:培養
| 培地 | 培養条件 |
|---|---|
| FTM | 30 ± 2℃/14日間 |
| TSB | 20~25℃/14日間 |
両培地を別々のインキュベーターで管理。
培養中は、毎日または数日に一度**外観観察(濁り・沈殿など)**を行います。
ステップ③:判定
| 判定基準 | 内容 |
|---|---|
| 合格 | 培地が透明なまま・濁りなしであれば「無菌」 |
| 不合格 | 培地に濁りや微生物の発育兆候があれば「汚染あり」 |
まとめ:膜ろ過法の流れ
cssコピーする編集する[試料準備] → [滅菌ろ過] → [膜を培地に移す] → [14日間培養] → [発育有無を確認]
無菌試験法の具体例2(直接接種法(Direct Inoculation)
目的・適用製剤
- 試料を直接培地に加えて微生物の発育を確認。
- 通常はろ過が難しい製剤に適用されます。
主な対象例:
- 油性注射剤(例:ビタミンE注射)
- 乳剤製剤
- 軟膏剤
- 粉末製剤(凍結乾燥製剤など)
使用材料・培地
| 材料/培地 | 用途 |
|---|---|
| 大豆-カゼイン消化物液体培地(TSB) | 好気性菌用(20~25℃、14日間培養) |
| 流加チオグリコール酸培地(FTM) | 嫌気性菌用(30~35℃、14日間培養) |
| 滅菌済試験容器、シリンジ、注射針など | 試料添加・操作用 |
以下に日本薬局方「4.06 無菌試験(Sterility Test)」において使用される主な培地を、役割ごとに明確にまとめます。
日本薬局方「4.06 無菌試験」で使用される主な培地一覧
【1】主要培地(試験本体で使用)
| 培地名 | 使用目的 | 培養条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Fluid Thioglycollate Medium(FTM) (チオグリコール酸液体培地) | 主に好気性および通性嫌気性細菌の検出 | 30~35℃、14日間 | 酸化還元指示薬(レサズリン)を含む。培地の透明性が重要。嫌気性にも対応。 |
| Soybean-Casein Digest Medium(SCDM) (大豆-カゼイン消化液体培地) | 真菌(酵母・カビ)および好気性細菌の検出 | 20~25℃、14日間 | 一般的な微生物の広範な検出に対応する汎用培地。pH 7.1±0.2が望ましい。 |
【2】性能確認・培地の適格性試験で使用される標準微生物(参考)
これらの菌株を使用して、上記培地の性能(微生物の発育能)を確認します。
| 微生物名(例) | 使用する培地の一例 |
|---|---|
| Staphylococcus aureus(ATCC 6538) | FTM, SCDM |
| Escherichia coli(ATCC 8739) | FTM, SCDM |
| Bacillus subtilis(ATCC 6633) | FTM |
| Candida albicans(ATCC 10231) | SCDM |
| Aspergillus brasiliensis(ATCC 16404) | SCDM |
| Salmonella Abony(NCTC 6017など) | FTM, SCDM |
【3】補助培地(場合により使用)
これらは日局に明記されてはいませんが、洗浄液の無菌性確認やろ過工程の検証など、試験補助に用いられることがあります:
| 培地名 | 使用例 |
|---|---|
| Tryptic Soy Broth(TSB) | 補助的な増菌やバリデーション用 |
| Buffered Sodium Chloride Peptone Solution | 試料の希釈・洗浄液として使用される場合あり |
培養条件のポイント
| 培地 | 温度 | 日数 | 使用理由 |
|---|---|---|---|
| FTM | 30~35℃ | 14日間 | 嫌気・通性嫌気性菌対応 |
| SCDM | 20~25℃ | 14日間 | 真菌・一般細菌対応 |
※両方とも14日間継続培養が必要。毎日または定期的に混濁や菌塊の有無を観察します。
補足情報
- 培地は無菌性を保証するために、使用前に無菌試験および性能確認試験(Growth Promotion Test)を実施する必要があります。
- **FTMの酸化状態(表層がピンク色になっていないか)**も使用前に確認する必要があります。
試験の具体的な流れ
ステップ①:試料の接種
- 試験対象(例:注射剤、軟膏など)を無菌操作下で準備。
- TSBおよびFTMに、決められた量の試料を直接加える(通常、10mLあたり最大1mLまで)。
- 混和して、すぐに培養へ。
※製剤が濁っている場合や防腐剤を含む場合は、中和剤の添加が必要になることがあります。
ステップ②:培養条件
| 培地 | 温度 | 期間 |
|---|---|---|
| TSB | 20~25℃(好気) | 14日間 |
| FTM | 30~35℃(嫌気) | 14日間 |
- 培養中は、濁りや沈殿など発育兆候を目視観察
- 防曇ガラス容器や傾斜容器が用いられることもあります
ステップ③:判定
| 判定基準 | 結果 |
|---|---|
| 合格 | 14日間、いずれの培地にも発育兆候がない(透明) |
| 不合格 | 濁り、沈殿、ガス産生、膜形成などがあれば不合格 |
まとめ:直接接種法の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象製剤 | ろ過困難なもの(油性、軟膏、乳剤、粉末など) |
| メリット | 簡便、器具が少なくて済む |
| 注意点 | 製剤が培地に干渉する場合がある(中和・希釈・事前検証が必要) |
| 合否判断 | 微生物の発育が完全にゼロであることが必須 |
【無菌試験における性能確認(陽性対照試験)】
Ⅰ. 性能確認とは?
- 無菌試験では、使用する培地や試験操作が微生物の検出に適しているかを確認する必要があります。
- これを「性能確認(適格性試験, Validation / Suitability Test)」と呼びます。
- 性能確認では、**少量(≦100 CFU程度)**の既知の微生物を試験に用い、それらが培養で増殖するかを確かめます。
Ⅱ. 使用される陽性対照菌(試験菌株)
日本薬局方では、以下の微生物を性能確認に使用することが推奨されています:
| 微生物名(学名) | 推奨株(ATCCなど)例 | 特徴 |
|---|---|---|
| バチルス・スブチリス(Bacillus subtilis) | ATCC 6633 | グラム陽性、好気性芽胞菌 |
| クラウディア・アルビカンス(Candida albicans) | ATCC 10231 | 酵母 |
| アスペルギルス・ニゲル(Aspergillus brasiliensis) | ATCC 16404 | カビ |
| 大腸菌(Escherichia coli) | ATCC 8739 | グラム陰性桿菌 |
| サルモネラ・アバニ(Salmonella Abony) | NCTC 6017 | グラム陰性桿菌 |
| スタフィロコッカス・アウレウス(Staphylococcus aureus) | ATCC 6538 | グラム陽性球菌 |
Ⅲ. 試験方法と評価
試験手順(概要)
- 選択した菌株から、**微量(≦100 CFU)**の懸濁液を調製する。
- それを実際の試験と同様の方法(直接接種法または膜ろ過法)で試験培地に添加。
- 指定の条件下(温度・期間)で培養する。
- 微生物が増殖して検出できることを確認。
判定基準
- 各菌株が適切な培地と条件で明確に増殖すること。
- 結果が不適合の場合は、培地、操作、試験条件を再評価・再確認する必要があります。
Ⅳ. 実施タイミングと頻度
- 性能確認は以下のタイミングで実施される:
- 新しい培地ロットを使用する前
- 試験法の初導入・変更時
- 定期的なバリデーションまたは疑義発生時
Ⅴ. なぜ重要か?
- 無菌試験は、「微生物が**いないことを確認する試験」」なので、微生物がいた場合にちゃんと見つけられるかを確認する性能試験が不可欠。
- これが確認できていないと、**偽陰性(本当は汚染されているのに検出されない)**リスクが高まります。
最後に
- 直接接種法は、膜ろ過法に比べて簡便ですが、製剤成分による干渉が起きやすいため、慎重な事前評価(バリデーション)が必要です。
- 中和剤や希釈剤の選定、陽性菌回収率の検証などが重要です。
参考ポスト
参考文献
- 微生物試験法に用いる培地及び微生物株の管 理 – PMDA
- Lesson2「第18改正日本薬局方:4.05 微生物限度試験におけ …
- 事務連絡 – PMDA : <一般試験法 微生物限度試験について> Q1 15局の微生物限度試験法でバリデーション(適合性)を取得済みの試料について、 第一追補の試験法での再バリデーションは必要であるか。 A1 試験法が異なるため、第一追補での適合性
- 生薬及び生薬関連製剤の微生物限度試 – PMDA
- 5.02 生薬の微生物限度試験法 – PMDA
- 微生物限度試験の方法 – クリタ分析センター株式会社
- 医薬分野における微生物試験技術の 動向と今後の展開 (住処分析センター)
編集履歴
2025/04/04 Mrはりきり