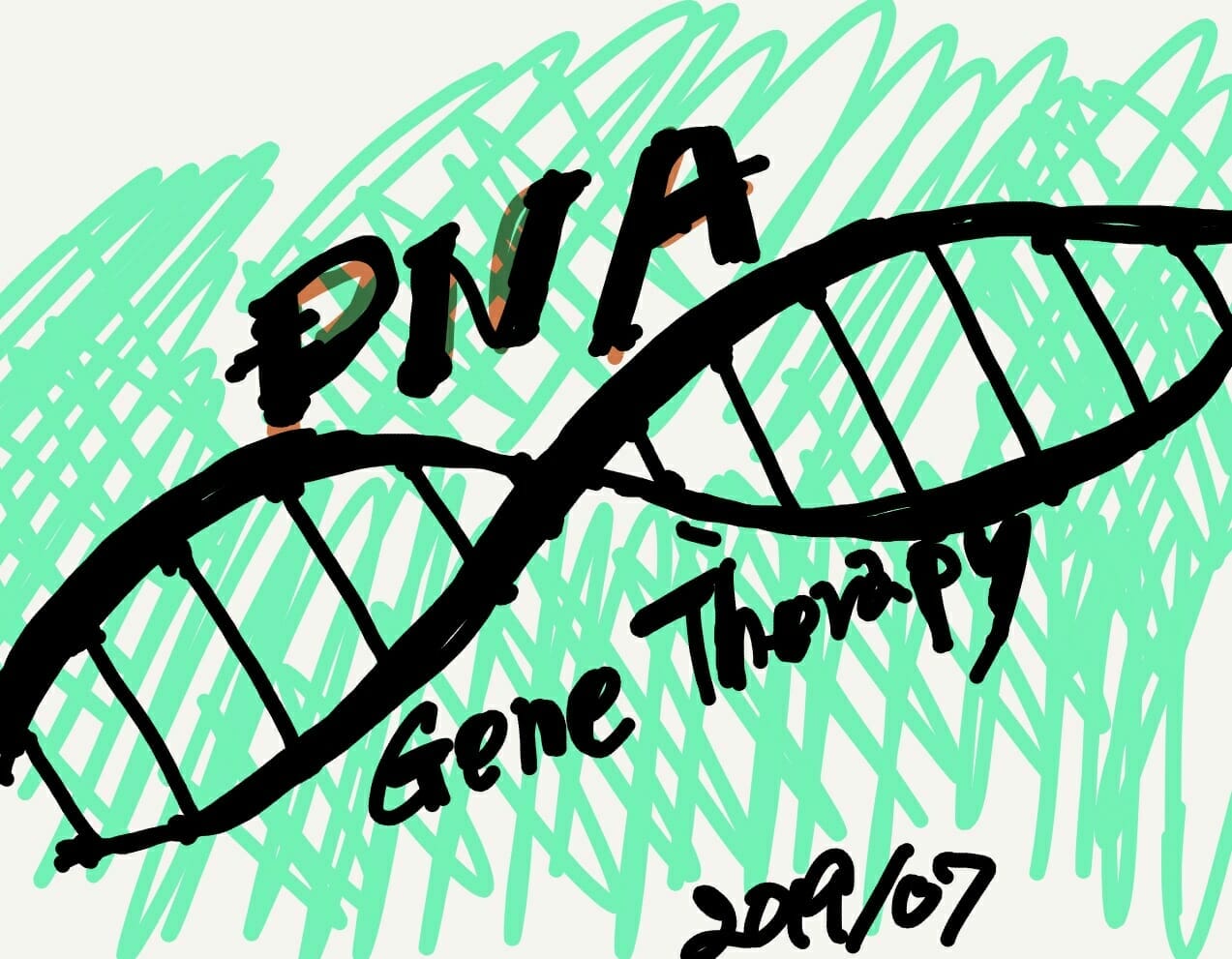はじめに
2019/07, 東大、3つの神経筋疾患に共通する異常なリピート配列を発見、創薬応用へ
東大は、3つの神経疾患について、異常なリピート配列を発見した。
異常なリピートは、非翻訳領域にCGGの3塩基からなる繰り返し配列の異常伸長であり、以下に示した3つの疾患に共通しており、別の疾患と考えられてきたこれらの疾患は、共通の繰り返し配列のリピートを原因とする疾患であることがわかった。
- 神経核内封入体病(neuronal intranuclear inclusion disease:NIID)
- 認知症などで知られている神経変性疾患。幼少期から高齢まで幅広く発症。
- NBPF19 遺伝子の5’非翻訳領域に存在するCGG繰り返し配列の異常伸長を確認
- 白質脳症を伴う眼咽頭型ミオパチー(oculopharyngeal myopathy with leukoencephalopathy:OPML)
- 頭部MRI画像で神経核内封入体病に類似した大脳白質の異常を示し、加えて眼球の運動を司る筋肉、嚥下・発声を担う咽頭の筋肉、四肢の筋肉を侵す疾患
- 解析の結果、LOC642361・NUTM2B-AS1という別の遺伝子に、同じCGG繰り返し配列の異常伸長が存在することを確認
- 眼咽頭遠位型ミオパチー(oculopharyngodistal myopathy:OPDM)という3つの神経筋疾患
- 眼球運動、咽頭、さらに四肢の遠位部の筋力低下が特徴的な筋疾患で、国が定める指定難病の一つである、遠位型ミオパチーに含まれる疾患
- 前述の白質脳症を伴う眼咽頭型ミオパチーと筋の罹患部位の分布が非常に類似していることをヒントに解析した結果、LRP12遺伝子に、やはりCGG繰り返し配列の異常伸長変異が存在することを確認
東大、3つの神経筋疾患に共通する異常なリピート配列を発見、創薬応用へ、日経バイテク, 2019/07
https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/news/p1/19/07/22/05843/
これまでに得られている関連情報
一般的にタンパク質への翻訳は,開始コドン(ATG)から始まる.しかし,特定の塩基配列の非常に長い繰り返し配列(リピート配列)が存在すると,開始コドンがなくても翻訳が生じることが2010年に実験的に確かめられ,repeat-associated non-ATG(RAN)翻訳と呼ばれるようになった.
RNA翻訳, 2015, – 薬学用語解説-
https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?RAN翻訳
「てんかんの新しい発症機構の解明 ―繰り返し配列の異常伸長によっててんかんが生じることを発見―」
発表ポイント
- 本邦に多く見られる、家族性のてんかんについて、次世代シーケンサーを駆使したゲノム解析によりその原因遺伝子として 3 遺伝子を発見
- 発見した 3 つの遺伝子(SAMD12 遺伝子、TNRC6A 遺伝子、RAPGEF2 遺伝子)は、いずれの場合も、イントロン領域に存在する、TTTCA という繰り返し配列の異常伸長が、発症原因となっていることを解明
- TTTCA 繰り返し配列の異常伸長が共通していることから、この異常伸長が直接てんかん発症の原因になっていると考えらる。神経細胞核内に TTTCA 繰り返し配列を有す る RNA の凝集体が観察され神経細胞の傷害に関与していると考えられます
【記者会見】別々の3疾患に共通する原因がヒトゲノムCGG塩基の繰り返し配列の異常伸長であることを解明, 2019/07
https://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/20190723.html
AIにこの表題について解説してもらった
神経疾患(ミオパシー、てんかん)に共通する異常なリピート配列の発見 – リピート配列は開始コドンがなくてもたんぱく翻訳される」・・・に関して解説して
ChatGPT:
リピート配列と神経疾患について解説
以下に、神経疾患における異常なリピート配列の発見と、それが開始コドンなしでタンパク翻訳される現象について、以下の観点から詳しく解説します。
1. 異常リピート配列と神経疾患の関連性
異常リピート配列とは
DNAやRNA中に存在する繰り返し配列(リピート配列)が、通常の繰り返し回数を超えて異常に伸長してしまうことがあります。こうした配列の伸長は、転写されたRNAや翻訳産物(タンパク質)に異常をもたらし、神経細胞など特定の細胞で機能障害を引き起こすことが知られています。これらの異常なリピート配列は、ミオパシー(筋疾患)や一部のてんかん症例を含む神経疾患に共通して見出される例もあり、病態発生の一因と考えられています。
疾患への影響
・リピート配列の伸長は、RNAの二次構造(例:ヘアピン構造)の形成を促進し、これが細胞内でのRNAの正常なスプライシングや輸送、局在に影響を与える可能性があります。
・また、伸長したリピートRNA自身が、細胞内のタンパク質と異常な相互作用を起こし、RNAの毒性(RNA毒性)として神経細胞にダメージを与えることも報告されています。
・これまでの研究では、リピート伸長疾患では、異常タンパク質の蓄積や細胞内凝集体の形成が細胞機能障害に寄与していることが示されています。
2. 開始コドンを必要としない翻訳:RAN翻訳
通常の翻訳開始メカニズム
通常、mRNAからタンパク質が合成される際は、リボソームがmRNA上の最初のAUG(メチオニンをコードする開始コドン)を認識し、そこで翻訳が開始されます。このプロセスにより、正確なタンパク質配列が生産されるのが一般的です。
RAN翻訳(Repeat-Associated Non-AUG Translation)の概要
近年の研究により、異常に伸長したリピート配列が、従来のAUG開始コドンなしでもタンパク質翻訳を引き起こす現象が明らかになりました。これが「RAN翻訳」と呼ばれる現象です。主な特徴は以下の通りです。
- 非典型的な翻訳開始
リピート配列は、AUGなどの定型的な開始コドンがなくても、リボソームによって認識され翻訳が開始される可能性があります。これには、リピート配列特有の安定した二次構造(ヘアピン構造など)が関与しており、リボソームがこれらの構造を足掛かりとして翻訳開始部位を決定するという仮説が提唱されています。 - 多様な枠(フレーム)での翻訳
通常、リボソームがAUGを基点として翻訳すると読枠が決まりますが、RAN翻訳では、異なる3つの読枠で翻訳が行われ、複数の異なるタンパク質(またはペプチド)が産生される可能性があります。このことは、同じリピート配列由来でありながら、病態に対して多角的な影響を与えることも意味します。 - 疾患関連性
RAN翻訳により産生されるタンパク質やペプチドは、しばしば凝集しやすく細胞内で毒性を示すことがわかっています。たとえば、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や前頭側頭型認知症(FTD)においても、C9ORF72遺伝子内のG4C2繰り返し配列がRAN翻訳を引き起こすことが示されており、これが神経変性の一因であると考えられています。今回取り上げたミオパシーやてんかんの場合も同様の機序が働いている可能性が指摘されます。
3. RAN翻訳がもたらす生物学的および病理学的意義
細胞内タンパク質の異常蓄積
RAN翻訳により産生されるタンパク質は、通常のタンパク質とは異なり、機能を持たない場合が多い上、細胞内で凝集しやすい性質を持っています。この異常なタンパク質の蓄積は、細胞のプロテオスタシス(タンパク質の品質管理機構)を乱し、細胞死(アポトーシスやネクローシス)に繋がる可能性があります。
新たな治療標的への展開
RAN翻訳は、従来のRNA毒性説やタンパク質凝集仮説だけでは説明できない神経疾患の発症メカニズムの一端として注目されています。これにより、RAN翻訳自体を抑制する、または異常タンパク質のクリアランスを促進する治療法の開発が期待されています。
また、開始コドン以外での翻訳開始という意外性は、細胞内の翻訳制御における新たな規制機構やシグナル伝達系の解明へも寄与する可能性があります。
4. 現在の研究動向と今後の課題
研究の進展
近年、多くの研究グループがRAN翻訳を詳細に調べるために、細胞実験や動物モデルを用いた解析を進めています。これにより、リピート配列の二次構造と翻訳開始の関係、さらに翻訳産物の細胞内におけるふるまいや毒性メカニズムが徐々に解明されつつあります。
今後の課題
- メカニズムのさらなる解明
どのような分子メカニズムや細胞内環境条件がRAN翻訳を促進するのか、または抑制するのか、詳細な研究が必要です。 - 治療法の開発
RAN翻訳による毒性タンパク質の産生を抑制するための分子標的や、異常タンパク質の除去メカニズムについて、臨床応用を見据えた研究が進められる必要があります。 - 診断法との関連
異常なリピート配列およびその翻訳産物がバイオマーカーとして用いられ、早期診断や病状の進行モニタリングに役立つ可能性も模索されています。
総括
異常なリピート配列の発見および、開始コドンがなくても行われるRAN翻訳は、神経疾患(ミオパシー、てんかんなど)における新たな病因解明の一端となっています。従来のタンパク質翻訳の常識に挑戦するこの現象は、細胞内で異常タンパク質が産生されることで神経細胞の機能障害や死に至るメカニズムの一部を説明し、また新たな治療標的としても注目されています。これからの研究の進展により、より具体的な治療戦略や診断技術の確立につながることが期待されます。
観想(2020/07/11)
mRNAからタンパク質に翻訳している機関はRibosomeであるが、Ribosomeがエラーしていると考えられるのか疑問に残った。Ribosome自体の頑健性に関わっている可能性があるもあるかもしれない。
この疑問にAIが答えた(2025/04/14)
mRNAからタンパク質に翻訳している機関はRibosomeであるが、Ribosomeがエラーしていると考えられるのか疑問に残った。どう解釈されているのか?
ChatGPT:
とても本質的なご質問です。
RAN翻訳(Repeat-Associated Non-AUG Translation)では、確かに通常のAUGによる開始ルールを無視してタンパク質が産生されるため、「リボソームがエラーを起こしているのか?」という疑問が生じるのは自然なことです。
この現象について、現時点での研究者の解釈と分子メカニズム仮説を以下のように整理して解説します。
❶ リボソームの「エラー」ではないという見解
▶ 基本的立場:
**RAN翻訳は「エラー」ではなく、ある種の「非正統的な翻訳開始メカニズム」**と考えられています。
つまり、リボソームが暴走しているわけではなく、「異常なRNA構造や細胞環境の条件下で、意図せず自然に起こる代替的な翻訳開始様式」であるというのが主流の見解です。
❷ RAN翻訳の機構に関する現在の理解
1. RNA構造の影響
異常に伸長したリピート配列(例:G4C2, CAGなど)は、
- G-quadruplex構造
- ヘアピン/ステムループ構造
などの強い二次構造をとることがあります。
🔸これにより、リボソームがmRNA上で異常な停滞・スキャニングをするようになり、
本来のAUGコドン以外の部位で翻訳を開始してしまうのではないかと考えられています。
2. リボソームのキャップ依存/非依存的開始
通常、翻訳開始は次の順に進みます:
- mRNAの5’末端のキャップ構造をリボソームが認識
- AUG開始コドンまでスキャン
- AUGで開始
一方、RAN翻訳では:
- キャップ依存性が弱くなるまたは不要
- 開始コドンがなくても、繰り返し配列内から翻訳が始まる
このことから、「リボソームが異常な構造を誤ってAUGと誤認する」「翻訳開始因子の異常利用」などのメカニズムが疑われています。
3. 翻訳開始因子の関与も一部で示唆
研究により、以下のような非正統的翻訳を助けるタンパク質の関与も示唆されています:
- eIF2A(通常と異なる翻訳開始を担う因子)
- eIF4G, eIF4Aなどのキャップ依存経路以外を使う因子
つまり、リボソーム単独の異常ではなく、翻訳の「開始ルール」を逸脱するような、RNA構造や翻訳補助因子の複合的な異常利用が関係していると考えられています。
❸ 現時点の仮説まとめ
| 項目 | RAN翻訳の仮説的解釈 |
|---|---|
| ❓ リボソームのエラーか? | ✕ エラーではなく、「非正統的な機構」 |
| 💡 開始のきっかけ | RNAの異常な二次構造が誘引 |
| 🔧 翻訳因子の関与 | eIF2Aやその他補助因子がAUGなし翻訳を許容する可能性 |
| 🎯 結果 | 本来の目的と異なる翻訳が起こり、毒性タンパク質が生じる |
❹ 今後の研究課題
- なぜリボソームが繰り返し配列を開始点と誤認するのか?
- どの翻訳開始因子が関与しているのか?
- 正常細胞でもRAN翻訳が起きるか?
- RAN翻訳の抑制が治療に繋がるか?
これらは現在も活発に研究が進められているテーマです。
✅ 結論
RAN翻訳は、リボソームのエラーではなく、リピート配列の異常構造や特異的な翻訳因子の関与によって引き起こされる、特殊な翻訳開始現象と理解されています。
リボソームは依然として「正確に動作」しているが、その起動のきっかけが異常な形で与えられている、というイメージが妥当です。
編集履歴
2020/07/11 Mr.はりきり
2025/04/14 追記(with ChatGPT)