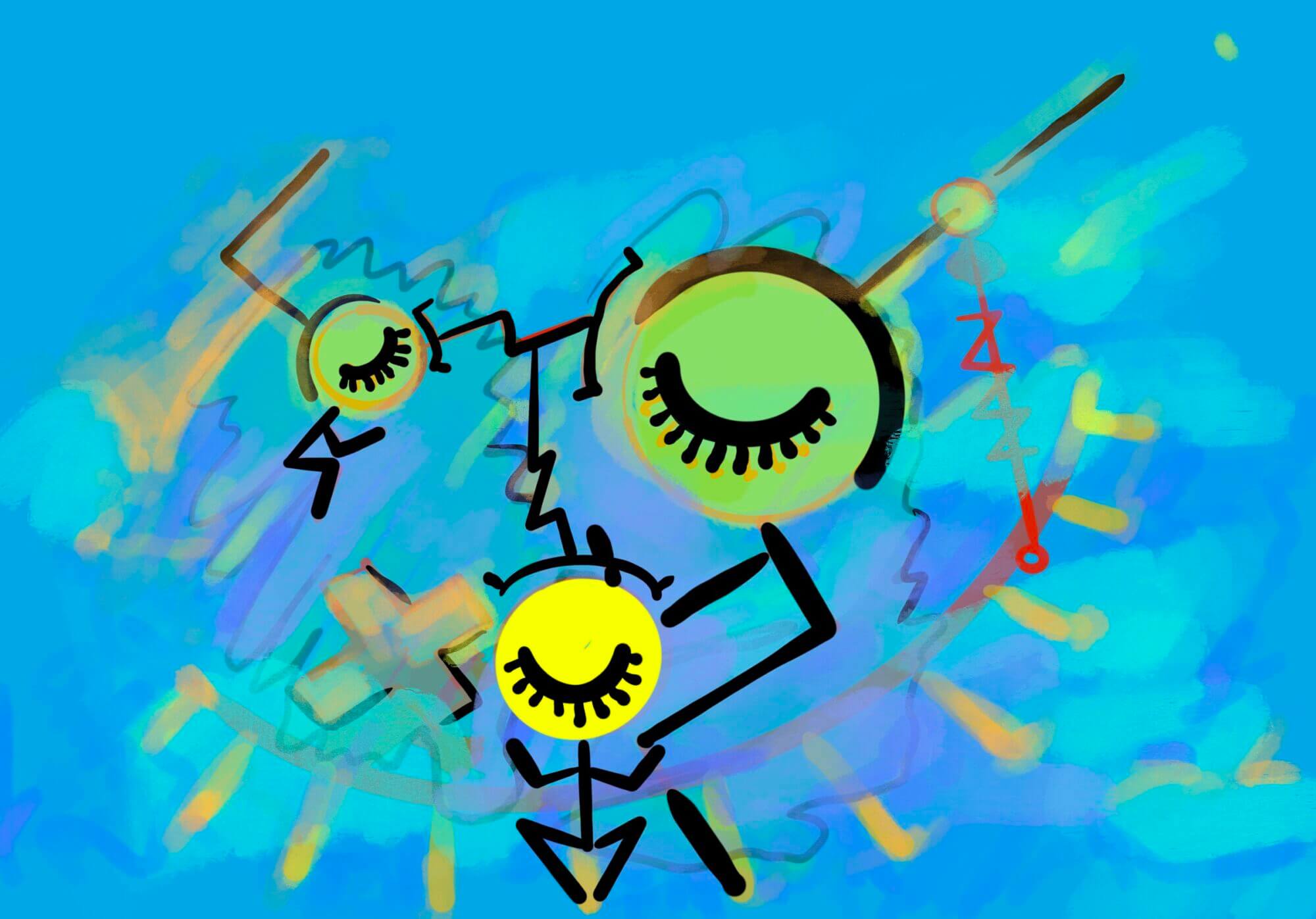はじめに
根本原因分析(Root Cause Analysis: RCA)は、問題や不具合の「真の原因(根本原因)」を特定し、それに対する対策を講じることで、再発防止を図る手法です。製薬業界においては、GMP遵守、品質保証、製造プロセスの最適化などの観点から極めて重要な分析手法です。
AIに聞いてみた
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
RCAとは
問題の「本当の原因(真因)」を追究するための分析手法で。
🔷 1. RCAの基本概念
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 単なる表面的な原因(例:ヒューマンエラー)ではなく、**なぜそれが起きたのか?**を繰り返し問うことで、**根本的な原因(systemic issue)**を明らかにする |
| 最終目標 | **再発防止策(Corrective Actions)と未然防止策(Preventive Actions)**の構築 |
| 代表的手法 | 5 Whys、Ishikawa Diagram(フィッシュボーン)、FMEA、Fault Tree Analysis(FTA)など |
🔷 2. 製薬業界における適用場面(共通)
| 適用ケース | 説明 |
|---|---|
| 逸脱(Deviation)発生時 | 製造や試験で手順逸脱、工程逸脱があった場合、その原因調査としてRCAが必要 |
| OOS/OOT(試験結果の異常) | 結果が規格外または傾向外となった場合、その原因を明確にする |
| 回収(Recall)対応時 | 市販後に不具合が発覚した際、根本原因を究明して再発防止策を講じる |
| 工程設計/バリデーション失敗時 | プロセスバリデーション(PV)の失敗・変動要因調査などでも用いられる |
| CAPA(是正予防措置)支援 | RCAはCAPA文書の一部に組み込まれ、原因分析の根拠資料となる |
🔷 3. RCAの活用:低分子 vs バイオ医薬品における違い
| 観点 | 低分子医薬品開発 | バイオ医薬品開発 |
|---|---|---|
| 対象物の安定性 | 化学的に安定な物質が多く、逸脱は装置・操作ミスに起因することが多い | 複雑な構造と環境依存性のため、温度・pH・剪断力・宿主由来因子など多因子が絡む |
| 製造プロセス | 精密な化学合成工程。原料や合成ルートの純度・反応条件が主因 | 細胞培養・精製工程における変動(例:培養pH・収量・プロテアーゼ活性)が問題となりやすい |
| 典型的なRCA事例 | – 合成反応の不完全 – 製造装置の不具合 – 試験法の誤差(機器校正など) | – 発現量の低下 – 溶液中の凝集体発生 – バイオ負荷によるフィルター閉塞 – クロマト精製の分離不良 |
| 分析支援法 | FTIR, HPLC, GC-MS等による不純物特定 | ELISA, SDS-PAGE, CE-SDS, LC-MS等の構造・活性評価がRCAの補助に |
🔷 4. RCA導入のフロー(製薬現場の例)
① 問題の特定 →
② 初期調査(事実確認) →
③ RCAチーム組成(品質保証・製造・分析・技術) →
④ 原因候補の洗い出し →
⑤ 分析(5 Whys、フィッシュボーン) →
⑥ 真因特定 →
⑦ CAPA設計・実行 →
⑧ 効果検証・記録化
🔷 5. 規制当局の要求事項との関係
| 規制・ガイドライン | RCAに関する要求・位置づけ |
|---|---|
| ICH Q10 | 品質マネジメントシステムにおいて、「逸脱の根本原因分析と是正予防措置」を求める |
| FDA警告書 | RCAの不備はよくある指摘事項:「不適切な原因特定」「繰り返し発生」「根拠不十分」など |
| EU GMP Annex 20(QRM) | リスクマネジメントにおける原因分析はリスク評価の中核とされている |
🔚 まとめ
根本原因分析(RCA)は、品質確保とリスクマネジメントの両面で不可欠なアプローチであり、
- 低分子では操作や設備の不具合を中心に
- バイオ医薬では生物学的変動や複合因子に着目する必要があります。
CAPA設計や製品品質の継続的改善のためにも、科学的かつ多角的なRCAの導入が推奨されます。
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
QbDやQRAでの使用ケース
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
はい、**RCA(Root Cause Analysis)**は、**QbD(Quality by Design)や品質リスク分析(QRA: Quality Risk Assessment)**においても、支援的な分析・判断ツールとして非常に重要な役割を果たします。
🔷 1. QbDとRCAの関係
✅ QbDにおける目的と構造
QbDは「製品・プロセスを科学的根拠に基づいて設計し、ばらつきに強い品質保証を実現する」アプローチであり、主に以下の要素から成ります:
| QbD要素 | 内容 |
|---|---|
| QTPP | 最終製品の品質目標 |
| CQA | 製品品質に影響を与える特性(Critical Quality Attributes) |
| CPP | 製造工程の中でCQAに影響する因子(Critical Process Parameters) |
| Risk Assessment | CQA・CPP同定のためのリスク分析 |
✅ RCAとの関係
QbDプロセスにおいて、RCAは次のような役割で使用されます:
| 用途 | 活用例 |
|---|---|
| 過去の逸脱・失敗の分析 | 開発初期における失敗知見から設計空間(Design Space)の設計要素を導出する |
| CQA/CPP設定時の因果関係分析 | CQAに影響(製品に影響)を与える工程要因を根本的に洗い出す際にRCAを利用 |
| 工程改善・再設計 | DoE結果のばらつきやPV失敗時に、RCAで因子同定 → 新たなCPP候補に反映(再設計につなげる) |
🧩 例:培養pHがわずかに変動すると発現量が不安定 → RCAで攪拌制御の異常が真因と判明 → CPPに設定
🔷 2. 品質リスク評価(QRA)との関係
✅ QRAの定義
QRAは、製品品質や患者安全性に関わるリスクを、体系的かつ文書化して評価・管理する手法です(ICH Q9に準拠)。これは,リスク低減策を設計するプロセスです。以下のようなQRAツールにRCAを活用しリスクを明確化します.
| 主なQRAツール | 説明 |
|---|---|
| FMEA(Failure Mode and Effects Analysis) | 事象の失敗モードと影響度を分析し、リスクを定量化 |
| FTA(Fault Tree Analysis) | トップレベルの事象から原因要素をロジック的に分解 |
| HACCP(製造上の重要管理点分析) | 食品・製薬向けプロセス管理手法 |
🧩 例:ろ過工程の膜閉塞発生 → RCAでバイオバーデンの増加が真因と判明 → FMEAの「原因」記載を更新し、SOPと監視項目に反映
✅ RCAとの統合的使用
| 活用場面 | 説明 |
|---|---|
| FMEAのフォローアップ | 高リスク項目に対してRCAを使って実因を深掘りし、CAPAの根拠とする |
| 逸脱に基づくリスク再評価 | 逸脱イベントに対するRCAの結果が、リスクランク再評価や制御戦略の見直しに貢献 |
| リスクレビュー | 製品ライフサイクル管理(PLCM)での再評価プロセスにRCA結果を統合可能 |
🔷 3. FDAでの位置づけ
| 規制文書 | RCAの関連記述(要旨) |
|---|---|
| FDA PVガイドライン(2011) | 「プロセス不具合の根本原因調査は、持続的改善と変更管理の起点である」 |
| FDA警告書・483指摘事項 | RCAの「不十分」「表面的」であるとの指摘多数 → GMP遵守上もRCAの精度が問われる |
🔷 4. RCAに言及・関連するICHガイドライン一覧
| ICHガイドライン | 関連内容 | RCAとの関係 |
|---|---|---|
| ICH Q9 (Quality Risk Management) | 品質リスクマネジメント手法(例:FMEA、FTA、HACCP)を紹介し、リスク発生時の評価と制御を推奨 | リスク要因の特定・評価後、真因分析手法としてRCAの導入が推奨されている |
| ICH Q10 (Pharmaceutical Quality System) | 逸脱、CAPA、変更管理、継続的改善を含む製薬品質システムの枠組み | CAPA実施のための真因特定手段として、RCAが明示的に記述されている |
| ICH E6 (R2) (GCP:臨床試験の品質管理) | 臨床試験における品質リスクマネジメントと問題対応の重要性 | 問題発生時の「root cause identification」の必要性が記載されている(3.4項など) |
| ICH Q7 (GMP for API) | 原薬製造における逸脱管理・文書管理・変更管理を規定 | 逸脱時の調査と是正において、原因分析(RCA)によるCAPA設計が求められる(2.15項など) |
| ICH Q5A/B (ウイルス安全性・製品均一性) | バイオ製品のウイルス不活化工程や製品の安定性管理 | 不具合発生時に再発防止のためのRCA適用が含意される場面あり(明示はされないがGMPとの連携で重要) |
| ICH Q12 (Product Lifecycle Management) | 製品ライフサイクル管理における変更管理や継続的改善 | 変更管理プロセスでの変更理由の正当化にRCAが支援的に活用されうる(リスクベースアプローチ) |
🔹 補足事項
- ICH Q9/Q10が最も明示的にRCAの必要性を記述しています。
- Q7やQ12では、明示されていないこともありますが、「適切な原因分析に基づく対応」としてRCAの導入が事実上求められていると解釈されます。
- E6(GCP)においても、臨床試験でのデータ不整合や逸脱に対してroot causeを特定する品質管理体制が重視されています。
✅ まとめ
RCAが関与するICHガイドライン:
- ICH Q9:品質リスク評価 → RCAはリスク要因の真因分析手法
- ICH Q10:CAPA・逸脱対応 → RCAは是正予防措置の基礎
- ICH Q7:原薬GMP → 逸脱管理・調査手段としてRCA
- ICH Q12:変更管理 → 理由の裏付けとリスク再評価にRCA活用
- ICH E6 (R2):臨床品質管理 → データ逸脱等への根本原因分析
- ICH Q5A/B:バイオ製品の問題分析におけるRCAの必要性(間接)
🔚 総括
RCA(Root Cause Analysis:根本原因分析)は、製薬業界において逸脱・OOS・CAPA・プロセス不具合の真因を科学的に特定し、再発防止策を講じるための重要な手法です。QbDでは、工程設計やCQA/CPPの同定において、過去の失敗要因分析としてRCAが活用され、品質設計の科学的根拠となります。また、品質リスク評価(QRA)においては、リスクの特定やFMEAにおける原因構造の裏付けに寄与します。RCAはICHガイドライン(Q9, Q10, Q7, Q12, E6など)に明示的または補足的に位置づけられており、特にICH Q10ではCAPA実施の要として、Q9ではリスク管理の一環として重要視されています。RCAは、品質問題に対する体系的・再現性のある対応手段として、GMP遵守、製品品質の確保、継続的改善の実現に不可欠です。
編集履歴
2025/04/20 Mrはりきり