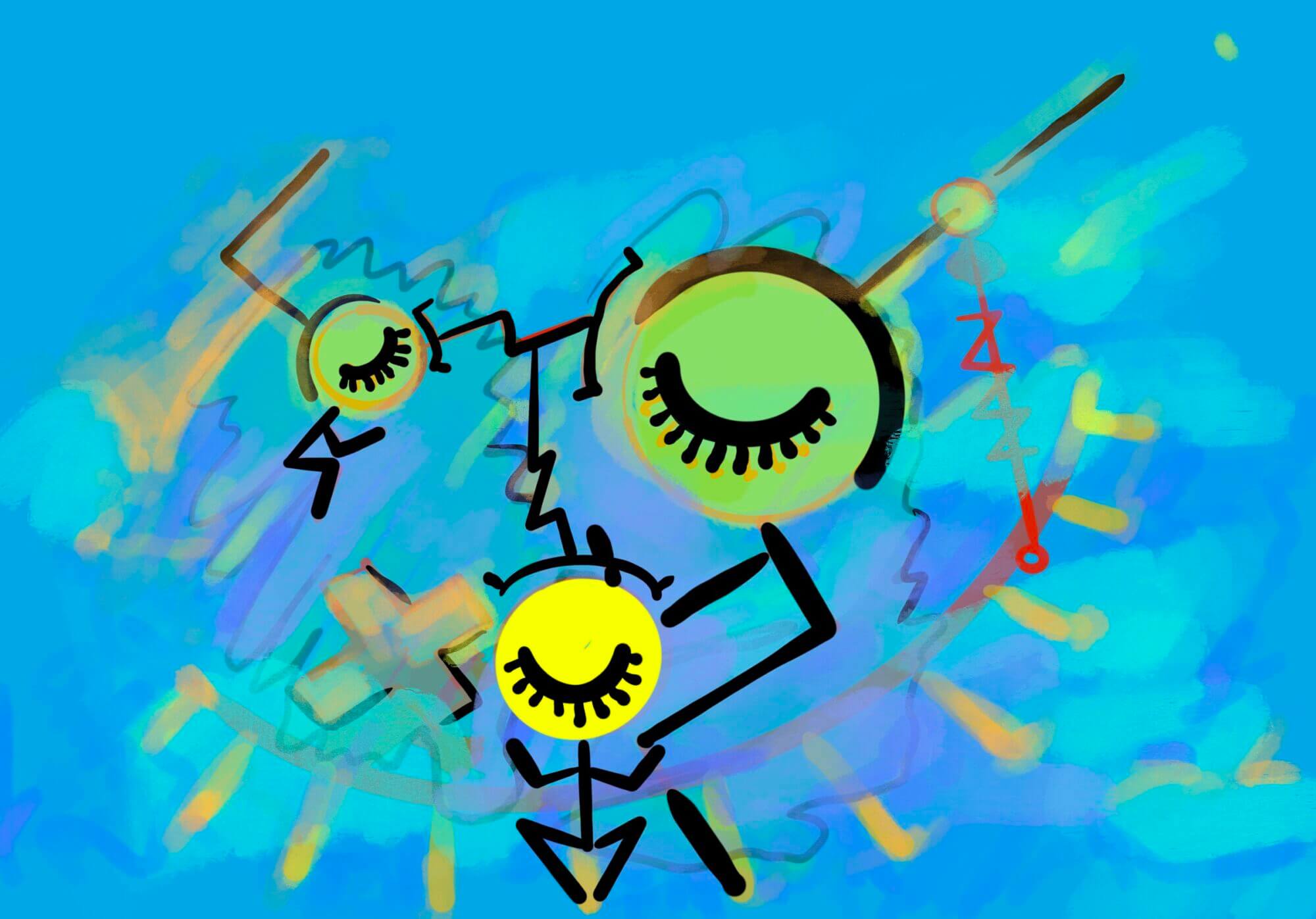カテゴリー: BIOLOGICS
-
気になる企業 – ファーメランタは組換え大腸菌でオピオイドの商用生産を目指している – コマーシャル製造にはどの程度の生産量が必要かAIに試算してもらった! [2025/05/19]
Post Views: 91 はじめに バイオベンチャー企業であるファーメランタは,組換え大腸菌によりオピオイ…
投稿者

-
Exosome – エキソソーム医薬品開発の歴史と今後のコマーシャル製造に向けた課題となる安定化剤についてAIに聞いてみた! [2025/05/16]
Post Views: 85 はじめに Exosome医薬品の開発の歴史についてAIに聞いてみた.1980年代…
投稿者

-
医薬品製造 -Automated Visual Inspection [2025/04/19]
Post Views: 154 WILCO AGの「EVO CAX 20」は、高品種少量(High-Mix/L…
投稿者

-
[Bio-CDMO] AGC Biologicsのバイオ医薬CDMO体制:統合解説(2025年版)
Post Views: 238 AGC Bilogics:企業概要と展開 **AGC Biologics(旧:…
投稿者

-
[Biologics] 「台湾バイオCDMO 4社の受託実績・設備・国際展開の徹底比較」[2025/04/19]
Post Views: 248 はじめに 近年、アジアのバイオ医薬品産業が急速に台頭する中、台湾のCDMO(開…
投稿者

-
[AAV] dual AAVによる大きな遺伝子の導入技術 [2025/04/17]
Post Views: 213 はじめに **dual AAV(2つに分割して送達)**することで,4.7kb…
投稿者

-
[Bio-Lab] 透析=濃縮/脱塩 = UF/DF.すなわちバッファ置換するためのラボ用装置にはどんな製品があるか解説する – ID8580 [2025/04/17]
Post Views: 303 透析 バイオ医薬品の開発において透析というのは,液状のサンプルの組成を置換する…
投稿者

-
[AAV] 急速に進化をつづけるアデノ随伴ウイルスベクター [2025/04/16]
Post Views: 142 はじめに アデノ随伴ウイルスベクター(AAVベクター)は、遺伝子治療分野で最も…
投稿者