技術者としての特許の理解
通り一辺倒の教育だけでは、理解は決して深まらない
「特許の流れ」は手続きなので、理解は容易です。しかし、特許文献としてその特許の範囲を理解したり、自分で特許を書く場合手続きではないので、その理解は容易ではありません。今回、特許の内容の理解、特許を書くこと、について方法論を論じている論文を紹介します。
特許に関わる役者には、現場レベルの研究者/技術者と、特許の専門家である弁理士、また、その間を繋ぐ組織内の専門組織やスタップがいます。
昔から、「リエゾン」(参考1)を進める動きはありました。特許部門からの提案は、ある時、突然出てきます。しかし、特許の査定を中心とした思考活動を学ぶことに、専門外となる研究者/技術者は、なかなか真剣に取り組みません。
技術者は、最低限において技術の内容が理解できれば良いため、特許成立に関わる基準が分からないまま、特許の内容を限定的に理解していることが多くあると思われます。
これが、リエゾンが進まない大きな要因であると、僕は考えています。
しかし、現場で特許に関する知識が、あやふやのままで良いのでしょうか?。折角の新規の技術が見つかったとしても、認知もできずに公知化することによる技術の流出や、競争相手の特許内容の理解が乏しく、対策が遅れたいするリスクが高まります。
私も含めて、特許クレームを本当に、腹落ちするように理解ができているのでしょうか?
今回、この文献を読んで、私は、腹落ちがしました。通り一辺倒の同じような教育やその内容を理解しても、堂々巡りです。尖った内容でアプローチの異なる理解により、停滞していた理解を深められます。
今回、この文献を読んで、相当程度の理解が深まったと感じています。
本当の研究者/技術者になる
自分たちで見つけた新規技術を特許申請することは、競業他社の特許を読み解くよりは、遥かに簡単です。
外部環境がどうなのかを知り、それを受けて自分たちの強みをどのように維持し、或いは、強めていくのか、そのためには、正確に外部環境を理解する必要があります。
そこで、他社特許(査定中を含め)に対して、その特許クレームは、どのように読み解けばいいのか、未だ査定中で特許に至っていない公開段階で、そのクレーム内容を読み解いた時、すべてのクレームに特許性があるのか、その特許を受けるに値しないクレームはどれなのか、今後、特許として査定される範囲はどれくらいなのか、そのような判断を迫られる場面は、新規技術に関わる研究者/技術者として遭遇する事は多いと思います。
特許の専門家にコメントを求めることは、当然必要です。しかし、実務レベルでも試行錯誤しなければならない場面も沢山あり、いつも、専門家のコメントを求めていれば、判断が遅れます。
スピードが求められる場合や小さな組織では、多能であることも求められます。
今回、レビューした1つの文献は、そうしたあやふやな技術理解ではなく、明確なメソッドとして、クレームを理解し、また、逆にクレームを書くスキームを提案しています。
対象発明の理解を通じたクレーム作成方法 の提案,そしてその応用 – パテント (2013), Vol.66, No.13
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201311/jpaapatent201311_045-060.pdf
Udemyのビデオ学習
今回の文献執筆者である大瀬さんが、以下に紹介した内容のオンライン教材としてUdemyでの受講が可能になりました。約60本のビデオによる解説と実習は、殆どが5分程度、長くて10分の講義です。僕もこの講義を受講し、2020/11/29に全ての学習を完了したので、少しレビューを述べたいと思います。
講座タイトルは、「初心者でもわかる特許の書き方講座【初心者向け】【弁理士が教える実践特許講座】」です(定価12,600円)。
副題 は、「特許知識ゼロでも大丈夫!自分の力で発明を文章にして特許書類が作成できるようになります。「発明を理解、把握するステップ」と「理解した発明を特許文章にするステップ」の2つのステップで誰でも簡単に「特許の書き方」を身につけることができます。」
僕にとって、講座内容の最も重要な部分は、以下の項目の実習に尽きました。
- 実務として技術を「要素」、その「属性」、および、それらの「関係」について全てを、エクセル表などに列挙していくメソッド
- 以上で、とりまとめた「要素」、「属性」、および「関係」の説明文をほとんどそのままを使って請求項に記述していくメソッド
これまでに、複数の書籍を購入し特許の勉強をしてきましたが、実務としてここまで、有益な情報を得ることが殆どできなかったことで、独学に限界を感じていました。しかし、今回、書籍ではなく、オンライ・ビデオ学習によって、また、特に技術者にとってわかりやすい開発されたメソッドによって、請求項というものが、3の要素、すなわち「要素」、「属性」及び「関係」からなっていることを、具体的な事例を実習することで、より良く短時間に知ることが出来ました。その結果、特許の請求項を書くことは、もちろん、誰かが書いた既存の特許の請求項を構造的に理解することができるようになったと思います。大変有意義な講義でした。大瀬さんに最大限の感謝を表します (2020/11/29, はりきり(Mr) )。
予備知識
クレーム
- 1つのクレーム(請求項)は、1つの発明である。
- 特許請求の範囲は、36条4項1号を満たすこと : 特定の課題を解決できること
- 要素列挙形式 (一般的)
- 構造的クレーム形式
一般的な要素列挙形式
まずは、「構造的クレーム形式」を読んで、用語を理解した上で、以下の要素列挙形式を読み進めてください。
- 要素間の関連性が多くなると複雑な文章に陥りやすい
- 曖昧な内容になりやすい
構造的クレーム形式
「構成」とは、「要素」、「属性」、「関係性」を総称する。
この構成を意識すれば、日本語がシンプルになり、クレームを読み込むことも、クレームを作成することも容易になります。
- 日本語の文章がシンプルになる
- クレームが多義的になりにくくなる
- クレームが不明瞭になりにくくなる
- 補正がし易くなる
- 外国語への翻訳がしやすくなる
- 「要素」 (外的不可)
- 「装置」の場合は、「部品」のこと
- 「方法」の場合は、「単一の工程(ステップ)」
- 「プログラム」の場合は、単一の演算を行う「関数」
- 「属性」:要素の属性 (内的付加)
- 絶対的な規定のこと
- 色
- 形
- 一般名(ねじ、バネ、キャップ)
- 絶対的な規定のこと
- 「関係性」:要素同士の関係性 (特許の世界では組合せという用語が近い)
- 「要素」間の関連性を相対的に規定すること
- 丁寧な観察により他との比較を行うことで、見つけ出す
- AとBは接続されている
- Aは、Bの軸受けにより支持されている
- AとBは、適切なな距離の間隔がある
請求項の事例
- 請求項1 (独立請求項)
- 要素は、aとbを備え
- 属性は、cとdであり
- 関係性は、eとf
- である「装置」
- 請求項2 (従属請求項)
- 要素は、gを備え
- 関係性は、i
- である「請求項1」の「装置」
従属請求項は、上位概念のクレームに対して、新規性違反などの拒絶理由が出された際に、争える内容となるように構成しておく役目を持たせるのが良い。
特許を理解するとは
対象の発明の内容を理解すること。
- 刺激 → (発明) → 反応、を理解できている
- 多様な「刺激」に関しても理解できている
理解を進める作業
マインドマップを活用できる。
- 「要素」(部品)を抽出する
- 「要素」の振る舞いを理解していること
- 例えば、Aユニット、Bユニット、処理部
- 要素の「属性」を抽出する
- 最小の単位で抽出する
- 複数もあり得る
- 色
- 硬さ
- etc.
- 要素間の「関係性」を抽出する
- 最小の単位で抽出する
- 複数もあり得る
- AとBは接続されている
- Bとそは接続されている
- モデル化
- 構造化 = (要素-属性) x 関係性
- 試動
- 刺激 → 構造体 → 反応、を観察
- 発明の理解
- 以下の反応が同一の結果となれば、発明について理解している
- 刺激(入力) → (発明) → 反応(出力)
- 刺激 → 構造体 → 反応
- 理解できたと、構造体の細部が描かれていることになり、完全に理解したと言えます。
- 以下の反応が同一の結果となれば、発明について理解している
- 考察
- 付随する機能の気づき
機能・効果
(要素、属性、関係)
1)「新規構成の抽出」へ
2)「発明の詳細な説明」、「課題を解決するための手段」として「明細書」へ
新規構成の抽出
(従来技術調査)
1)「上位概念の発掘」へ
2)「背景技術」、「先行技術文献」として「明細書」へ
上位概念の発掘
1)「構造的クレーム」へ
2) 「変形例」、「産業利用性」として「明細書」へ
構造的クレーム
明細書
構造的クレームの書き方
以上を理解していれば、上記、「請求項の事例」に従ってクレームを作ることで、クレームを書くことができます。
「発明の詳細な説明」欄
- 構成の説明
- 機能・作用の説明 : 実例レベルの説明。将来に補正する場合の自由度の担保の役割として利用する。[課題を解決するための手段]での、上位概念化された対象発明が課題を解決することを説明するのと異なる
- 変形例 : 上位概念化作業の際に見つけた上位概念と含まれる下位概念を記載する箇所。〜のような機構があれば、どのようなものでも構わない。
「課題を解決するための手段」欄
- 「特許請求の範囲」をそのままコピペすることが多いが、それをすると、出願後の拡張(不要構成の削除)補正する場合に、それが新規追加事項になる危険性があります (出願当初の請求項の「すべての構成」が課題を解決するために必要と認定されると)
- 請求項1に記載の発明がどのように機能・効果を発揮するかを簡潔(不要な構成を紛れ込ませない)に記載する
「発明が解決しようとする課題」欄
発見した新規構成(要素、属性、関係)を規定として、権利化したい構成をクレームする手法を
- なぜ、記載順が、「発明が解決しようとする課題」、「課題を解決するための手段」としないのか : 権利化を目的としているることから、発明内容に従った課題とすべきとの考え
- 請求項1 : 要素を羅列、属性および関連性
- 請求項2 : 要素を羅列、属性および関連性
- ・・・
注意点
構成は漏れなく含まれていれば、不要なものがあったとても試動で完全に動かすことができます。即ち、冗長なものが、含まれている可能性を否定できません。
- 振る舞いに貢献していない記述を削除する
- これを、割り算型クレーム構築手法、といいます
割り算型クレーム
- 「部品」クレームにまで、削ぎ落とすことは、難しい
掛け算型クレーム構築法の書き方
- 構成を更に付加して、上位概念をクレームする。
- 帰納的に推論する
- 上位概念とは、共通するということ。それをもっと普遍的な言葉に置き換える
- 掛け算型クレームは、「部品」クレームになりやすい
- 発明の本質の抽出 (新規性、進歩性) : 従来の全ての技術と比較して
- 構成が一致していれば、効果も同一のはず
- 但し、「要素、属性、関係」と効果との因果関係が自明でない技術領域(化学、材料、バイオ)
- 構成(要素、属性、関係)が、それぞれ開示されていたとしても、その効果が非自明であれば、進歩性がある場合があります
- 要素同士の関連性がないのであれば、「寄せ集め発明」です
- 従来技術の組み合わせの場合は、新規性が無いことが基本ですが、阻害要因がありそれを解決できれば、新規性はあると思われます(コメント)
完成品クレームと部品クレーム
- 部品クレームの方が権利範囲が広い
上位概念化万能論への反論
- 先ずは、不要構成を極限まで削ぎ落とすことが、広い権利を確保できる
- その後、上位概念化して、広い特許範囲にしていく。
知的労働の自動化
- 構造化することでAI処理の容易性が挙げられる。
- 構成(要素、属性、関係)は、部品として再利用できる
- これらをデータベース化して、クレームの自動生成
- 特許翻訳の自動化
- 先行技術調査の自動化
- 特許網構築状況の可視化
- イ号製品被覆状況の可視化
参考
参考1
パテントリエゾンマン養成講座 – より
https://www.nihon-ir.jp/patent-liaison-man/
パテントリエゾンマン(特許リエゾン担当者)とは、技術者が発明創出をサポートするとともに、その発明を戦略的に活用することを考える立場の人をいいます。今、特許業界で必要とされているのは優秀なパテントリエゾンマンの存在です。
編集履歴
2020/04/10 はりきり(Mr) 2020/11/29 追記(今回紹介した「対象発明の理解を通じたクレーム作成方法 の提案,そしてその応用 - パテント (2013), Vol.66, No.13」の筆者である、大瀬さんが開発した本内容のビデオ教育プログラムについて受講したので、その概要)
![[特許] クレーム内容を理解するために文献レビュー —「対象発明の理解を通じたクレーム作成方法の提案、そしてその応用」、パテント (2013),Vol.66, No.13 – / Udemyのオンライン・ビデオ講座 で完結する – ID13101[2020/11/29]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/05/51FEA33E-56F1-4896-8958-9DCDDB225BD2.jpeg)
![[COVID-19] 世界のCOVID-19アプリ – イギリス、アメリカ、シンガポール、韓国 (NHK 7時のニュース)](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/04/CEEBD8EE-9D2E-4F43-B074-64ABE84F4C6B.jpeg)
![[Bio-Edu] 沈殿化法によるタンパク質の回収・分離 – 検討方法 – ID4376 [2025/04/21]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/02/80F3D755-3019-49C6-BDAE-47D137C87826.jpeg)
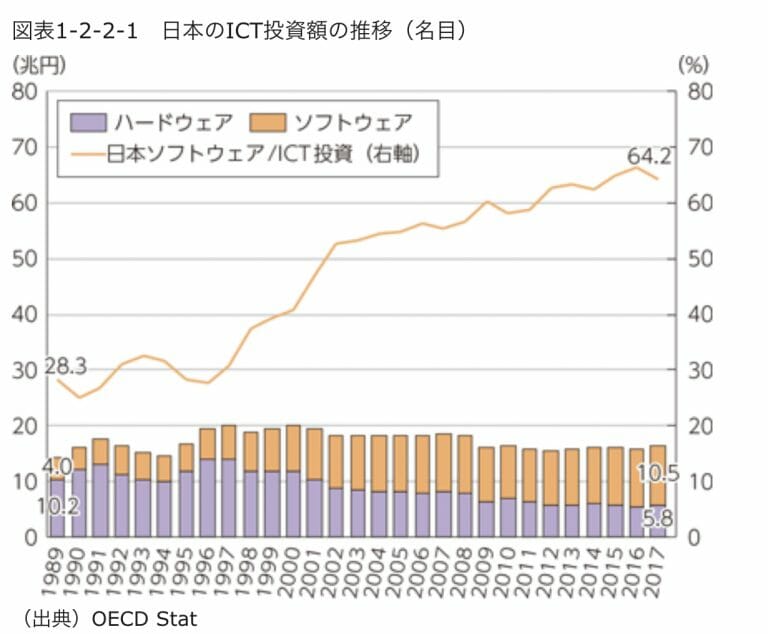
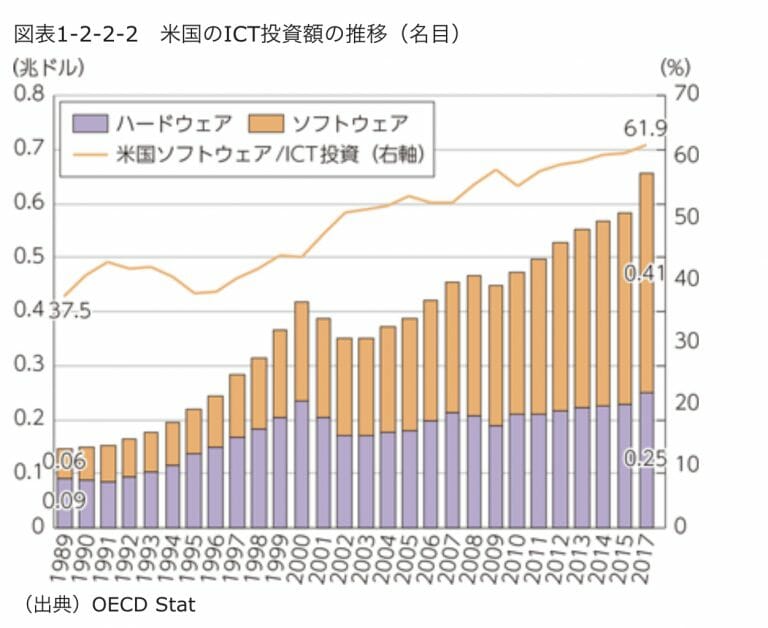
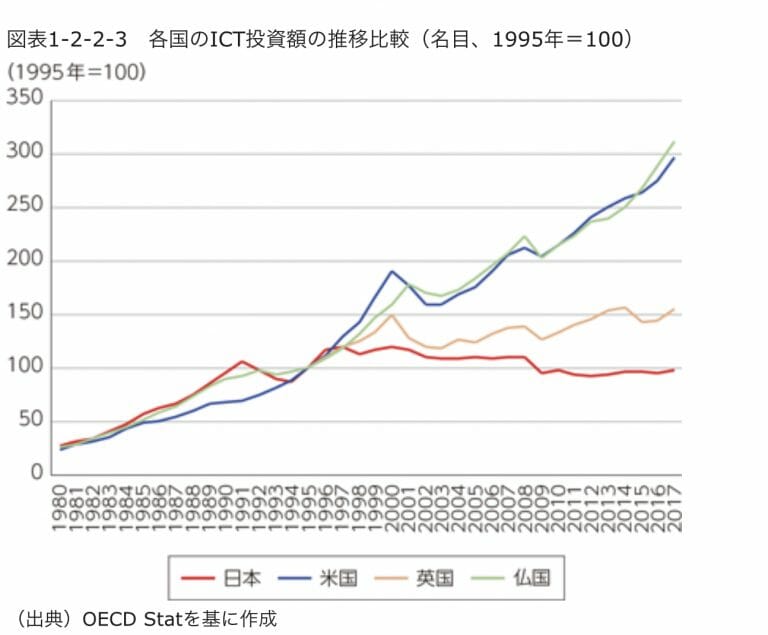
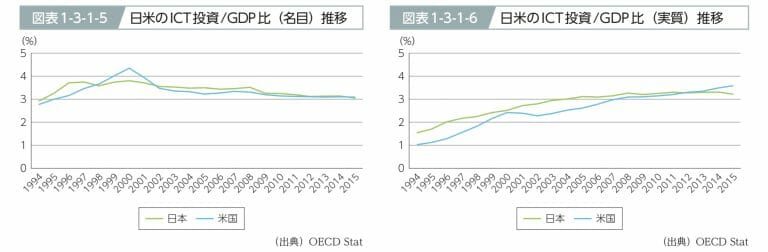
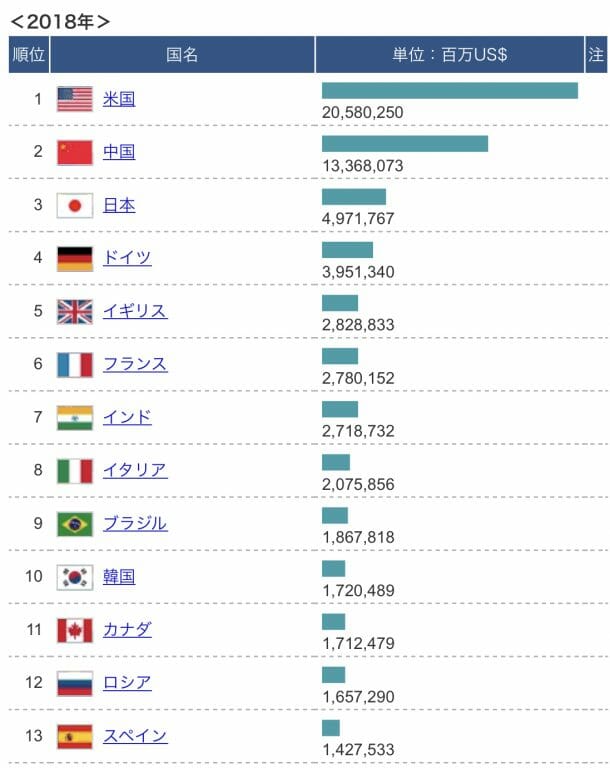
![[Virus-Edu] WHO が、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の治療薬に関する大規模臨床を開始する – ID13021 [2020/04/09]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/03/38256752-5BF6-4A83-BA92-9BDD15E138FB.png)
![[Kw] 浅草寺の大提灯は、戦時の焼失以来、京都の高橋提灯で10年毎に貼り替えられている [2020/04/08]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/04/70C6E40E-4FE6-4BA8-8D5D-290F1A03600E.png)
![今日の英語 – on track/delay = 予定通り/遅れあり[2020/04/08]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/11/F12C8F86-A0B0-4334-9DAD-E75022893870.jpeg)
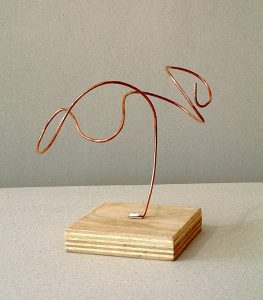
![[健康] 忘れかけていた健康の大事さ(1) – 愚者は経験から学ぶ [2020/04/08]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/04/3B0F6B20-C23B-4F1D-B1A1-3A84BAB8DADD.jpeg)