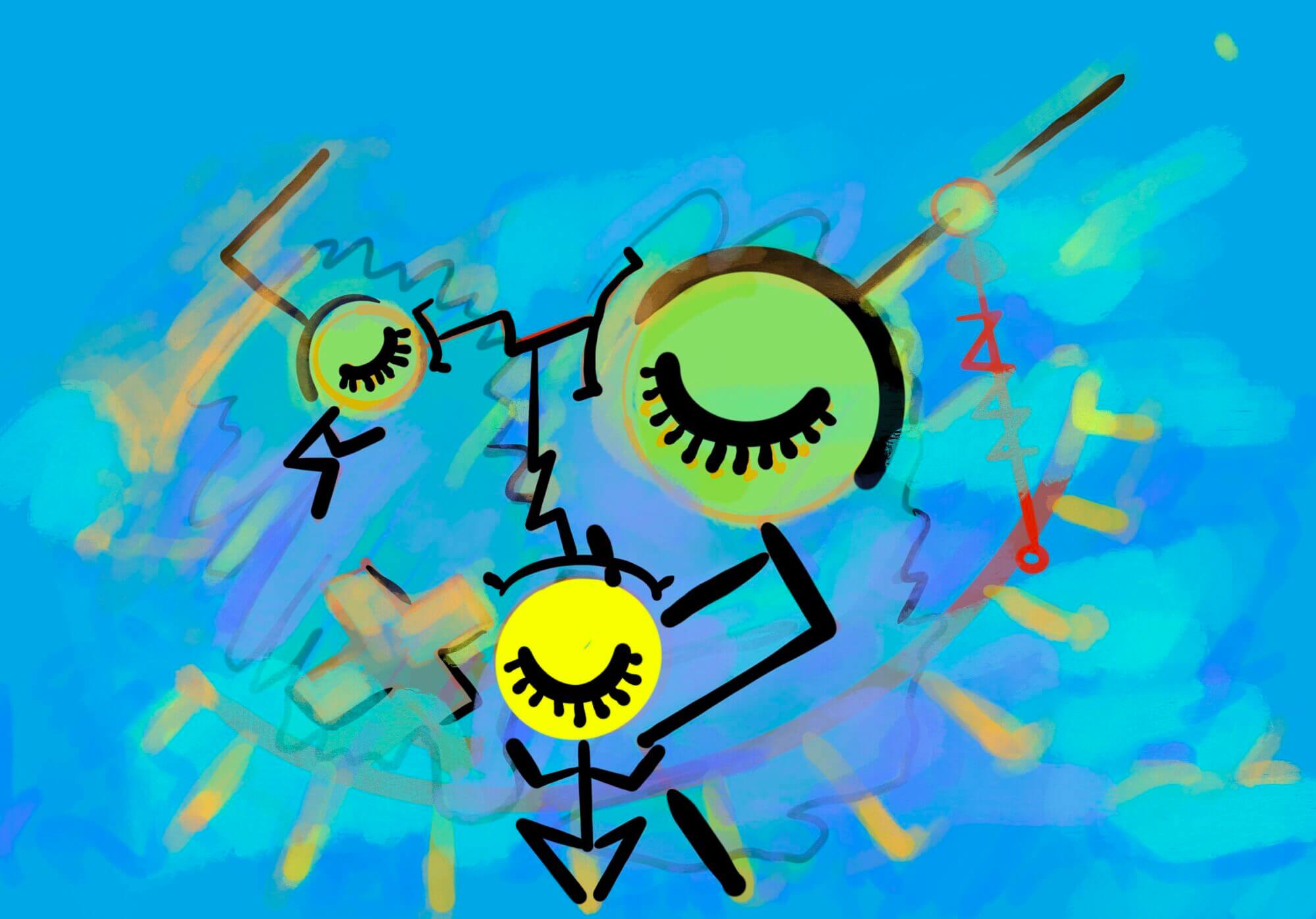はじめに
日本薬局方における 「微生物限度試験」 と 「無菌試験」 は、いずれも医薬品の品質・安全性を確保するための微生物学的試験法ですが、それぞれ目的・対象・方法に違いがあります。
目次
微生物限度試験(収載番号:4.05)
試験目的
- 医薬品中の**一般生菌数(TAMC)や真菌数(TYMC)**を定量
- 特定微生物の有無を確認(健康リスクのある菌)
- TAMC(一般生菌数)やTYMC(真菌数)の試験は、基本的には「嫌気性細菌を検出することを目的とはしていません」。
- 無菌製剤ではない一般製剤(例:経口薬、外用薬、漢方薬など)について、「一定以下の微生物数であるか?」,「有害な特定微生物が含まれていないか?」 を確認する.
TAMC・TYMCと嫌気性細菌の関係について・・・
| 試験名 | 主な対象微生物 | 培養条件 | 嫌気性菌は対象か? |
|---|---|---|---|
| TAMC | 好気性または通性嫌気性の細菌 | 約30~35℃で好気培養(空気あり) | ❌ 原則含まない(嫌気性菌は育たない) |
| TYMC | 酵母・カビ(真菌) | 約20~25℃で好気培養 | ❌ 対象外 |
→ TAMC/TYMCの環境では、偏性嫌気性細菌(例:Clostridium属など)は発育できないため、検出されません。
嫌気性細菌を検出するには?・・・
嫌気性細菌(特に毒素産生性の菌)を検出するには、以下の試験が適しています:
| 試験名 | 対象微生物 | 特徴 |
|---|---|---|
| 無菌試験(4.06) | 好気性・嫌気性すべて | 嫌気性菌も発育できる培地(FTM)使用 |
| 特定微生物試験(4.05内) | Clostridium属など | 嫌気培養・熱処理で芽胞菌を検出 |
| エンドトキシン試験(4.01) | グラム陰性菌由来の毒素 | 生菌ではなく毒素そのものを検出 |
まとめ
特定微生物試験(4.05内):嫌気条件で選択的に培養する
TAMC/TYMCは好気性微生物が対象で、嫌気性菌の検出には適していない。
嫌気性菌を評価するなら:
無菌試験(4.06):培地性能試験にClostridium sporogenesなど使用
適用対象
- 経口剤、外用剤、原料など 非無菌製剤
試験法の特徴
- 培養法(平板培養・液体培養)を用いて微生物数を測定。
- 一定の菌数以下であること(限度)を確認。
- 特定微生物は有無を調べるのみ(定量ではない)。
主な測定内容
- 一般生菌数 (好気性性微生物)
- 真菌数(カビ・酵母)
- 特定微生物の有無(例 : 大腸菌,サルモネラ属菌,黄色ブドウ球菌,緑膿菌,クロストリジウム属菌など)
主な手順概要
一般生菌数・真菌数の測定
- 試料の前処理(希釈・溶解)
- 寒天平板法または膜ろ過法により培養
- 培養期間:
- 一般生菌数:30~35℃で3~5日間
- 真菌数:20~25℃で5~7日間
- コロニー数をカウント(限度値以下なら合格)
特定微生物の検出(例)
| 微生物名 | 判定基準 | 使用培地・条件例 |
|---|---|---|
| 大腸菌 (E. coli) | 検出されないこと | マッコンキー培地、選択増菌 → 確認試験(発酵等) |
| サルモネラ属菌 | 検出されないこと | RVS培地などで選択増菌 → SS寒天で確認 |
| 黄色ブドウ球菌 (S. aureus) | 検出されないこと | マンニット食塩寒天培地 |
| 緑膿菌 (P. aeruginosa) | 検出されないこと | シュードモナス寒天 |
| クロストリジウム属菌 | 検出されないこと | 嫌気性条件、加熱処理(芽胞強調) → 培養 |
無菌試験(収載番号:4.06)
試験目的
- 無菌製剤に微生物がまったく存在しないことを確認
- 無菌性が要求される製剤(例:注射剤、点眼剤、輸液など)に対し,「1個でも微生物が存在していないこと(無菌性)」 を確認するための試験.
適用対象
- 注射剤・眼科用剤・生物学的製剤・無菌処理済製剤
試験法の特徴
- 試料を直接またはろ過により培養液に接種し、14日間培養して微生物の発育を確認。
- 好気性・嫌気性両方の培地を用いる。
- 微生物が1つでも存在すれば「不合格」。
試験法の種類
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 膜ろ過法 | 液体をフィルターでろ過 → 培地に浸して培養。濾過できる製剤に適用。 |
| 直接接種法 | 製剤を直接、培地に加えて培養。濾過困難な製剤(油性、軟膏等)に使用。 |
使用培地
| 培地名 | 用途 |
|---|---|
| 大豆-カゼイン消化物液体培地(TSB) | 好気性菌用(35 ± 2℃、14日間) |
| 流加チオグリコール酸液体培地(FTM) | 嫌気性菌用(30 ± 2℃、14日間) |
試験菌(陽性対照)に用いられる代表株
| 微生物 | 用途 |
|---|---|
| Bacillus subtilis(枯草菌) | 芽胞形成好気性菌 |
| Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌) | グラム陽性球菌 |
| Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌) | グラム陰性桿菌 |
| Candida albicans(カンジダ) | 酵母(真菌) |
| Aspergillus brasiliensis(アスペルギルス) | 糸状菌(カビ) |
| Clostridium sporogenes(クロストリジウム) | 芽胞形成嫌気性菌 |
試験の判定
- 培養終了後、濁りや沈殿などの微生物の発育兆候がなければ「無菌」と判定
- 発育があれば不合格(=無菌性なし)
まとめ(微生物減と試験と無菌試験の違い)
| 項目 | 微生物限度試験(4.05) | 無菌試験(4.06) |
|---|---|---|
| 品目対象 | 非無菌製剤(経口薬、外用薬など) | 無菌製剤(注射剤など) |
| 目的 | 微生物汚染レベルの確認 | 微生物が1つも存在しないことの確認 |
| 検出対象 | 微生物の数と特定菌の有無 | あらゆる微生物の存在 |
| 判定基準 | 限度内なら可 | 1個でも存在すれば不合格 |
| 培養期間 | 3~5日(菌種により異なる) | 14日間(好気・嫌気両方) |
| 使用する菌 | 試験対象とする微生物 | 陽性対照菌(6種以上)で試験性能確認 |
| 使用する培地 | 選択培地・平板寒天など | 液体培地(TSB、FTM) |
| 合否基準 | 限度内 or 特定菌なし | 微生物の発育なし=合格 |
微生物試験法および関連試験法の一覧
日本薬局方(第十八改正)には、生物学的試験法/生化学的試験法/微生物的試験法など微生物に関連する試験項目として6つが抽出できるが,4.03は微生物関連の試験には直接関係しないが、以下にリストした.
| 収載番号 | 項目名 | 概要 |
|---|---|---|
| 4.01 | エンドトキシン試験法 | グラム陰性菌由来のエンドトキシン(発熱性物質)の有無を検出する試験。リムルス試薬を用い、ゲル化法、比濁法、発色法などで判定します。 |
| 4.02 | 抗生物質力価試験法 | 抗生物質の有効性(力価)を微生物に対する成長阻害作用を評価して測定する試験。円筒平板法や微量液体希釈法などが用いられます。 |
| 4.03 | 消化力試験法 | 消化酵素製剤の酵素活性を評価する試験。でんぷん消化力(アミラーゼ活性)、タンパク質消化力(プロテアーゼ活性)、脂肪消化力(リパーゼ活性)を測定します。(細菌関連の試験に直接的に関わらない試験) |
| 4.04 | 発熱性物質試験法 | 医薬品中の発熱性物質(パイロジェン)の有無を検出する試験。ウサギを用いた試験法で、試料を静脈内注射し、体温上昇を測定して評価します。 |
| 4.05 | 微生物限度試験法 | 非無菌製剤や原料中の微生物汚染レベルを評価する試験。一般生菌数、真菌数の測定や特定微生物(大腸菌、サルモネラ属菌、黄色ブドウ球菌など)の検出を行います。 |
| 4.06 | 無菌試験法 | 無菌性が求められる製剤(注射剤、点眼剤など)に対し、微生物が存在しないことを確認する試験。ろ過法や直接接種法で実施し、一定期間培養して判定します。 |
日本薬局方(第十八改正)において、嫌気性細菌および好気性細菌の検出に関連する試験法は以下のとおりです。
1. 微生物限度試験法(収載番号:4.05)
- 概要:非無菌製品や原料中の微生物汚染レベルを評価する試験法で、一般生菌数、真菌数の測定や特定微生物の検出を行います。
- 関連する細菌の検出:
- 好気性細菌:一般生菌数の測定として、好気性細菌の数を評価します。
- 嫌気性細菌:特定微生物試験において、Clostridium sporogenes(クロストリジウム・スポロゲネス)などの嫌気性細菌の検出が規定されています。
2. 無菌試験法(収載番号:4.06)
- 概要:無菌性が求められる製剤に対し、微生物が存在しないことを確認する試験法です。ろ過法や直接接種法で実施し、一定期間培養して判定します。
- 関連する細菌の検出:
- 好気性細菌:培地性能試験および手法の適合性試験において、Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)、Bacillus subtilis(枯草菌)、Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)などが試験用菌株として使用されます。
- 嫌気性細菌:同じく、Clostridium sporogenesが試験用菌株として使用され、嫌気性細菌の検出が行われます。
さらに、参考情報として以下の関連する項目:
| 参考情報番号 | 項目名 | 概要 |
|---|---|---|
| G4-2-180 | 微生物試験法に用いる培地及び微生物株の管理 | 微生物試験に使用する培地の調製方法や品質管理、試験に用いる微生物株の取り扱いについての指針を示しています。 |
| G4-3-170 | 保存効力試験法 | 製剤中の防腐剤の有効性を評価する試験法で、製剤が微生物汚染から保護されることを確認します。 |
| G4-4-180 | エンドトキシン試験法と測定試薬に遺伝子組換えタンパク質を用いる代替法 | 従来のエンドトキシン試験法に代わり、遺伝子組換えタンパク質を用いた新しい試験法についての情報を提供しています。 |
| G4-6-170 | 微生物迅速試験法 | 従来の培養法に比べ、短時間で微生物の検出・定量を行う迅速試験法についての指針を示しています。 |
| G4-7-160 | 遺伝子解析による微生物の迅速同定法 | 微生物の同定を迅速かつ正確に行うための遺伝子解析手法についての情報を提供しています。 |
| G4-8-152 | 蛍光染色による細菌数の迅速測定法 | 蛍光染色技術を用いて、細菌数を迅速に測定する方法についての指針を示しています。 |
| G4-9-170 | 消毒法及び除染法 | 医薬品製造環境や器具の消毒・除染方法についての基準や手順を示しています。 |
| G4-10-162 | 滅菌法及び滅菌指標体 | 医薬品や器具の滅菌方法および滅菌効果を評価するための指標体についての情報を提供しています。 |
G4-4-180のような番号の意味とは?
これらの番号は、日本薬局方の「参考情報(General Information:GI)」セクションに付けられている管理番号です。
例:
G4-4-180
→ 「General(G)」 + 「第4章関連(4)」 + 「通し番号(4-180)」
🔹 日本薬局方における位置づけ
| 種類 | 内容 | 法的拘束力 |
|---|---|---|
| 正文(本編) | 公定試験法、基準、定量法など(例:4.01 エンドトキシン試験法) | あり(法的拘束力を持つ) |
| 参考情報(GI) | 実務上の指針・補足的知識・新技術の紹介など(例:G4-4-180) | なし(参考扱い) |
以上,これらの試験法や参考情報は、医薬品の製造・品質管理において、微生物学的な安全性を確保するために不可欠です。
参考ポスト
編集履歴
2024/10/17 Mrはりきり
2024/10/18 菌種購入について追記
2025/01/23 文言整備
2025/04/04 内容修正・整備(日本薬局方の関連する参考情報の追加,タイトル修正,操作の具体例を分離しページを新たに作った)