はじめに
ChatGPT Plusを使っていると、「GPT-4o」「GPT-4.5」「o3-mini」など複数のモデルが選択できるようになっています。どれを選ぶべきか迷ったことはありませんか?さらに最近では、「ChatGPTには思考過程がある」「会話が記憶されている」といった話題も耳にすることが増えてきました。本記事では、実際に私がChatGPT 4oを使いながら確かめた「モデルごとの違い」「推論の有無」「記憶機能がどこまで働いているのか」について整理し、初心者から上級者まで役立つ情報としてまとめました。
特に、GPT-4oは最新の統合モデルとして音声・画像・テキストの全てに対応し、従来のGPT-4 Turboよりも高速で柔軟な応答が可能です。一方で、軽量モデルである「o3-mini」やその高性能版「o3-mini-high」も、場面によっては有効な選択肢となります。
また、ChatGPTはあなたの興味や会話スタイルを覚える「記憶」機能も備えており、使い方次第でよりパーソナライズされたAIアシスタントになります。本記事を通じて、あなたにとって最適なChatGPTの使い方を見つけていただけたら幸いです。(以上は,以下の質問・会話の内容からAIに作ってもらった記述)
目次
ChatGPTのモデルについて
Q: ChatGPTについて,o3とo3miniの違いを教えて
ChatGPT: ChatGPTの「o3」と「o3-mini」は、GPT-4世代のモデルでありながら、それぞれに異なる特性と利用目的があります。以下に、主な違いを表で整理して解説します。
ChatGPT「o3」と「o3-mini」の比較
| 項目 | ChatGPT o3(GPT-4) | ChatGPT o3-mini |
|---|---|---|
| モデル世代 | GPT-4 | GPT-4(軽量版) |
| 公開時期 | 2024年4月 | 2024年4月15日(公開) |
| 性能(推論能力) | 高精度・高能力 | 軽量・低コスト |
| 応答速度 | やや遅め | 高速 |
| 計算リソース | 多い | 少ない |
| 推定用途 | 精度重視の対話、創作、分析 | リアルタイム対応、コスト削減 |
| Deep Research/検索機能 | 対応 | 対応(ただし制限がある場合も) |
| 利用対象 | Plusプラン(GPT-4)ユーザー | Plusプラン(GPT-4)ユーザー |
| 位置づけ | フラッグシップモデル | 軽量パートナー/補助モデル |
詳細なポイント
- 「o3」(正式には GPT-4 Turbo の最新版、2024年版)は、ChatGPT Plusユーザーにとってのデフォルトモデルで、文章生成、推論、複雑な分析など高精度な処理を得意としています。
- **「o3-mini」**は、同じGPT-4世代に属するものの、処理を軽量化したバージョンです。高速応答が求められる場面や、比較的単純な対話・自動応答などでの使用に向いています。
使用イメージの違い
- o3(GPT-4 Turbo):<br>
✔ 研究的対話・創作支援・コード生成・長文理解などで使用。<br>
✔ ChatGPTの「Deep Research」や「画像生成」とも連携しやすい。 - o3-mini:<br>
✔ FAQボット、チャット対応、軽量アプリのAI機能など。<br>
✔ 応答が速く、スケーラブルな環境での採用が期待されている。
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
Q: 4oとo3の違い?
ChatGPT: 「GPT-4o(4o)」と「GPT-4 Turbo(o3)」の違いは、OpenAIが2024年4月に発表した最新モデル GPT-4o(オー)が、従来のGPT-4 Turbo(コード名 o3)に比べて速度・性能・コスト・マルチモーダル能力すべてで上回っている点にあります。
以下に、わかりやすく違いを表にまとめて解説します:
GPT-4o(4o) vs GPT-4 Turbo(o3)
| 項目 | GPT-4o(4o) | GPT-4 Turbo(o3) |
|---|---|---|
| モデル公開日 | 2024年4月(4月末から順次展開) | 2023年11月(ChatGPT向け) |
| マルチモーダル対応 | ◎ 音声・画像・テキスト完全対応 | △ テキスト・画像(音声不可) |
| 応答速度 | 非常に高速 | 高速(ただし4oより劣る) |
| 精度・性能 | GPT-4と同等以上 | GPT-4相当(圧縮型) |
| リアルタイム音声対応 | ◯(300ms以下) | × |
| 入出力制限 | 同等(128kトークン) | 128kトークン |
| 実装技術 | 新アーキテクチャ(未公開) | GPT-4 Turbo |
| 利用可能範囲 | 無料ユーザーも利用可能(一部制限) | Plusユーザー専用 |
| API展開 | 提供中(OpenAI API) | 提供中(OpenAI API) |
| コスト(API) | 約50%割安 | 高め(比較対象による) |
特徴のまとめ
✅ GPT-4o(o = omni の略)
- 「音声/画像/テキスト」をすべてリアルタイムに処理可能な初のGPTモデル。
- 応答が人間の会話並みに高速(平均320ms)。
- マルチモーダル処理が統一された単一モデルで完結(旧GPT-4は別モジュールを使っていた)。
✅ GPT-4 Turbo(o3)
- 高性能かつ長文対応(128k token)で、従来のGPT-4(2023年3月版)よりもコスト削減&高速化されたモデル。
- マルチモーダルには部分対応(画像は可能、音声は非対応)。
- 2024年4月現在、GPT-4oに置き換わりつつある。
実際の用途面の違い
| 用途例 | 向いているモデル |
|---|---|
| 音声対話・同時通訳 | GPT-4o |
| 高精度テキスト生成 | GPT-4o または GPT-4 Turbo |
| 画像解析と説明生成 | GPT-4o |
| コード生成・文書要約 | 両方対応 |
| 長文処理(書籍級) | 両方対応(128k) |
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
ChatGPT: ありがとうございます。有料版(ChatGPT Plus)をご利用中で、以下のようなモデル選択肢が表示されているとのことですね:
💬 ChatGPTで選択可能なモデル(有料版)
- GPT-4o
- GPT-4.5
- o1
- o3-mini
- o3-mini-high
これらはすべてGPT-4系またはその派生モデルですが、目的や設計思想が異なっています。それぞれのモデルがどのような立ち位置か、以下にまとめて解説します。
モデル一覧と違いの比較
| モデル名 | 正式名・説明 | 特徴(主な強み) | 想定用途 |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | GPT-4 Omni (2024年4月リリース) | テキスト・画像・音声対応の統合モデル | 最も高性能なマルチモーダルモデル |
| GPT-4.5 | GPT-4 Turbo系の発展モデル(暫定ラベル) | GPT-4相当の精度+高速性 | 正確な対話、文章生成、分析など |
| o1 | GPT-4.0(旧GPT-4 Turbo)の初期バージョン(2023年11月頃) | GPT-4精度+高速+コスト低 | 現行モデルのベース |
| o3-mini | GPT-4世代の軽量版ミニモデル(2024年4月公開) | 高速・低コスト・軽量 | FAQ、チャットボット、リアルタイム用途 |
| o3-mini-high | o3-miniの「高精度バージョン」 | miniよりも精度高だが依然軽量 | ミドルクラス向けAIアプリ |
解説付きポイント
1. GPT-4o(Omni)
- OpenAIが最新の旗艦モデルとして発表(2024年4月)。
- 単一モデルで「音声・画像・テキスト」すべてを理解・応答。
- ChatGPT無料プランでも使えるが、Plus版では速度・優先処理で有利。
2. GPT-4.5
- 通称的な呼称。実際には GPT-4 Turbo の一種で、「o3」や「o1」などのコードネームモデル群の一つ。
- ChatGPT UI上では「GPT-4.5」や「GPT-4 Turbo」などの表記になることも。
3. o1
- GPT-4 Turbo(2023年11月〜2024年3月頃)に対応する初期型。
- 現在は後継モデル(GPT-4oなど)に置き換えが進行中。
4. o3-mini
- GPT-4系軽量モデルのうち高速・軽量特化型。
- 通常のチャットや埋め込み用途、低コストAPI向け。
5. o3-mini-high
- o3-miniの派生モデルで、「精度重視」だが軽量性も保つ中間型。
- 機械学習APIやアプリ組み込みに適した性能バランス。
結論:どう使い分ける?
| 用途 | おすすめモデル |
|---|---|
| 高精度・幅広い生成 | GPT-4o または GPT-4.5 |
| コスト重視・高速応答 | o3-mini |
| 軽量でもやや精度を重視 | o3-mini-high |
| フルモーダル対応(音声等) | GPT-4o |
| GPT-4時代の標準モデル | o1(参考用/旧モデル) |
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
思考過程や推論過程があるモデル
Q: モデルによっては,思考過程や推論過程があるものとないモデルが存在していると聞くがそれは正しいか?
ChatGPT: とても鋭いご質問です。結論から言うと:
「思考過程」や「推論過程」を
明示的に出力できるモデルと、そうでないモデルがある
というのはある程度「正しい」認識です。
そもそも「思考過程・推論過程」とは?
AIにおける「思考過程・推論過程」というのは、以下のようなものを指します:
- Chain of Thought(思考の連鎖)
→ 問題に対して、一段ずつ論理的にステップを踏んで答えに至る過程を出力する技術。
→ 例:「まずAを確認し、次にBを考慮し…だからCになる」 - Tool Use(ツール利用推論)
→ 計算、検索、知識ベースなどの外部ツールを使ってステップを明示的に処理すること
モデルによる違い(思考プロセス出力の有無)
| モデル | Chain of Thought対応 | 推論ステップの出力精度 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | ◯(指示で可能) | 非常に高い | 人間的な思考プロセスを自然に表現できる |
| GPT-4 Turbo(o1/o3) | ◯(強い) | 高 | 数学や論理のステップも精度が高い |
| o3-mini | △(指示が必要) | 中〜低 | 単純な推論なら可能、深い思考は苦手 |
| o3-mini-high | △(やや強い) | 中 | miniよりは強いが、Turboには及ばない |
| GPT-3.5(旧モデル) | △〜× | 低 | Chain of Thoughtはうまく使えない場合多い |
なぜ違いが出るのか?
- 学習データの違い
- Chain of Thought形式のプロンプト(例:Think step by step)を多く学習しているモデルは強い。
- モデルサイズとアーキテクチャ
- 大規模・多層構造のモデルほど論理の連続性を保持しやすく、内部的な「推論構造」が強い。
- 目的設計の違い
- mini系モデルは応答速度・軽量性が重視されるため、複雑な推論処理を簡略化している可能性がある。
実例:思考ステップの比較
質問:7個のりんごを3人で公平に分けたら1人あたり何個ですか?
- GPT-4oやGPT-4 Turbo
→ 「7 ÷ 3 = 2余り1。したがって、各人に2個ずつ配り、残り1個は…」など丁寧に手順を示す。 - o3-mini
→ 「2.3個」や「2個」と即答するが、過程を説明しないことがある。
まとめ
| 判定項目 | 説明 |
|---|---|
| 思考過程の表示能力 | GPT-4系(特にGPT-4o, Turbo)は優秀。mini系は簡略化されがち。 |
| 推論力(精度) | GPT-4o > GPT-4 Turbo ≒ o3-mini-high > o3-mini > GPT-3.5 |
| 明示的な「思考手順」の出力 | 明示的プロンプトがあれば、多くのモデルで可能だが、精度と深さに差が出る。 |
~メンバー専用 ↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
Q: わたしがChatGPT 4oを使用し始めて1カ月未満だが,4oには沢山の質問を含め会話してきたが,これらの内容は,今後の質問に対してどのように影響してくるのか?
ChatGPT: とても重要で興味深いご質問です。ChatGPT(特にGPT-4o)との会話内容が**今後の対話や応答にどう影響するのか?**について、以下のように整理して解説します。
ChatGPT 4oとの過去の会話が今後にどう影響するか
| 観点 | GPT-4oでの影響 | 解説 |
|---|---|---|
| 会話中の文脈記憶(短期) | ✅ 強力に影響する | 同じセッション中(ページ開いている間など)は文脈を高精度に保持。 |
| アカウントに紐づく記憶(長期) | ✅ 有効(設定によりON/OFF可能) | 「カスタム指示」や「記憶機能」をONにしていれば、長期的に好みや知識を学習。 |
| モデル自体への学習 | ❌ 不可(現時点では) | 個別ユーザーの会話内容が「モデルの知識そのもの」には反映されない。 |
| プロンプトパターンの学習 | ⭕ 傾向として補正が効く(セッション中) | あなたの質問傾向に対し、回答スタイルを調整し始める(”癖を掴む”)。 |
詳しく分けて説明すると:
① セッション内での「文脈記憶」
→ あなたが一連の会話で話した内容は、直後の質問に非常に影響します。
例えば:
- 前に出した例や定義に従って、以降の説明が行われる。
- トピックが連続していれば、背景知識がある前提で話してくる。
→ これが「コンテキストウィンドウ(文脈保持)」で、GPT-4oは最大128,000トークン(書籍数冊分)まで保持できます。
② 長期的な記憶(「カスタム指示」・「記憶機能」)
ChatGPT Plusには、「記憶(memory)機能」があります(GPT-4oも対応):
- ✔ あなたがどんな関心を持っているか(例:GMP、Blender、CDMO)
- ✔ 好む答え方(例:表形式、箇条書き、詳細→要約順)
- ✔ 話し方のトーン(丁寧/カジュアル)
これらを明示的に保存・調整可能で、メニューから以下のように管理できます:
📌 [設定 > パーソナライズ > 記憶] でON/OFF
📌 記憶に追加された内容は、通知され、いつでも削除可能
③ モデル自体の再学習には影響しない
あなたの会話は、モデル本体(GPT-4o)の学習や改善には使われません(ChatGPTのプライバシーポリシーに基づく)。
個人ごとのセッション改善には使われるが、OpenAI全体の知識更新とは別です。
まとめ:今後の質問にどう影響するか?
| 状況 | 影響の内容 |
|---|---|
| 同じセッションで話題を続けたとき | 非常に高精度な文脈理解(話の続きが自然に) |
| 記憶機能がONになっているとき | あなたの興味・好み・目的に合わせた回答スタイルを維持 |
| 複数日やアプリ間でやり取りする場合 | 過去の保存情報を活用し、精度と一貫性が向上 |
| モデルの挙動そのものを変えるか? | いいえ(あなたの個別使用では学習されない) |
o3と4oの比較
「o3」と「GPT-4o」の違いまとめ
| 比較項目 | GPT-4o(4o) | o3(GPT-4 Turbo 2024年版) |
|---|---|---|
| モデル名の意味 | o = omni(全方位:音声・画像・テキスト) | o3 = GPT-4 Turbo の2024年版コードネーム |
| リリース時期 | 2024年4月 | 2024年初頭(2023年11月~2024年3月で主力) |
| 性能 | GPT-4系で最高水準の統合モデル | 高速・高精度なGPT-4 Turbo |
| マルチモーダル対応 | ✅ 音声・画像・テキストすべて統合対応 | ◯ テキスト+画像(音声なし) |
| 応答速度 | ✅ 大幅高速化(音声で300ms台) | 高速(旧GPT-4よりもかなり速い) |
| 推論・思考の深さ | 非常に高い | 高い(4oに近いがやや劣る) |
| トークン上限 | 128,000トークン | 128,000トークン |
| API提供 | OpenAI APIで利用可能(低価格) | OpenAI APIで提供 |
| ChatGPTでの位置づけ | 最新かつ主力モデル(無料でも使える) | GPT-4 Plus専用モデル(無料では使えない) |
補足解説
● GPT-4o(4o)の特徴
- 「omni」の名の通り、1つのモデルでマルチモーダル(音声・画像・テキスト)をネイティブに処理。
- 応答速度は人間の会話に近い(平均応答300〜500ミリ秒)。
- Plusプランでは最も優先されるモデルであり、今後の主軸。
● o3の特徴(GPT-4 Turbo)
- GPT-4 Turboの中でも、2024年版(o1→o3へ進化)。
- 高速でありながら、GPT-4と同等の精度を保つ。
- マルチモーダルは別モジュール処理(統合ではない)。
結論:どちらを使うべき?
| 目的・状況 | 推奨モデル |
|---|---|
| 音声や画像を含むマルチモーダル利用 | ✅ GPT-4o |
| 単純なテキスト生成・コード記述 | 両方(GPT-4o推奨) |
| 高速性と精度のバランスを重視したい | GPT-4o(最新) |
| GPT-4 Turbo世代の従来モデルを試したい | o3(比較用) |
編集履歴
2025/04/22 Mrはりきり
![[ChatGPT] o3とか4oとかよく分からん! 今は有料版で4oを通常使用-その他のモデルも使用できるが,先ずは比較検討してみた [2025/04/22]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2023/06/IMG_8895.jpeg)
![[GMP] Validation,Verification and Qualificationの違い.医薬品の開発や製造においては文脈で少しだけ異なることもあるとか.[2025/04/21]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2024/01/IMG_2093.png)
![[医薬品開発] 委託製造でもPMDA調査はある?申請者が備えるべきGQP・GVP体制 [2025/04/20]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/02/80F3D755-3019-49C6-BDAE-47D137C87826.jpeg)

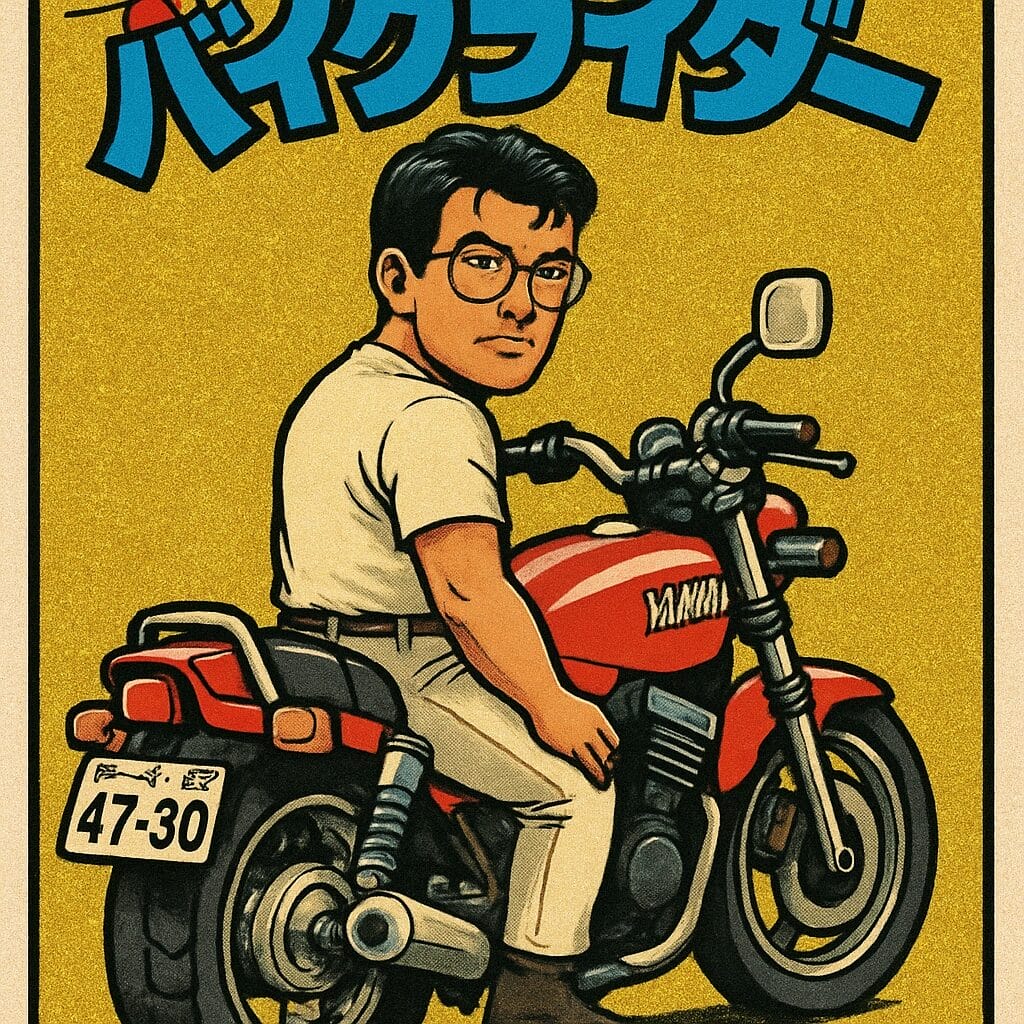
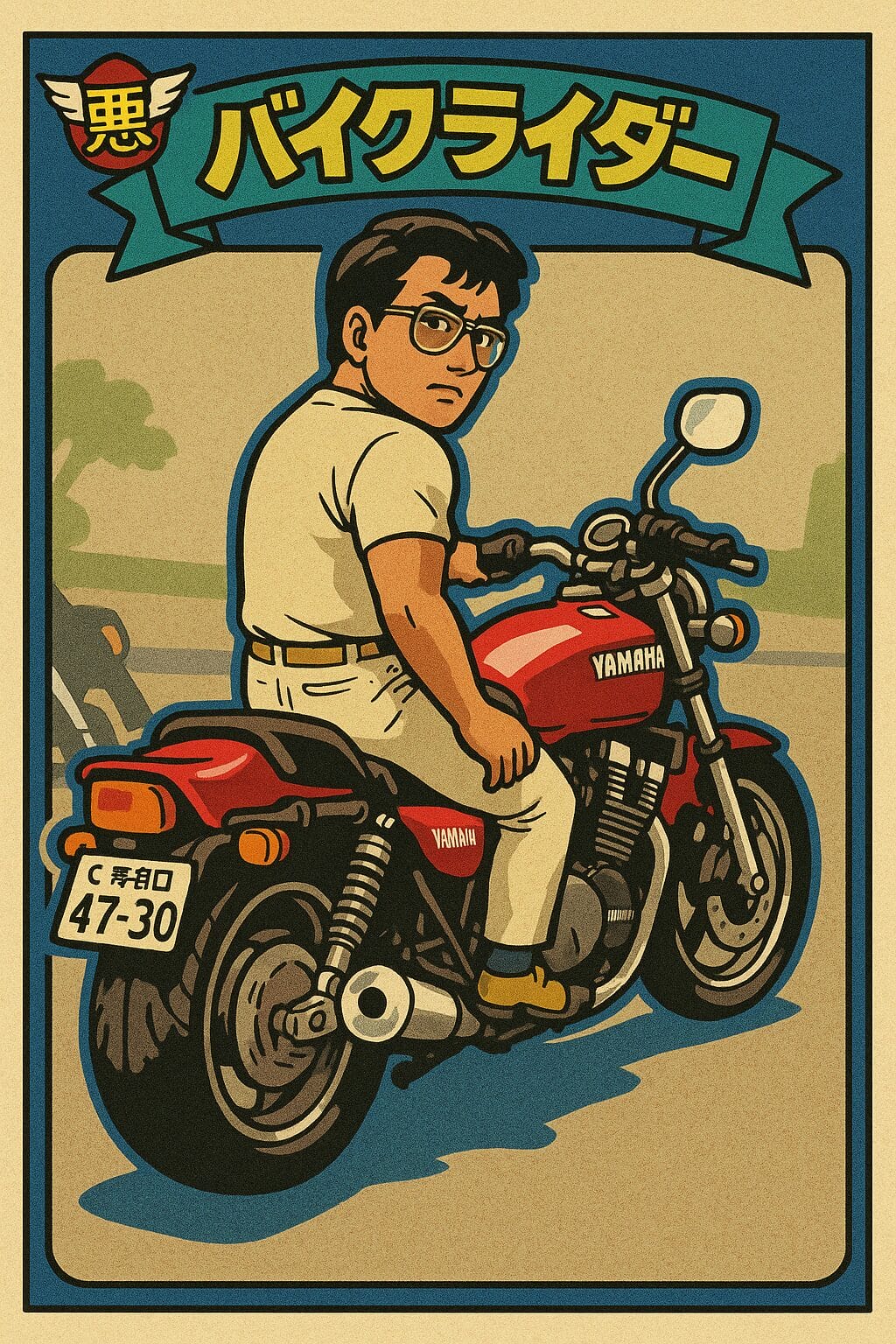

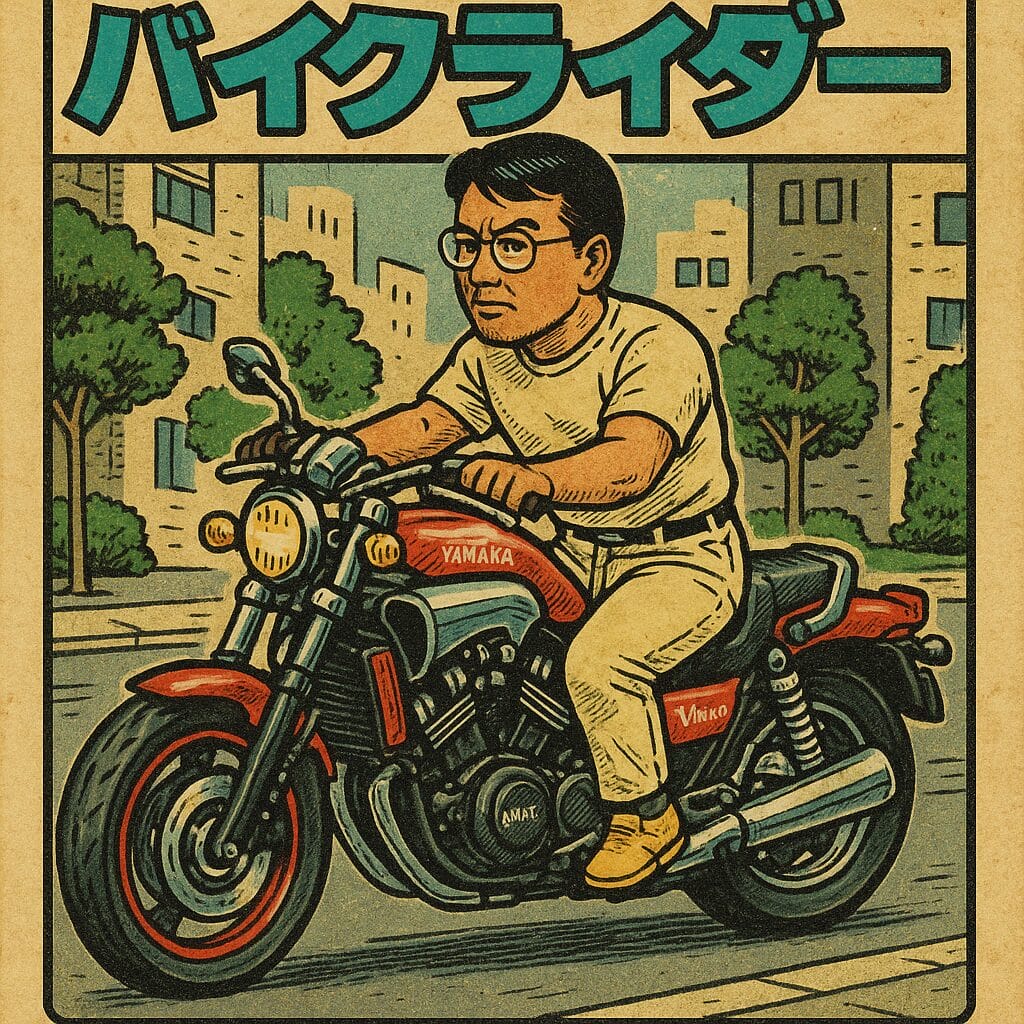



![[ITセキュリティ] 「ET CINS Active Threat Intelligence Poor Reputation IP group 16」は、ネ過去に悪質な活動が確認されたIPアドレス群からの通信を検知・警告アラート-ブロックすべきかどうか? [2025/04/19]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2020/12/ABAB7B15-D8B3-4466-AAD6-423FBBC7E6BD.jpg)