Post Views: 143
CTD(Common Technical Document:共通技術文書)は、新薬の承認申請資料を国際的に統一されたフォーマットで提出するための文書構成 です。
🔹 CTDの基本構成(モジュール構造)
CTDは5つの**モジュール(Module 1〜5)**から構成され、それぞれの役割が明確に分かれています。
モジュール番号 名称 内容概要 Module 1 地域別情報(Administrative Information) 各国ごとに異なる部分(例:申請書類、添付文書、GCP適合性資料など)日本独自 の様式等が含まれる Module 2 CTD概要(Common Technical Document Summaries) Module 3〜5の要点をまとめた「概要・総括」 Module 3 品質情報(Quality) 原薬・製剤の品質、製造、分析法、安定性など(旧:CMC資料) Module 4 非臨床試験データ(Nonclinical Study Reports) 動物試験などの安全性評価(毒性、薬理、薬物動態) Module 5 臨床試験データ(Clinical Study Reports) 治験など人に対する試験結果(有効性・安全性の証拠)
🔸 各モジュールの補足ポイント
◆ Module 1(地域独自)
日本では「添付資料 」「申請書」などが該当
eCTDでは「M1」は国ごとのテンプレートあり(ICH外)
◆ Module 2(サマリー)
膨大なModule 3〜5を読む前に、要点を把握するための文書
特に審査官がレビュー時に重視するモジュール
◆ Module 3(品質パート)
原薬(Drug Substance)と製剤(Drug Product)の情報が含まれる
バイオ医薬品の場合も同様の構成
◆ Module 4(非臨床パート)
動物実験ベースの毒性試験(単回・反復・遺伝毒性・生殖毒性など)
薬物動態(ADME)や安全性薬理も含む
◆ Module 5(臨床パート)
臨床試験(第1相〜第3相)などの結果
個別の試験報告書だけでなく、統合解析(例:統合安全性報告書)も含む
📦 図式:CTD構成イメージ
sqlコピーする編集するCTD 全体
├── Module 1: 地域別情報(国別で異なる)
├── Module 2: サマリー(各パートの概要)
├── Module 3: 品質情報(化学・製造)
├── Module 4: 非臨床試験(毒性・薬理など)
└── Module 5: 臨床試験(治験データなど)
📝 補足:電子CTD(eCTD)
上記CTD構成を**電子ファイル形式(XML+PDF等)**で提出する仕組み
ICH M8で仕様が定義されており、現在はeCTDでの提出が主流です
Module 1の構成
少し異なっていると思われる箇所もあるが,そこはあとで確認しることにする.概ねあっている.
CTDの Module 1 は、各国の規制要件に基づく地域別の情報 をまとめる部分であり、**ICH共通仕様には含まれていない(非共通)**モジュールです。
ここでは、日本のCTD Module 1の構成 を中心に、基本的な内容を解説します。
🔹 CTD Module 1(日本版)の構成概要
📁 1.0 表紙および提出書類に関する情報
1.0.1 表紙 1.0.2 添付資料一覧表 1.0.3 提出に関する説明資料(オプション)
1.1.1 医薬品製造販売承認申請書 1.1.2 添付文書(案) 1.1.3 製品情報概要 1.1.4 日本語ラベル(表示)案
📁 1.2 GCP等に関する情報(治験実施体制)
1.2.1 治験実施に関する情報一覧 1.2.2 治験責任医師・実施医療機関一覧 1.2.3 治験契約書の写し 1.2.4 倫理委員会関連資料 1.2.5 治験薬概要書(IB) 1.2.6 同意文書等のサンプル
📁 1.3 製造管理および品質管理に関する情報(GMP適合性等)
1.3.1 製造方法概要書 1.3.2 GMP適合性調査申請資料 1.3.3 製造施設一覧・構造図
📁 1.4 医薬品リスク管理計画(RMP)
1.4.1 医薬品リスク管理計画書 1.4.2 添付文書との関連資料
📁 1.5 費用・審査関係資料(オプション)
🗂️ Module 1は「国ごとの提出ルールに準拠」
地域 Module 1の特徴 日本 添付文書、治験情報、GMP資料、RMPなどが含まれる 米国 FDAフォーム、薬価関連文書、PATの使用などが含まれる EU スマルタ(SmPC)、パッケージリーフレット、ラベル案などが必要
📝 補足:電子提出(eCTD)との関係
Module 1も**eCTD対応(構造フォルダ+XMLタグ)**で提出
日本ではPMDAが定めるフォルダ構成に従って提出する(「1.1」「1.2」などのサブフォルダ)
Module 2の構成
CTDのModule 2 は、モジュール3〜5(品質・非臨床・臨床)に関する概要(サマリー)をまとめた部分 です。最初に読む 、非常に重要なモジュールです。
🔹 CTD Module 2 の構成概要
📁 2.1 CTDの概要(General Introduction)
CTD全体に関する簡単な紹介文(提出の背景、構成など)
通常1〜2ページ程度の説明書き(日本では必須ではない)
📁 2.2 CTDサマリー(Overall CTD Table of Contents)
CTD全体(Modules 2〜5)の目次
各セクションの構成を一覧形式で示す(eCTDでは自動生成も)
📁 2.3 品質に関する全体概要(Quality Overall Summary:QOS )
Module 3(品質情報)の要約版 原薬(Drug Substance)と製剤(Drug Product)に分かれた構成:
2.3.S:原薬の概要(製造法、特性、規格など)
2.3.P:製剤の概要(組成、製造、安定性など)
📁 2.4 非臨床概要(Nonclinical Overview)
Module 4(非臨床試験)の全体的な要約
薬理・毒性・薬物動態など、安全性の評価まとめ
📁 2.5 臨床概要(Clinical Overview)
Module 5(臨床試験)の全体的な要約
有効性、安全性、使用経験、ベネフィット/リスク評価など
📁 2.6 非臨床サマリー(Nonclinical Written and Tabulated Summaries)
分野別の非臨床試験データを表形式+記述形式で要約
2.6.1 薬力学(一次・二次・安全性)
2.6.2 薬物動態(吸収、分布、代謝、排泄)
2.6.3 毒性(急性、反復、生殖、発がん性など)
📁 2.7 臨床サマリー(Clinical Summary)
臨床試験データの詳細なサマリー(記述+表)
2.7.1 生物薬剤学・臨床薬理
2.7.2 有効性
2.7.3 安全性
2.7.4 付録(統合データの表など)
🧭 構成図イメージ
objectivecコピーする編集するModule 2
├── 2.1 CTD概要
├── 2.2 CTDサマリー目次
├── 2.3 品質概要(QOS)
├── 2.4 非臨床概要
├── 2.5 臨床概要
├── 2.6 非臨床サマリー(詳細表)
└── 2.7 臨床サマリー(詳細表)
📌 Module 2のポイント
審査官がまず読む要約セクション :評価の印象を左右する重要パート明快で簡潔な要約 が求められる(資料本文はModule 3〜5に格納)eCTDではPDFで提出 されることが多く、各セクションにXMLタグが付与される
以下に、**CTD Module 2(特に2.4 非臨床概要 / 2.6 非臨床サマリー)**の作成に関連する:
GLP要件の基本 毒性試験記載テンプレート(2.6 / 2.4 対応) 新規モダリティ(例:核酸医薬)における非臨床戦略の考え方
を順にご紹介します。
✅ ① GLP要件(非臨床試験)
🔸 GLP(Good Laboratory Practice)とは
非臨床安全性試験の信頼性を確保するための国際的基準 日本では**医薬品GLP省令(厚労省)**が適用
**CTD Module 4(原報)**だけでなく、Module 2(サマリー)にもGLP準拠の明記が求められる
📌 Module 2での記載例(2.6や2.4中)
コピーする編集する本試験は、OECD GLP基準および厚生労働省のGLP基準に準拠して実施された。
GLP適合性確認は実施機関のQA部門により行われ、試験責任者による署名済み最終報告書を取得している。
✅ ② 毒性試験の記載テンプレート(2.6.3向け)
🔹 サンプル構成:2.6.3「毒性に関する文書と表形式サマリー」
bashコピーする編集する【試験タイトル】
28日間反復投与毒性試験(ラット、経口投与)
【試験番号】
TOX-XYZ-001
【被験物質】
API(ロット番号:123456)
【試験機関・GLP適合】
ABC試験センター(OECD準拠)
【群構成】
対照群、高用量、中用量、低用量(各群10匹/性)
【評価項目】
臨床症状、体重、血液・血液生化学、器官重量、組織病理など
【主な結果】
- NOAEL:30 mg/kg/day(♂)、10 mg/kg/day(♀)
- 100 mg/kg群で肝障害(ALT, AST上昇)と脂肪変性を認めた
【考察】
→ 薬理作用と関連あり、可逆性を確認済。
📝 2.6には記述形式、表形式の両方 が求められます(ICH M4Sに準拠)
✅ ③ 新規モダリティ(例:核酸医薬)の非臨床戦略
🔬 特性:
DNA/RNAベースの医薬品 (例:アンチセンス、siRNA、mRNA、ASOなど)標的特異性が高く、毒性プロファイルが従来と異なる
📌 非臨床戦略のポイント(Module 2.4で総括)
評価項目 留意点 薬理試験 標的遺伝子の発現を確認するin vitro試験、動物種の選定(ヒトとの相同性) PK試験 分布(肝臓、腎臓への集積)、組織残留、消失経路の確認(代謝酵素不要) 毒性試験 反復投与毒性(通常2種)、局所毒性(皮下注など)、免疫刺激性(Toll様受容体など) 遺伝毒性・発がん性 一般に不要 (ターゲット特異性と非組換え性に基づく) 免疫毒性 必須、特に免疫活性化の有無(IL-6, INF-αなどの測定) 反芻動物への適応 ヒトと近い動物種(例:サル)が必要な場合も多い
📄 Module 2.6/2.4ではどうまとめるか?
モダリティ特有の項目を明記し、ICHガイドラインとの整合性を示す 必要な場合は、「評価不要」の理由も科学的に記載する
例: 遺伝毒性試験は実施していない。本品は標的配列に特異的な20-merのASOであり、染色体DNAとの相互作用の可能性は極めて低く、既存のガイドライン(例:ICH S2(R1))に従い不要と判断した。
GLP対応チェックリスト for Module 2 (非臨床試験サマリー/概要用)GLP Compliance Checklist for Module 2 (2.4 / 2.6)
チェック項目 / Item ✅ Done 備考 / Remarks 1. 各試験がGLP準拠で実施されたか記載している Is GLP compliance clearly stated for each study? ☐ 「本試験はGLP基準に準拠して実施された」と明記 2. 試験機関名・所在地を記載 Study facility name and location specified ☐ GLP認証機関名(例:○○研究所) 3. GLP適合性の根拠(監査、QA等)の記載 GLP certification or QA audit mentioned ☐ 「QA部門により監査された」など 4. 試験責任者(Study Director)の署名記載 Study Director signature included in final report ☐ 通常CSRまたは添付資料に署名あり 5. GLP未実施の場合、その理由を明確に説明 If not GLP, is justification clearly stated? ☐ 「探索的試験のためGLP外で実施」などの記述 6. GLP準拠試験と非GLP試験を区別して記載 GLP and non-GLP studies distinguished in summary ☐ 表や記述で区分けされているか 7. GLP対象外の試験領域を明記 Are GLP-exempt areas (e.g., pharmacology) acknowledged? ☐ 薬理試験や探索PKはGLP外でも可とされることが多い 8. 試験実施年・期間が記載されている Study period (start/end date) clearly shown ☐ 記録の信頼性確保に必要 9. eCTD提出時にGLP適合表現がメタデータにも反映されている GLP status reflected in eCTD metadata (if applicable) ☐ eCTDタグ情報に「GLP Yes/No」が設定されているか 10. 統合評価(Module 2.4)にGLP順守状況の総括がある GLP summary included in 2.4 (Nonclinical Overview) ☐ 例:「すべての毒性試験はGLP下で実施された」など
Module 3の構成
CTDのModule 3 は、医薬品の**品質情報(Quality)をまとめるセクションです。 原薬(Drug Substance)と 製剤(Drug Product)**に関するあらゆる品質データが収められており、**CMC(Chemistry, Manufacturing and Controls)**に相当する部分です。
🔹 CTD Module 3の全体構成
Module 3は、次の2つの大きなブロックで構成されています:
mathematicaコピーする編集するModule 3: Quality
├── 3.2.S:原薬(Drug Substance)に関する情報
└── 3.2.P:製剤(Drug Product)に関する情報
このほか、3.1(目次)や3.3(参考資料)もあります。
📁 3.1 モジュール3の目次
Module 3 全体の構成と各セクションの目次一覧
📁 3.2.S 原薬(Drug Substance)に関する情報
セクション 内容 3.2.S.1 一般情報(名称、構造式、物理化学的性質など) 3.2.S.2 製造方法(合成ルート、原料、工程管理など) 3.2.S.3 特性解析(構造確認、不純物プロファイルなど) 3.2.S.4 管理規格(試験項目、試験法、許容値) 3.2.S.5 製造バッチ・バリデーションデータ(ロット試験結果) 3.2.S.6 容器・包装(バルク品の容器情報) 3.2.S.7 安定性(保存試験データ、推定有効期限)
📁 3.2.P 製剤(Drug Product)に関する情報
セクション 内容 3.2.P.1 一般情報(製剤の名称、性状、組成など) 3.2.P.2 開発薬事(処方設計、試験法選定理由、QbDなど) 3.2.P.3 製造方法(製造工程、工程管理、フローチャート) 3.2.P.4 製剤原料の管理(賦形剤、添加剤の品質管理) 3.2.P.5 管理規格(完成品の試験項目・方法・規格) 3.2.P.6 容器・包装(最終製品の容器、材料、適合性など) 3.2.P.7 安定性(長期保存・加速試験データ、有効期限)
📁 3.3 参考資料(Literature References)
🧭 構成図(簡易)
lessコピーする編集するModule 3: Quality
├── 3.1 目次
├── 3.2.S 原薬情報
│ ├── S.1 一般情報
│ ├── S.2 製造方法
│ ├── S.3 特性
│ ├── S.4 管理規格
│ ├── S.5 バッチ試験
│ ├── S.6 容器
│ └── S.7 安定性
├── 3.2.P 製剤情報
│ ├── P.1 一般情報
│ ├── P.2 開発薬事
│ ├── P.3 製造
│ ├── P.4 原料管理
│ ├── P.5 規格
│ ├── P.6 容器
│ └── P.7 安定性
└── 3.3 文献等
📌 Module 3のポイント
提出量が最も多くなるモジュール (大量のデータを含む)品質試験のロジックと一貫性 が重視される(例:規格設定の妥当性)
バイオ医薬品の場合はQ5シリーズ のガイドラインと密接に連携
🔹 CTD Module 4 の全体構成
Module 4は以下のように構成されます:
sqlコピーする編集するModule 4: Nonclinical Study Reports
├── 4.1 目次(Table of Contents)
├── 4.2 薬理試験報告(Pharmacology)
├── 4.3 薬物動態報告(Pharmacokinetics)
└── 4.4 毒性試験報告(Toxicology)
📁 4.1 目次(Table of Contents)
Module 4 全体の構成と各試験報告の一覧
電子CTDでは自動生成されることもあります
📁 4.2 薬理試験報告(Pharmacology)
セクション 内容 4.2.1 一次薬理作用(主作用)に関する試験 4.2.2 二次薬理作用(付随作用)に関する試験 4.2.3 安全性薬理試験(心臓、中枢神経、呼吸など) 4.2.4 薬理学的相互作用(必要に応じて)
📁 4.3 薬物動態試験報告(Pharmacokinetics)
セクション 内容 4.3.1 吸収(Absorption)試験 4.3.2 分布(Distribution)試験 4.3.3 代謝(Metabolism)試験 4.3.4 排泄(Excretion)試験 4.3.5 薬物相互作用(非臨床PKでのDDI) 4.3.6 その他(例:タンパク結合、血液脳関門透過性など)
📁 4.4 毒性試験報告(Toxicology)
セクション 内容 4.4.1 単回投与毒性試験(急性毒性) 4.4.2 反復投与毒性試験(サブアキュート・サブクロニック) 4.4.3 生殖発生毒性試験(DART) 4.4.4 局所刺激性・感作性試験 4.4.5 遺伝毒性試験(Ames試験、染色体異常など) 4.4.6 発がん性試験(長期毒性) 4.4.7 毒性薬物動態(Toxicokinetics) 4.4.8 その他(免疫毒性、光毒性、小児毒性など)
🧭 構成図(簡略イメージ)
sqlコピーする編集するModule 4: Nonclinical Study Reports
├── 4.1 Table of Contents
├── 4.2 Pharmacology
│ ├── 4.2.1 Primary
│ ├── 4.2.2 Secondary
│ └── 4.2.3 Safety
├── 4.3 Pharmacokinetics
│ ├── 4.3.1 Absorption
│ ├── 4.3.2 Distribution
│ ├── 4.3.3 Metabolism
│ └── 4.3.4 Excretion
└── 4.4 Toxicology
├── 4.4.1 Acute
├── 4.4.2 Repeat dose
├── 4.4.3 Reproductive
├── 4.4.5 Genotoxicity
└── 4.4.6 Carcinogenicity
📌 Module 4のポイント
実際の**試験報告書(Study Reports)**を収載するモジュール
試験はGLP準拠 で実施されている必要がある(日本では厚労省指針対応)
Module 2(サマリー)と内容が対応している必要あり(例:2.6と4)
Module 5の構成
CTDのModule 5 は、**臨床試験データ(Clinical Study Reports)**に関する情報をまとめるパートであり、医薬品の有効性と安全性の科学的根拠 を示す最も重要なモジュールの一つです。
🔹 CTD Module 5 の全体構成
Module 5は、以下のように整理されています:
sqlコピーする編集するModule 5: Clinical Study Reports
├── 5.1 目次(Table of Contents)
├── 5.2 特別な種類の臨床報告書
├── 5.3 個別の臨床試験報告書
├── 5.4 他の臨床情報(文献など)
├── 5.5 臨床試験の一覧表(目録)
📁 5.1 目次(Table of Contents)
Module 5 全体の構成を示す目次(セクションと文書タイトル)
📁 5.2 特別な種類の臨床報告書(Special Clinical Reports)
サブセクション 内容(例) 5.2.1 ヒト薬物動態に関する報告書(例:相互作用、代謝プロファイル) 5.2.2 先行使用経験(例:治験外使用、同種薬の臨床経験) 5.2.3 コンパッショネート使用、同種薬の実地使用データなど(任意)
📁 5.3 個別の臨床試験報告書(Clinical Study Reports)
このセクションが最も重要で、以下のように分類されます:
サブセクション 内容 5.3.1 生物薬剤学試験・関連試験 5.3.2 臨床薬理試験(フェーズ1) 5.3.3 治療的確認試験(フェーズ2・3) 5.3.4 長期使用試験、安全性延長試験など 5.3.5 探索的臨床試験(フェーズ0〜1)
📁 5.4 他の臨床情報(Literature, Reports)
発表済み文献、他社データ、公開情報など
引用文献のPDFなども含む
📁 5.5 臨床試験の一覧(Tabular Listing)
Module 5 に含まれるすべての臨床試験を表形式で一覧化
🧭 モジュール構成図(簡略)
sqlコピーする編集するModule 5: Clinical Study Reports
├── 5.1 目次
├── 5.2 特殊臨床データ
├── 5.3 試験報告書
│ ├── 5.3.1 BA/BE試験
│ ├── 5.3.2 臨床薬理(P1)
│ ├── 5.3.3 有効性確認(P2・P3)
│ ├── 5.3.4 長期使用・拡張試験
│ └── 5.3.5 探索的試験
├── 5.4 文献・他の資料
└── 5.5 試験一覧表
📌 Module 5のポイント
提出データ量が非常に多くなるモジュール 多くの報告書が**ICH E3(臨床試験報告書構成)**に準拠して作成される必要あり
Module 2.7(臨床サマリー)と一貫性がとれていることが重要
原則、GCP準拠試験 である必要あり(PMDAやFDAで査察対象となる)
🔍 よくある資料の例
治験報告書(CSR)
BE試験報告書(Q8対応)
PK試験報告書(集団PK含む)
安全性統合報告(ISS)
有効性統合報告(ISE)
✅ ① CSR(Clinical Study Report)テンプレート概要
(ICH E3ガイドライン準拠)
markdownコピーする編集する1. タイトルページ
2. 概要(Synopsis)
3. 目次(Table of Contents)
4. 倫理的配慮
5. 研究目的
6. 試験の設計
7. 対象被験者の選択(インクルージョン/エクスクルージョン)
8. 治療の詳細(用量、スケジュール)
9. 有効性評価の方法と結果
10. 安全性評価の方法と結果
11. 統計的手法と解析結果
12. 試験中止・逸脱・欠測の説明
13. 結論と解釈
14. 付録(例:CRF、試験薬ロット情報、検査所一覧など)
📝 補足:
英語で作成するのが一般的(日本語版をPMDAに添付する場合あり)
試験ごとに一冊ずつ作成されます
✅ ② Module 5 作成時の注意点一覧
ポイント 説明 1. 試験の分類を正しく行うこと フェーズ分類(1, 2, 3)や試験目的(BA/BE、安全性拡張など)に基づいて適切なセクション(5.3.x)へ配置 2. CSRはICH E3準拠で記載 一貫した構成で審査官の読みやすさを確保 3. 各試験の概要はModule 2.7と整合させること データの整合性が重要視されます(例:試験結果が一致しているか) 4. タイトルページに試験番号・日付を明記 トレーサビリティ確保のために統一フォーマットを徹底 5. 付録を別ファイルとして提出する場合は参照リンクを明記 eCTD形式ではファイル間リンクが審査効率に関与します 6. 文献(5.4)とCSR(5.3)の重複に注意 重複資料を避け、資料の位置づけを明確に
✅ ③ 臨床試験リスト(5.5)作成例
試験番号 試験名 フェーズ デザイン 被験者数 主評価項目 CSRファイル名 ABC-101 第1相 単回投与PK試験 Phase 1 無作為化、単盲検 40人 Cmax, AUC 5.3.2_ABC-101.pdf ABC-202 第2相 有効性探索試験 Phase 2 無作為化、プラセボ対照 80人 減少率(%) 5.3.3_ABC-202.pdf ABC-301 第3相 確認試験 Phase 3 無作為化、二重盲検 400人 寛解率、安全性 5.3.3_ABC-301.pdf ABC-BE1 生物学的同等性試験 BA/BE クロスオーバー 24人 Tmax, AUC, Cmax 5.3.1_ABC-BE1.pdf
📝 補足:
ExcelやWordで一覧を作成することが多く、eCTDでは5.5フォルダ に格納
一覧には試験の意義やファイル名 も含めるとわかりやすいです
編集履歴
2025/05/06 Mrはりきり

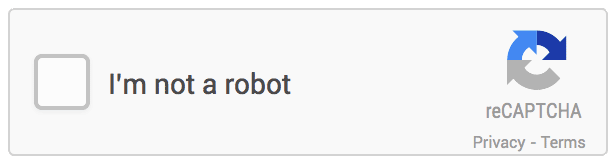
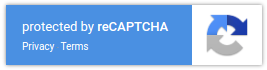
![Google のre-CAPTCHAの種類と機能の説明 [2025/04/13]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/02/80F3D755-3019-49C6-BDAE-47D137C87826.jpeg)
![[Blender 4.4.0] 現在のboneの状態,即ちposeを一括して保存する方法.[2025/04/12]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2024/11/blender_logo.jpg)