Post Views: 36
はじめに
再生医療等安全性確保法は、iPS細胞などを用いた再生医療の安全な実施を目的として2014年に施行された法律である。対象は、細胞加工物を用いる治療に加え、2023年からは体内投与型の遺伝子治療(in vivo遺伝子治療)も含まれる。再生医療等はリスクに応じて第1~第3種に分類され、それぞれに応じた法的手続きが定められている。医療機関は提供計画を作成し、厚生労働大臣に提出する前に、認定再生医療等委員会(第1種は特定認定委員会)の審査と意見書取得が必須である。さらに、患者への説明・同意(インフォームド・コンセント)、記録の作成・保存(10年間)、定期報告および有害事象の即時報告が義務付けられている。細胞加工物の製造は、企業では許可制、医療機関では届出制で行われ、GCTP準拠の品質管理が求められる。委員会は審査の中立性と記録保存義務を負い、厚労省は監視・指導・停止命令等の権限を有する。本法は、再生医療の科学的発展と国民の安全の両立を図る枠組みである。
再生医療等安全性確保法とは
Q:
再生医療等安全性確保法とは
ChatGPT:
再生医療等安全性確保法(正式名称:再生医療等の安全性の確保等に関する法律)は、再生医療を迅速かつ安全に提供し、その普及を促進することを目的として、2014年(平成26年)11月25日に施行されました。この法律は、再生医療等を提供する医療機関や細胞培養加工施設に対して、一定の基準や手続きを定め、安全性と倫理性を確保するための枠組みを構築しています。日本医師会+4厚生労働省+4株式会社グランソール免疫研究所+4 ウィキペディア+5厚生労働省+5厚生労働省+5
法律の目的と背景
再生医療は、iPS細胞や幹細胞などを用いて、損傷した組織や臓器の再生を目指す先進的な医療技術です。しかし、その特性上、従来の医薬品や医療機器とは異なるリスクや倫理的課題が存在します。そのため、再生医療の研究開発から実用化までを総合的に推進しつつ、安全性と生命倫理を確保するために、本法律が制定されました。 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 ウィキペディア 厚生労働省+3ひざ関節の痛み解消ナビ | 不安と不調に寄り添うメディア+3株式会社グランソール免疫研究所+3
主な内容と特徴
1. 再生医療等のリスク分類と提供手続き
再生医療等は、リスクの程度に応じて以下の3つに分類され、それぞれに応じた手続きが求められます:
各種別に応じて、提供計画を厚生労働大臣に提出し、特定認定再生医療等委員会または認定再生医療等委員会の意見を聴取することが義務付けられています。 株式会社グランソール免疫研究所+7厚生労働省+7独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+7
2. 特定細胞加工物の製造と管理
再生医療等で使用される細胞加工物のうち、再生医療等製品でないものを「特定細胞加工物」と定義し、その製造には以下の要件が設けられています:厚生労働省+5厚生労働省+5ウィキペディア+5
また、医療機関が特定細胞加工物の製造を外部に委託する場合、許可または届出を受けた施設に限られます。 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+1株式会社グランソール免疫研究所+1
3. 安全性確保のための措置
患者への適切な説明と同意(インフォームド・コンセント)、個人情報の保護、疾病等の発生時の報告義務など、安全性を確保するための措置が定められています。また、厚生労働大臣は、必要に応じて改善命令や提供の一時停止などの措置を講じることができます。 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+1厚生労働省+1
最近の法改正と動向
再生医療の進展に伴い、2023年には以下のような法改正が行われました:ひざ関節の痛み解消ナビ | 不安と不調に寄り添うメディア
再生医療等安全性確保法は、再生医療の安全な実施と普及を支える重要な法律です。最新の情報や詳細な手続きについては、厚生労働省の公式サイトをご参照ください。 厚生労働省 日本医師会+1ひざ関節の痛み解消ナビ | 不安と不調に寄り添うメディア+1
委員会の設置
Q:
特定認定再生医療等委員会または認定再生医療等委員会はどこに設置されるか
ChatGPT:
特定認定再生医療等委員会および認定再生医療等委員会は、再生医療等の提供計画を審査するために、厚生労働省の認定を受けた機関です。これらの委員会は、全国の大学、医療機関、研究機関、非営利団体などに設置されています。具体的な設置場所や連絡先については、厚生労働省の「e-再生医療」サイトにて一覧が公開されています。以下に、いくつかの例を挙げます。e-再生医療+2e-再生医療+2ctr.med.keio.ac.jp+2
特定認定再生医療等委員会の例
大阪大学第一特定認定再生医療等委員会
東京科学大学特定認定再生医療等委員会
九州大学病院特定認定再生医療等委員会
認定再生医療等委員会の例
東北大学認定再生医療等委員会
日本肌再生医学会認定再生医療等委員会
これらの委員会は、再生医療等提供計画の審査を行うために設置されており、各種の再生医療等提供計画に対する意見を述べることを目的としています。設置場所や連絡先は委員会ごとに異なりますので、詳細については各委員会の公式ウェブサイトや厚生労働省の「e-再生医療」サイトをご参照ください。東京医科歯科大学+4ishinkai-committee.com+4藤田医科大学 – Fujita Health University+4
rAAV遺伝子治療薬の区分
Q:
細胞加工物を用いない遺伝子治療は,第2種再生医療等にあたるか
ChatGPT:
細胞加工物を用いない遺伝子治療(いわゆる in vivo 遺伝子治療 )が再生医療等安全性確保法において 第2種再生医療等に分類されるか どうかについては、以下のように整理できます。
■ 結論(2023年改正後の制度に基づく)
原則として「第2種再生医療等」に該当する可能性が高いが、個別にリスク評価される。
■ 背景と制度的根拠
1. 改正のポイント(2023年)
2023年の法改正(「再生医療等安全性確保法施行規則の一部改正」)により、それまで対象外とされていた 細胞加工物を用いないin vivo型の遺伝子治療 も、再生医療等に含まれることになりました。
例:アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターを体内に直接投与する遺伝子治療
2. 種別分類の考え方
再生医療等は、以下の3種に分類され、使用される細胞または処置の リスクの程度 に応じて決定されます。
区分 概要 主な例 第1種 高度なリスク(ヒトES細胞、iPS細胞、遺伝子導入細胞など) iPS由来の細胞移植、CAR-T細胞療法など 第2種 中程度のリスク(自己の体性幹細胞、他家間葉系幹細胞など) 自家脂肪由来幹細胞移植など 第3種 低リスク(自己由来の非幹細胞で遺伝子導入なし) 自家線維芽細胞の移植など
in vivo遺伝子治療は:
遺伝子導入が関与するが、細胞加工がない ため、第1種と第3種の中間 に位置づけられる。そのため 第2種として扱うことが標準的 です。
ただし、使用するウイルスベクターの性質や投与方法、標的器官、全身への影響リスクなどによっては、個別判断で第1種に分類されるケースもあり得ます 。
■ 規制上の対応
提供計画の提出 が必要。認定再生医療等委員会の意見聴取 が義務。医療機関の届出または特定細胞加工物製造業者の許可 は不要(in vivo型で細胞加工なしのため)。
■ 参考資料
厚生労働省「再生医療等安全性確保法におけるin vivo遺伝子治療の取扱い(通知)」
令和5年(2023年)度薬生監麻発0730第1号「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
ご希望があれば、該当する通知文書の原文や分類事例集をまとめて提供できます。
4o
提供計画の提出
Q:
提供計画の提出とは,具体的にどのような経路があるか関連する機関や患者など含めて関係性をしめしながら全体像を教えて
ChatGPT:
再生医療等の提供を行う際には、提供計画の提出 が法律により義務付けられており、これは「再生医療等安全性確保法」に基づいて、安全性・倫理性・科学的妥当性 を確保するための中心的な制度です。以下に、全体の流れと関係機関・関係者との関係性 を図式的・段階的に解説します。
提供計画の提出の全体像(関係機関・関係者との関係を含めて)
■【ステップ①】提供計画の作成
主体 医療機関(再生医療等を実施しようとする医師・医療機関) 内容 – 提供計画書(実施方法、リスク管理、患者情報管理 等)を作成 関連情報源 再生医療等提供計画様式(厚生労働省の定型様式あり)
■【ステップ②】認定委員会による審査・意見書作成
主体 認定再生医療等委員会(または特定認定再生医療等委員会) 内容 – 医師による提供計画を審査し、科学的妥当性・倫理性・安全性を確認 委員会設置先の例 大学病院、研究機関、民間学会等(厚労省認定済)
■【ステップ③】厚生労働大臣(実務は地方厚生局)への計画提出
主体 医療機関 提出内容 – 提供計画書 提出先 地方厚生局(施設所在地の管轄) 形式 電子媒体と紙の両方、または厚労省指定の電子申請システム(e-再生医療)使用
■【ステップ④】提供開始
主体 医療機関 要件 提出後、厚労大臣の確認を待たずに実施可能 (ただし記録・報告義務あり) 備考 提供計画は定期報告・有害事象の報告義務 を伴う(年1回以上、即時報告もあり)
■【ステップ⑤】患者との関係:インフォームド・コンセント
主体 医師と患者 内容 – 提供前に十分な説明と同意の取得が必須(文書で) 書類 – 説明文書
関係者と機関の相関図(簡易フロー)
markdownコピーする編集する【医療機関】
└→ 提供計画の作成
↓
【認定委員会】
└→ 提供計画を審査 → 意見書を発行
↓
【医療機関】
└→ 意見書+提供計画を厚労省(地方厚生局)に提出
↓
【厚労省/地方厚生局】
└→ 提出の受理(認可ではない) → 届出完了
↓
【医療機関】
└→ インフォームド・コンセント後に患者へ提供開始
提出・審査・報告に関する法的義務(概要)
区分 義務の有無 備考 計画提出 義務(全ての種別) 実施前に必須 委員会審査 義務(第1〜3種全て) 第1種は特定認定委員会、それ以外は認定委員会 有害事象報告 義務 重篤例は即時報告、軽微でも年1回報告義務 提供記録の保存 義務(10年間) 患者ごとの処置・副作用等を記録
ご希望があれば、各書式のサンプル(提供計画書、説明文書、同意書)や、審査チェックリスト例も提供できます。
4o
CPC施設は阪大医学部に併設されている
Q:
CPC施設として大阪大学にあるMTR CPCの略号の内,MTRは何の略号か
ChatGPT:
大阪大学の再生医療関連施設「MTR CPC 」における「MTR」は、以下のように略されています:
MTR の正式名称
MTR = Medical and Translational Research
✅ 全体の意味(MTR CPC)
MTR CPC = Medical and Translational Research Cell Processing Center 日本語訳:医療・トランスレーショナルリサーチ細胞加工センター
🏥 背景と役割
大阪大学医学部附属病院が設置したこの施設は、再生医療等製品や細胞治療の開発・実施に必要な細胞加工 を行うCPC(Cell Processing Center)であり、「基礎研究(Medical Research)」と「橋渡し研究(Translational Research)」の融合拠点として位置づけられています。
🔗 関連情報
所在地:大阪大学医学部附属病院(吹田キャンパス)
役割:細胞培養、品質管理、GCTP/GMP準拠の製造、再生医療の臨床応用支援
必要であれば、MTR-CPCの機能・設備構成、あるいは同様の大学CPC施設の比較もご提供可能です。
4o
関連機関の役割
Q:
再生医療等安全性確保法に挙げられている対処しなければならない事項についてリストアップして
ChatGPT:
再生医療等安全性確保法(正式名:再生医療等の安全性の確保等に関する法律)では、再生医療等の提供にあたり、医療機関・事業者・関連機関が対処しなければならない事項が法的に定められています。以下に、同法および関係政省令(施行規則等)に基づいて、医療機関・細胞加工事業者・委員会などが対処しなければならない主な事項 を体系的にリストアップします。
【1】医療機関が対処すべき主な義務
区分 対処事項 根拠条文・通知等の備考 ① 再生医療等提供計画の作成・提出 法第4条・第5条:厚生労働大臣への提出義務 ② 委員会の審査を受ける 第6条:認定/特定認定再生医療等委員会の意見取得義務 ③ 患者への説明と同意取得(IC) 第10条:書面での説明・署名付き同意書 ④ 提供記録の作成と10年間の保存 第11条:提供の経過、処置、結果など ⑤ 提供状況の定期報告 第12条:原則年1回以上、厚生局へ報告義務 ⑥ 有害事象・死亡等の報告 第13条:重大な事象は速やかに届出 が必要 ⑦ 提供計画の変更・中止等の届出 第14条:内容変更時は再審査や届出義務あり ⑧ 再生医療等の適正提供体制の維持 全般:医師・看護師体制、教育訓練の整備等
【2】細胞加工物の製造施設(企業・医療機関)が対処すべき事項
区分 対処事項 根拠条文・通知等の備考 ① 特定細胞加工物の製造許可申請(事業者) 第15条:厚労大臣の許可が必要(企業・外部施設) ② 製造届出(医療機関) 第16条:施設内で製造する場合の届出義務 ③ 製造管理・品質管理体制の構築 第17条:GCTP相当の手順書、責任者、教育訓練など ④ 製造記録の保存 第18条:10年間保存義務あり ⑤ 製品品質不良や逸脱の報告 第19条:速やかに届出、必要時は出荷停止等
【3】認定再生医療等委員会の義務
区分 対処事項 根拠条文・備考 ① 提供計画の審査と意見書の発行 第6条:倫理性・安全性・科学的妥当性を評価 ② 審査記録・議事録の保存 指針・政省令:5年間の保存義務 ③ 独立性・中立性の保持 委員構成・利益相反管理などの遵守
【4】厚生労働省(または地方厚生局)の監督対応
区分 内容 指導・監督 提出された提供計画や報告をもとに、監視・指導を実施 改善命令 安全性に問題がある場合、改善を命じる権限あり 提供停止命令 重大な危害が想定される場合、即時提供停止を命令可能 公表措置 法違反などが認められた場合、違反内容を公表可能
参考:対処事項の典型的な構造(図式)
cssコピーする編集する医療機関 → [計画作成] → [認定委員会で審査] → [厚労省に提出] → [提供開始]
↓ ↓ ↓
[記録保存・有害事象報告・IC] [年次報告・計画変更届出]
ご希望があれば、これらの項目ごとにチェックリスト形式(Excel等)や、法令別マトリクス(条文×義務対応)としても整理できます。必要ですか?
4o
改正法と旧法の比較
再生医療等安全性確保法の比較表(2014年施行版 vs 2023年改正版)
Q:
2023年の改正法と以前の法律の比較として既存のものと変更点をリストアップし比較としての説明を入れた表にして
ChatGPT:
以下に、再生医療等安全性確保法の2023年改正点 と改正前(2014年施行時)の制度 との比較表を示します。制度の違いが一目で分かるよう、**比較ポイント別に「改正前」「2023年改正後」**を対比し、要点を解説付きで整理しています。
比較項目 2014年(改正前) 2023年改正後 解説・変更点のポイント 対象範囲 細胞加工物を用いた治療のみ対象 遺伝子治療(in vivo)も新たに追加 遺伝子治療薬(ウイルスベクター等)を体内投与する治療も「再生医療等」として規制対象に 遺伝子治療の扱い 対象外(医薬品医療機器等法などの枠で対応) 再生医療等として第2種などに分類し規制 in vivo遺伝子治療を医療機関経由で行う際に、計画提出・委員会審査が必要となる 委員会への規制 認定制だが、立入検査や運用指針は不明確 委員会に対しても立入検査等を可能とする法的規定を追加 委員会の品質と中立性確保を目的に、監督機能を強化 委員会の標準化(審査の質) 質のバラつきが指摘されていた 審査記録の保存義務、標準的審査基準の整備 透明性向上・質の均一化を図る規定が追加 情報公開・患者説明 医療機関に委ねられていた説明文書の整備基準が不統一 様式・記載事項に関するガイドラインを厚労省が明確化 説明文書や同意書の標準化が進み、患者保護が強化 事後監視・罰則 不備に対する行政対応に限界あり 重大違反に対する命令・公表等の制裁措置を強化 悪質な運用に対する監視・是正力を強化 電子申請・届出制度 紙ベース主体、一部メール提出 電子化が推進され「e-再生医療」システムを整備・活用 提出・変更届等が電子化され、事務負担軽減・迅速化へ 医療機関への教育・支援 自主対応任せだった 厚労省による医療機関向け教育・指導制度の整備(e-learning等) 現場の理解不足を防止し、安全な提供体制を強化
解説(まとめ)
2023年改正では、従来の「細胞加工物主体」の制度設計に、**非細胞性の遺伝子治療(in vivo型)**を新たに含めたことが最大の変化です。加えて、審査委員会の中立性や審査水準の均一化、法的な監視・是正手段の整備、患者説明文書の標準化、申請電子化など、制度運用の実効性と透明性を高める方向へ進化 しています。
編集履歴
2025/05/29, Mrはりきり

![GMP : 医薬品製造における逸脱対応について逸脱の発見からCAPA対応までのステップを解説する [2025/06/04]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2024/01/IMG_2093.png)
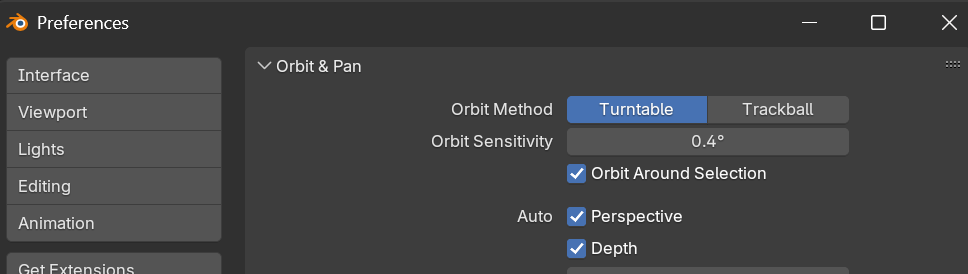
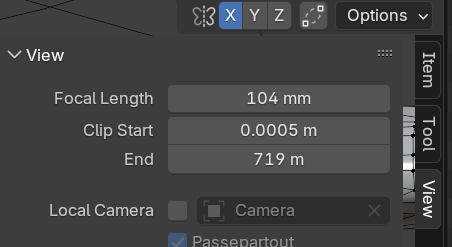
![[GCTP] 今日の一問一答 ~iPS細胞など再生医療等製品にもGQP体制は必要か? AI君に聞いてみた[2025/06/01]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2021/02/80F3D755-3019-49C6-BDAE-47D137C87826.jpeg)
![ChatGPT – Blender : Geometry Node設定方法の質問ではハルシネーションが満載 [2025/05/31]](https://harikiri.diskstation.me/wp-content/uploads/2023/06/IMG_8895.jpeg)

