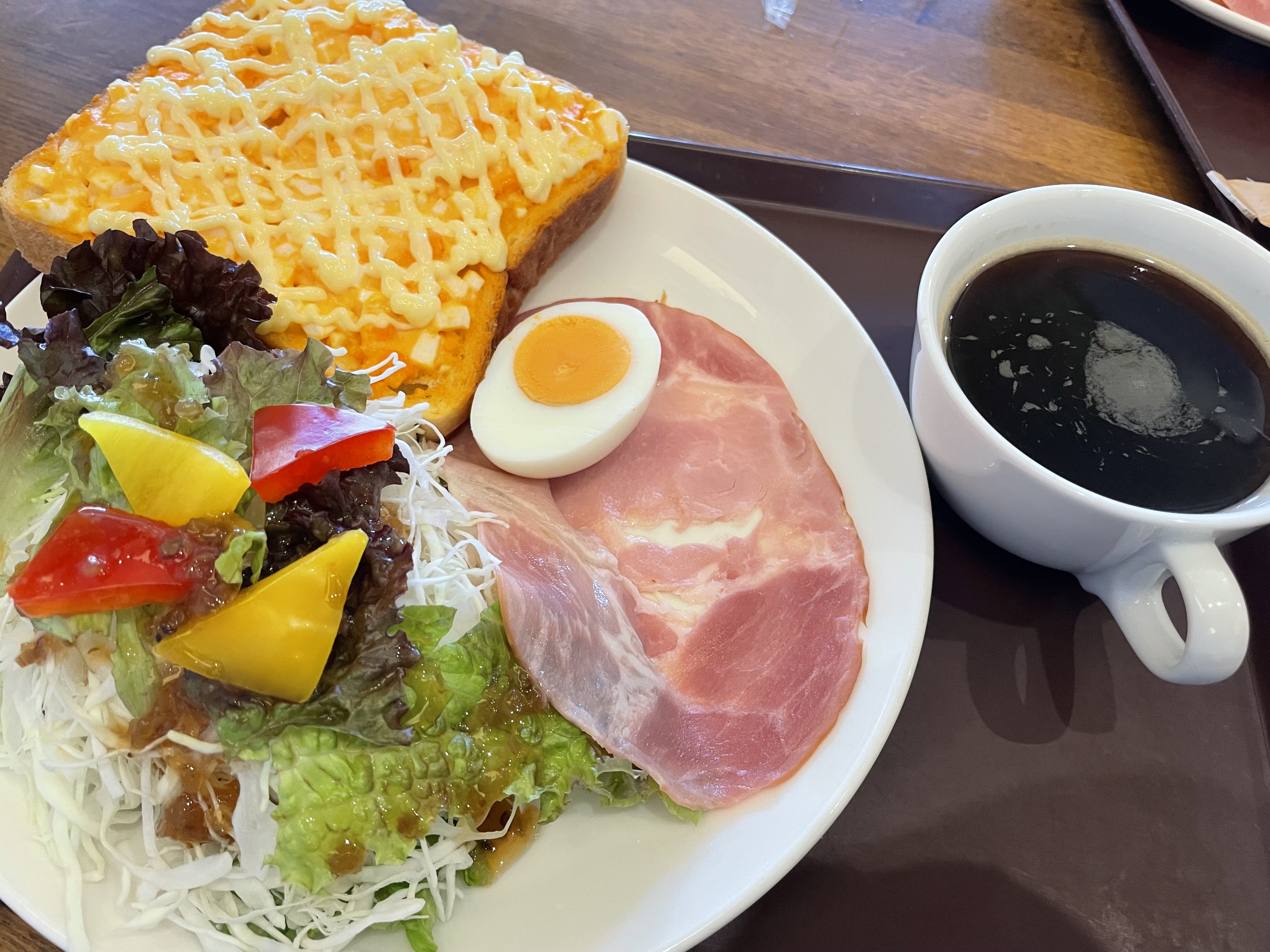Post Views: 18
はじめに
GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)とGMP(Good Manufacturing Practice)は、医薬品および再生医療等製品の製造における品質保証を確保するための基準ですが、その適用範囲と内容は異なります。
GMPは主に医薬品、バイオ医薬品、無菌製品、医療機器の製造管理および品質管理を対象とし、製造工程の無菌性、品質試験、製造記録、設備管理を網羅しています。
GMPは日米欧で広く適用され、各地域でその具体的な要件は異なるものの、ICH(国際医薬品規制調和会議)ガイドラインに基づき、リスクベースアプローチ(ICH Q9)も採用されています。
一方、GCTPは日本独自の基準であり、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)に特化した規制です。
GCTPは、細胞・組織の採取から製品化までのトレーサビリティ、ドナー適格性評価、無菌操作、交差汚染防止など、再生医療等製品特有のリスク管理に焦点を当てています。日本ではGMPとGCTPは独立して運用され、バイオ医薬品にはGMPが適用される一方、再生医療等製品にはGCTPが適用されます。
GMPは製品の品質と安全性を確保するための基本的な枠組みを提供し、GCTPはその一部を補完する役割を担っています。特にGCTPは、細胞・組織に特有のリスク(感染症リスク、交差汚染リスク)に対応し、GMPにはない「ドナー適格性評価」「トレーサビリティ保証」などの基準を追加しています。
両者の併用により、医薬品および再生医療等製品の品質と安全性が保証されます。
目次
GMPとGCTPの関係性 Q: GMPとGTCPの関係性は,GMPを前提にしてGTCPは上乗せ的な運用がされるのか,それとも個別に運用されるような関係性なのか?
ChatGPT: GMP(Good Manufacturing Practice)とGCTP(Good Cell and Tissue Practice)は、製品の特性や適用される製品カテゴリに基づき、異なる規制フレームワークで運用されます。その関係性は以下の通りです。
個別に運用:製品カテゴリごとに適用
GMPは、医薬品、原薬、無菌製品、バイオ医薬品、医療機器の製造に適用されます。
GCTPは、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品など)に適用されます。
そのため、GMP製品(例:抗体製品、一般医薬品)とGCTP製品(例:幹細胞治療製品、遺伝子改変細胞)はそれぞれ異なる基準で製造・品質管理が行われます。
適用範囲の重複はない
GMPは製品の無菌性、製造工程の管理、設備のクリーンルーム管理などに重点を置きます。
GCTPは、細胞・組織の安全性(供給元のトレーサビリティ、ドナー適格性評価)、製造プロセスでの交差汚染防止、ウイルス・細菌等の病原体の排除に重点を置きます。
GCTPはGMPに上乗せされるのではなく独立
GCTPは、細胞・組織を扱う特性に対応して独自の要件(例:ドナー適格性評価、細胞のトレーサビリティ)を持ち、GMPとは異なる要件が設定されています。
例:無菌操作の基準はGMPに準じることがあるが、細胞・組織の特異的なリスク管理はGCTPが担う。
具体例で理解:GMP製品とGCTP製品の運用の違い 製品タイプ 適用基準 管理内容例 抗体医薬品 GMP 無菌性保証、製造工程の品質管理、出荷試験 幹細胞治療製品 GCTP ドナー適格性評価、細胞のトレーサビリティ、交差汚染防止 遺伝子治療製品 GCTP ベクターの安全性確認、細胞の遺伝子導入効率、ウイルス除去
まとめ GMPとGCTPは**「相互に上乗せされるものではなく、別々の規制として運用される」**関係です。GMPは医薬品・原薬などの一般医薬品製造に適用され、GCTPは再生医療等製品に特化した規制として独立して運用されます。
この構造により、GMPとGCTPは互いの特性に応じて、異なる品質保証のアプローチを取ることが可能になります。
GMP適合性調査:バイオ医薬品の場合 Q: バイオ医薬品では製造販売承認申請後に製造所の適格性調査が行われるが,その調査は一般的にGMP適合性調査といわれることがある.GCTPの場合の説明をしてください
ChatGPT: バイオ医薬品(GMP適用製品)と再生医療等製品(GCTP適用製品)では、製造販売承認申請後の製造所の適格性調査(適合性調査)の実施方法や内容に違いがあります。
調査の対象
医薬品製造業者(バイオ医薬品を製造する工場) GMP(Good Manufacturing Practice)基準に基づく調査
調査の目的
GMPに基づく製造管理および品質管理が適切に行われているか確認。
無菌製品の場合、無菌操作および環境モニタリングが適切か確認。
原材料調達から最終製品に至るまでのトレーサビリティが保証されているか確認。
調査内容
施設・設備の確認: 無菌環境、クリーンルーム管理、製造ラインの設計。文書管理: 製造記録、出荷記録、逸脱管理手順の確認。従業員教育: GMPトレーニング、無菌操作トレーニングの実施状況。品質管理: 試験方法のバリデーション、出荷試験、安定性試験の確認。
GCTP適合性調査:再生医療等製品の場合 調査の対象
再生医療等製品の製造業者(細胞・組織を取り扱う施設) GCTP(Good Cell and Tissue Practice)基準に基づく調査
調査の目的
再生医療等製品(例:細胞治療製品、遺伝子治療製品)の製造過程がGCTPに準拠しているか確認。
細胞・組織の採取、調整、保存、輸送が安全かつ適切に管理されているか確認。
ドナー適格性評価、トレーサビリティ、病原体リスク管理が保証されているか確認。
調査内容
ドナー適格性評価: ドナーのスクリーニング、採取プロトコルの確認。細胞・組織のトレーサビリティ: 細胞採取から製品化までの記録確認。製造環境管理: 無菌操作手順、クリーンルーム管理、交差汚染防止措置。品質管理: 細胞の品質試験(生存率、純度、微生物試験)。ウイルス・細菌除去手順: 製品の無病原性を保証するための検査手順確認。
GMPとGCTPの適合性調査の比較 項目 GMP適合性調査 (バイオ医薬品) GCTP適合性調査 (再生医療等製品) 調査対象 製造所、製造ライン 細胞・組織を扱う施設 基準 GMP GCTP 重点管理領域 無菌製造、製造工程管理、品質管理 ドナー適格性、細胞・組織管理、トレーサビリティ トレーサビリティ 原材料から最終製品まで ドナーから最終製品まで 特殊要件 無菌性保証、環境モニタリング ドナー感染リスク管理、交差汚染防止 実施機関 PMDA(日本の場合) PMDA(日本の場合)
特記事項:PMDAによるGCTP適合性調査の特徴
GMP調査との違い GCTP特有の調査内容
細胞・組織の採取時の手順(適正な採取環境、無菌操作)。
ドナー適格性スクリーニング(感染症スクリーニング)。
細胞・組織の保管・輸送における温度管理、時間管理。
製品の無病原性保証(ウイルス・細菌の除去確認)。
GMP調査との併用
実務での対応ポイント
バイオ医薬品(GMP適用)は、製造設備や製造環境の無菌性と製造記録の整合性が強調されます。
再生医療等製品(GCTP適用)は、細胞・組織の取り扱いとドナー管理が重要視されます。
施設がGMPおよびGCTP両方に対応している場合は、製造エリアを物理的に分離 し、両方の基準に基づく適合性を確保する必要があります。
このように、GMPとGCTPの調査は、それぞれ製品特性に応じた基準に基づき、明確に異なる視点で実施されます。
GMPからGCTPへの経緯
GCTP以前の再生医療等製品:GMP準拠の時代 Q: 再生医療等製品のガイドラインは現在,GCTPがあるが,それが無かったころにはGMPに準拠するような運用がされていたのか?
ChatGPT:
1. GCTPの登場以前の運用 GCTP(Good Cell and Tissue Practice)が導入される以前、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)の製造および品質管理は、GMP(Good Manufacturing Practice) を基本に運用されていましたが、その適用にはいくつかの課題がありました:
GMPは本来、一般医薬品を対象 としており、細胞・組織の特性に対応した規制は存在しなかった 。GMPの基準は、無菌製品やバイオ医薬品の製造を念頭に置いており 、細胞や組織の採取・調整・保存・輸送といった特有のプロセスは考慮されていませんでした。
2. GMP準拠の再生医療等製品の課題 GMPに基づき再生医療等製品が製造されていた時代には、以下の課題がありました:
課題 説明 ドナー適格性評価の不明確化 GMPにはドナーの健康状態や感染症スクリーニングに関する規定がなく、製造者判断に依存。 トレーサビリティの不足 細胞・組織の採取元から最終製品までの完全な追跡は保証されていなかった。 細胞特有のリスク管理の欠如 細胞の汚染リスクや変異リスクに特化した規定が存在しなかった。 ウイルス・病原体リスク対応不足 GMPは無菌性(バクテリア)には対応していたが、ウイルスや細胞内病原体への対応は不十分。 製造環境基準の不整合 クリーンルーム基準(ISOクラス)はGMPに準じていたが、細胞操作には過剰または不足。
3. 再生医療等製品におけるGMP運用の実例
日本:GMP準拠の細胞治療製品
例:自家培養軟骨シート、幹細胞治療製品(GMP環境で製造)。
GMP基準に基づくクリーンルームで製造されたが、ドナー適格性評価は施設独自の基準で運用。
米国:GMP準拠の遺伝子治療製品
遺伝子ベクター(例:AAVベクター)はGMPに準拠して製造。
細胞ベースの遺伝子治療は、施設ごとに品質管理が異なり、ドナー管理は独自規定。
欧州:GMP準拠の組織工学製品
皮膚再生シートはGMPで製造されたが、ドナー感染リスクの管理はガイドラインが不足。
4. GCTP導入の必要性 GCTPの導入は、以下の理由から不可欠でした:
細胞・組織特有のリスク管理 ドナー管理の明確化 トレーサビリティの強化 細胞培養・製造プロセスの専用規定
5. GCTP導入による変化 GCTPは以下のようなポイントでGMPからの独自性を確立しています:
項目 GMP (導入前) GCTP(導入後) 適用対象 一般医薬品、バイオ医薬品 再生医療等製品(細胞治療、遺伝子治療、組織工学製品) ドナー適格性評価 記載なし 必須(感染症スクリーニング、健康状態確認) トレーサビリティ 製造工程の一貫した記録 採取から製品化までの完全トレーサビリティ 無菌性保証 一般的な無菌操作基準 細胞・組織特有の無菌操作(交差汚染防止) 製造環境 クリーンルーム(ISOクラスに準拠) 細胞・組織の無菌操作に特化した環境管理 ウイルス・病原体リスク対応 無菌性(細菌)に対応 ウイルス・病原体リスク(細胞由来病原体)に対応
6. まとめ GCTPが導入される以前、再生医療等製品はGMPに準拠して製造されていましたが、これは以下のような制約がありました:
細胞・組織特有のリスク(ウイルス、病原体)への対応が不足。
ドナー管理やトレーサビリティに関する明確な規定がなかった。
製造環境は医薬品向けの無菌環境に限定され、細胞培養に最適化されていなかった。
GCTP管理への経緯の概要
GCTPは、これらの課題を解決し、再生医療等製品の安全性と品質を確保するために導入されました。
Q: GMP準拠の時代からGCTP適用の時代として年代経過を教えて
ChatGPT: 再生医療等製品に関する製造管理および品質管理の基準であるGCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、2014年(平成26年)11月25日に施行されました。これにより、再生医療等製品の製造および品質管理に特化した規制体系が確立されました。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構+1J-STAGE+1
GCTPの導入以前、再生医療等製品の製造管理は、主にGMP(Good Manufacturing Practice)に準拠して行われていました。しかし、GMPは一般医薬品を対象とした基準であり、細胞・組織を原料とする再生医療等製品の特性には十分に対応できない部分がありました。例えば、ドナー適格性評価や細胞・組織のトレーサビリティ、無菌性の確保など、再生医療等製品特有のリスク管理が不十分でした。
GCTPの施行により、再生医療等製品の製造においては、ドナーの適格性評価、細胞・組織のトレーサビリティ、無菌性の確保など、製品特性に応じた管理が求められるようになりました。これにより、再生医療等製品の安全性と品質の確保が強化されました。
以下に、GMP準拠からGCTP適用への移行の概要を示します。
時期 主な出来事 1990年代~2000年代 再生医療等製品の開発が進む。GMPに準拠した製造管理が行われるが、細胞・組織特有のリスク管理には対応が不十分。 2014年11月25日 GCTPが施行され、再生医療等製品の製造管理および品質管理に特化した規制体系が確立される。
GCTPの導入により、再生医療等製品の製造においては、製品特性に応じた適切な管理が求められるようになり、安全性と品質の確保が強化されました。
GCTPの改定の履歴
Q: GCTPは2014年に初めての版が施行されたが,その後の版のアップデートの時期とその変更・修正内容を教えて
ChatGPT: GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、再生医療等製品の製造および品質管理に関する基準として、2014年(平成26年)11月25日に施行されました。その後、法改正や運用上の必要性に応じて、以下のような主な改正が行われています。
GCTPの主な改正履歴と内容
1. 2014年11月25日:GCTP初版施行
背景 :「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」の改正に伴い、再生医療等製品の製造管理および品質管理の基準としてGCTPが新設されました。主な内容 :
2. 2021年7月30日:GCTP調査要領の改正
通知 :「GCTP調査要領の改正について」(令和3年7月30日 薬生監麻発0730第1号)背景 :薬機法の一部改正(令和元年法律第63号)に伴い、再生医療等製品の製造販売等に関する要件が見直されました。主な改正内容 :
3. 2023年8月2日:適合性調査申請時の提出資料の改訂
通知 :「再生医療等製品適合性調査申請時の提出資料について」(2023年8月2日付 PMDA医薬品品質管理部 事務連絡)背景 :申請手続きの効率化および透明性の向上を目的として、提出資料の明確化が図られました。主な改正内容 :
まとめ
GCTPは、再生医療等製品の特性に応じた製造および品質管理の基準として、2014年に初めて施行されました。その後、法改正や運用上の必要性に応じて、調査要領の改正や申請手続きの見直しが行われ、再生医療等製品の安全性と品質の確保が強化されています。最新の情報や詳細な手続きについては、厚生労働省やPMDAの公式ウェブサイトを参照することをお勧めします。
GCTP(Good Cell and Tissue Practice)の改訂履歴 改訂版 年月日 主な改正内容 背景・通知 初版 2014年11月25日 – GCTP初版施行 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」改正に伴う新設 改訂1 2021年7月30日 – GCTP調査要領の改正 「GCTP調査要領の改正について」(令和3年7月30日 薬生監麻発0730第1号) 改訂2 2023年8月2日 – 適合性調査申請時の提出資料の改訂 「再生医療等製品適合性調査申請時の提出資料について」(2023年8月2日付 PMDA医薬品品質管理部 事務連絡)
解説
初版(2014年11月25日) 改訂1(2021年7月30日) 改訂2(2023年8月2日)
追加で確認したいことはありますか?
~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
GCTP改訂に伴う実務での運用変更
Q: GCTP改訂に伴う実務での運用変更の具体例を示して
ChatGPT:
GCTP改訂に伴う実務での運用変更:具体例 1. 2014年11月25日:GCTP初版施行
変更内容: 実務での運用変更例: 項目変更前(GMP準拠)変更後(GCTP準拠)ドナー適格性評価自主基準(各施設が独自に判断)ドナー適格性評価の義務化(感染症スクリーニング、健康確認)トレーサビリティ管理製造記録はGMP基準(バッチごとの記録)細胞・組織の採取から最終製品までのトレーサビリティを確保細胞・組織の無菌性保証一般的な無菌製造基準(無菌環境での製造)無菌操作に加え、交差汚染防止や無病原性保証が必須製造環境クリーンルーム(ISOクラスに準拠)細胞・組織に特化した無菌環境基準(手袋、無菌作業区域の明確化)出荷試験一般的な製品試験(外観、無菌性、安定性)細胞・組織製品特有の品質試験(生存率、純度、無病原性)
2. 2021年7月30日:GCTP調査要領の改正
変更内容: 実務での運用変更例: 項目変更前変更後調査準備自己点検および内部文書の準備事前にGCTP調査要領に基づく資料提出(ドナー管理、製造記録、品質管理手順書)調査実施監査員による製造エリア確認(GMPに準拠)調査対象施設ごとの製造プロセス確認(採取、調整、保管、出荷)調査結果の評価調査員の個別判断に依存評価基準が明確化(逸脱事項は段階的に評価:重大、軽微、指摘)追加入力調査後のフィードバックは任意必要に応じて是正措置・予防措置(CAPA)の提出が必須トレーサビリティの確認製造記録の確認が中心細胞・組織の採取から製品化までのトレーサビリティ(電子記録、バーコード)
3. 2023年8月2日:適合性調査申請時の提出資料の改訂
変更内容: 実務での運用変更例: 項目変更前変更後提出資料施設ごとの個別提出(書類形式が異なる)統一フォーマットでの提出(ドナー適格性、製造手順、品質試験手順)ドナー情報個別の記録提出(調査時の確認)ドナー適格性評価資料の事前提出(感染症スクリーニング結果、同意書)製造記録各製品ごとの製造記録(バッチ単位)製造フローチャートおよび各工程のトレーサビリティを一括提出品質試験手順各施設が独自に記載統一された品質試験手順(無病原性試験、生存率、純度確認)事前確認監査時の調査員判断提出資料を事前に確認し、不備があれば事前に修正を求める
追加で確認したいこと
~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
GCTP調査要領
Q: GCTP調査要領の概要を解説して
ChatGPT:
厚生労働省+3日本薬事法務学会+3日本薬事法務学会+3
GCTP調査要領の概要 1. GCTP調査要領の位置づけ
GCTP調査要領 は、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)の製造施設がGCTP(Good Cell and Tissue Practice)基準に適合しているかを確認するための公式な調査基準です。制定目的 :GCTPに準拠した安全で品質の高い再生医療等製品の製造を保証し、適切な製造管理および品質管理が維持されていることを確認する。実施主体 :厚生労働省およびPMDA(医薬品医療機器総合機構)。
2. 調査要領の構造 GCTP調査要領は以下の主要構成から成り立っています:
項目 内容 ① 調査の対象 再生医療等製品(細胞治療、遺伝子治療、組織工学製品)を製造する施設および関連施設。 ② 調査の目的 GCTP基準に基づき、安全かつ品質の高い再生医療等製品の製造が行われているか確認。 ③ 調査方法 施設訪問調査、文書確認、関係者へのインタビュー。 ④ 調査基準 GCTPに基づく製造管理・品質管理基準(例:ドナー管理、トレーサビリティ、無菌性保証)。 ⑤ 調査結果の評価 逸脱事項(重大、軽微、指摘)に分類し、必要に応じ是正措置を要求。 ⑥ 報告および通知 調査後、調査結果を施設に通知し、指摘事項への対応確認。 ⑦ 調査後のフォローアップ 是正措置・予防措置(CAPA)を確認し、必要に応じ追加調査。
3. 調査の実施方法 GCTP調査は以下の手順で実施されます:
1️⃣ 調査計画の策定
調査対象施設を選定し、事前に調査計画を策定。
調査日程、調査範囲、調査員を確定。
2️⃣ 事前資料の確認
申請者は以下の資料を事前に提出:
ドナー適格性評価資料(感染症スクリーニング、健康確認)
製造手順書(SOP)、品質管理手順書
トレーサビリティ資料(採取から製品化まで)
3️⃣ 現地調査の実施
調査員が施設を訪問し、以下を確認:
施設設備の適格性(クリーンルーム、無菌環境)
ドナー適格性評価手順の実施状況
製造および品質管理記録(無菌操作、トレーサビリティ)
管理者および担当者へのインタビュー
4️⃣ 調査結果の評価
逸脱事項を3つのレベルで分類:
重大な逸脱(Critical) :製品の安全性に直接影響を与える。軽微な逸脱(Major) :製品の品質に影響を与える可能性がある。指摘事項(Minor) :改善が望まれる点。
5️⃣ 調査結果の報告
調査終了後、調査結果を施設に報告。
逸脱事項に対する是正措置・予防措置(CAPA)の提出を要求。
6️⃣ フォローアップ調査
是正措置の実施状況を確認。
必要に応じて追加調査を実施。
4. GCTP調査で確認される主な項目 項目 説明 ドナー適格性評価 ドナーの健康状態確認(感染症スクリーニング、問診、同意書) トレーサビリティ 細胞・組織の採取から製品化までの完全な記録(バーコード、電子記録) 無菌操作 クリーンルーム内での無菌操作手順(手袋交換、無菌衣着用) 交差汚染防止 複数ドナーの細胞が混在しないようにするための作業エリア分離 製造手順およびSOP(標準作業手順) 製造工程のSOP(標準作業手順書)および従業員への教育訓練 品質管理 製品の品質試験(生存率、無病原性、純度確認) 廃棄物管理 細胞・組織由来廃棄物の処理手順(バイオハザード管理)
5. GCTP調査での指摘例(逸脱事項) 逸脱レベル 事例 是正措置例 重大(Critical) ドナー適格性評価が適切に実施されていない(感染症スクリーニングの欠如)。 ドナー評価手順書の改訂、教育訓練の実施。 軽微(Major) 無菌操作中に手袋交換が行われていない。 無菌操作手順書の改訂、定期的な監視の実施。 指摘(Minor) トレーサビリティ記録が一部欠落(採取から製品化までの記録が未整備)。 トレーサビリティシステムの再確認、電子記録の導入。
6. まとめ
GCTP調査要領は、再生医療等製品の製造・品質管理を保証するために、施設の適合性を評価する重要な手段です。
調査は、文書確認、現地確認、インタビューによって構成され、逸脱事項の指摘および是正措置が実施されます。
事前資料提出、ドナー適格性評価、無菌操作、トレーサビリティは特に重要な調査項目です。
追加で確認したいことはありますか?
~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
ChatGPT: 再生医療等製品の製造管理および品質管理に関する基準であるGCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)は、日本独自の規制であり、欧米では同様の名称は使用されていません。しかし、各国・地域において、再生医療等製品に対する規制や基準が設けられており、その内容や運用には違いがあります。以下に、日米欧における再生医療等製品の規制の違いを解説します。
🇯🇵 日本:GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)
対象製品 :再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)主な規制内容 :
ドナー適格性評価の義務化
細胞・組織のトレーサビリティ確保
無菌性および病原体リスク管理の強化
特徴 :日本独自の基準であり、再生医療等製品の特性に応じた製造管理および品質管理を求めています。
🇺🇸 アメリカ:cGTP(Current Good Tissue Practice)
🇪🇺 欧州連合:ATMP(Advanced Therapy Medicinal Products)
対象製品 :先進医療製品(遺伝子治療製品、体細胞治療製品、組織工学製品)主な規制内容 :
製造および品質管理基準(GMP)
臨床試験および市販後調査の要件
中央集権的な承認手続き(EMAによる)
特徴 :ATMPは、Regulation (EC) No 1394/2007に基づき、EU全体で統一された規制が適用されます。PMC
🧾 日米欧の規制の比較
項目 日本(GCTP) アメリカ(cGTP) 欧州連合(ATMP) 対象製品 再生医療等製品 HCT/Ps 先進医療製品 主な規制内容 ドナー評価、トレーサビリティ、無菌性管理 ドナー評価、感染症予防、施設管理 製造・品質管理、臨床試験、市販後調査 承認手続き PMDAによる審査 FDAによる審査 EMAによる中央集権的な審査 特徴 日本独自の基準 加工の程度や使用目的に応じた規制 EU全体で統一された規制
このように、再生医療等製品に対する規制は、各国・地域で異なる名称や基準が設けられていますが、共通して製品の安全性と品質の確保を目的としています。国際的な調和を図るため、各国の規制当局は協力し、共通のガイドラインや基準の策定に取り組んでいます。
日米欧における再生医療等製品の規制におけるGMPへの参照比較 Q: 日米欧における再生医療等製品の関わるガイドラインでは,既存のGMPを参照しない日本のGCTPがあるが,欧米でのGMPへの参照程度について日米欧における比較を解説して
ChatGPT: 再生医療等製品における製造管理および品質管理は、各国・地域で異なるガイドラインに基づいていますが、GMP(Good Manufacturing Practice)への参照や適用範囲には大きな違いがあります。以下では、日米欧でのGMPへの参照度を比較し、その違いを詳しく解説します。
日本:GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)
GMPへの参照:限定的(独立したGCTP基準)
日本のGCTPは、再生医療等製品(細胞治療、遺伝子治療、組織工学製品)に特化した規制であり、GMPとは独立した基準です。
GMPを直接参照することはなく 、GCTP独自の基準が設定されています。例:GCTPはドナー適格性評価、トレーサビリティ、無菌操作に特化しており、GMPが規定する「製造環境の無菌性」や「製造記録」も独自の要件に基づく。
GCTPの主な特徴
GMPの代替基準 :GCTPはGMPの代替ではなく、再生医療等製品専用の規制。無菌性の保証 :GMPのクリーンルーム基準(ISOクラス)とは異なる「無菌操作基準」を適用。ドナー適格性評価 :GMPではカバーされないドナーの健康状態や感染症スクリーニングを義務化。トレーサビリティ :細胞・組織の採取から製品化までの完全なトレーサビリティを確保。
アメリカ:cGTP(Current Good Tissue Practice)とGMP
GMPへの参照:限定的(製品の分類に依存)
アメリカでは、再生医療等製品はHCT/Ps(Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products)として規制され、製品の分類に応じてcGTP(Current Good Tissue Practice)またはGMPが適用されます。
HCT/PsはSection 361とSection 351に分かれ :
Section 361(低リスク製品) :cGTPのみ適用(GMPは参照されない)。Section 351(高リスク製品) :cGTPに加えてGMP(21 CFR Part 210, 211)が適用。
cGTPとGMPの適用例 製品タイプ 適用基準 GMPへの参照 自家細胞治療(低リスク) cGTP(21 CFR Part 1271) 参照なし 他家細胞治療(高リスク) cGTP + GMP(21 CFR Part 210, 211) GMP基準(無菌操作、トレーサビリティ) ウイルスベクター GMP(21 CFR Part 210, 211) 完全にGMP準拠
cGTPの主な特徴
GMPはリスクに応じて適用 :製品のリスク分類により、GMP適用が決定される。ドナー管理はcGTPで規定 :感染症スクリーニングやトレーサビリティはcGTPでカバー。GMPとの併用可能 :高リスク製品(遺伝子治療製品など)はGMPも適用。
欧州連合:ATMP(Advanced Therapy Medicinal Products)
GMPへの参照:広範かつ必須
欧州では、ATMP(先進医療製品:遺伝子治療製品、細胞治療製品、組織工学製品)は、基本的にGMPに準拠して製造管理および品質管理が行われます。
EudraLex Volume 4(GMPガイド) のPart IV「ATMP向けGMPガイド」が適用されます。例:ATMPにおける無菌操作はGMPに基づき、クリーンルーム(ISOクラス)の環境での製造が必須。
ATMPの主な特徴
GMPは基本要件 :ATMPはすべてGMPに準拠し、無菌性、トレーサビリティ、製造記録がGMP基準で規定。特定のGMPガイドライン :EudraLex Volume 4 Part IVがATMP向けに細かく規定。中央集権的な承認 :EMA(欧州医薬品庁)による中央審査で統一されたGMP基準を適用。製造施設の登録義務 :ATMP製造施設はEMAまたは各国当局による登録および適合性調査が必要。
日米欧におけるGMP参照度の比較 規制 日本(GCTP) アメリカ(cGTP) 欧州連合(ATMP) GMP参照度 ✖️ 参照しない(独立したGCTP) △ リスクに応じて適用 ✅ 常に参照(ATMP向けGMPガイド) 主な基準 GCTP(独立基準) cGTP + GMP(リスクに応じた組み合わせ) EudraLex Volume 4(GMP Part IV) 無菌操作 GCTP独自基準(交差汚染防止) cGTPまたはGMP(無菌環境管理) GMPに基づくクリーンルーム(ISO基準) ドナー適格性評価 GCTPで規定 cGTPで規定(感染症スクリーニング) GMP + ドナー適格性ガイドライン トレーサビリティ GCTPで独自に規定 cGTPで規定(採取から最終製品まで) GMP(EudraLex Volume 4 Part IV) 承認手続き PMDA FDA(HCT/Psのリスクに応じて) EMA(中央集権的審査)
まとめ
日本はGCTPとして独立した基準を持ち、GMPに依存せず再生医療等製品を規制。
アメリカはリスクに応じた柔軟なcGTP + GMP構成で、製品の特性に応じた規制が可能。
欧州はATMPに関して完全にGMP基準を適用し、無菌操作やトレーサビリティはGMPに準拠。
追加で確認したいこと
日米欧でのドナー適格性評価の詳細な比較を示しましょうか?
ATMP向けGMP(EudraLex Volume 4 Part IV)の詳細な規定内容を解説しましょうか?
GCTPの改訂履歴と実務運用変更の具体例も追加しましょうか?
Q: 医薬品製造ではICHガイドラインがあるが,GCTP,HCT/PsおよびATMPはそれぞれICHに対してどのように準拠した内容になっているのか? 日米欧において準拠具合に濃淡があるように感じるが,ICHに対する準拠程度を日米欧の比較で解説して.
ChatGPT: 再生医療等製品に関する規制は、日米欧それぞれの地域で異なるアプローチが取られており、ICH(国際医薬品規制調和会議)ガイドラインへの準拠度にも差異があります。以下に、各地域の規制とICHガイドラインとの関係を比較し、その違いを解説します。
🇯🇵 日本:GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)
ICHガイドラインへの準拠度: 限定的
日本のGCTPは、再生医療等製品に特化した独自の基準であり、ICHのGMPガイドライン(例:ICH Q7、Q8、Q9)を直接参照していません。
ただし、臨床試験に関しては、ICH E6(GCP)に準拠したガイドラインが適用されています。
また、品質や非臨床試験に関する技術的な指針では、ICHガイドラインの考え方を参考にしている部分もあります。
🇺🇸 アメリカ:HCT/Ps(Human Cells, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products)
ICHガイドラインへの準拠度: 中程度
アメリカでは、HCT/Psはリスクに応じて異なる規制が適用されます。
Section 361 に該当する低リスク製品は、cGTP(Current Good Tissue Practice)のみが適用され、ICHガイドラインの直接的な適用はありません。Section 351 に該当する高リスク製品は、医薬品や生物製剤として扱われ、GMP(21 CFR Part 210, 211)やICHガイドライン(例:ICH Q7、Q8、Q9)に準拠する必要があります。
このように、製品のリスク分類に応じて、ICHガイドラインの適用範囲が変わります。theattcnetwork.co.uk
🇪🇺 欧州連合:ATMP(Advanced Therapy Medicinal Products)
ICHガイドラインへの準拠度: 高い
欧州では、ATMPに対してICHガイドラインが広範に適用されています。
品質管理には、ICH Q5A~Q9などのガイドラインが適用されます。
非臨床および臨床試験には、ICH SシリーズやEシリーズのガイドラインが適用されます。
また、ATMP特有のガイドラインも整備されており、ICHガイドラインと整合性を持たせています。
このように、欧州ではICHガイドラインを基盤としつつ、ATMPに特化した追加的な規制が設けられています。BioInsights Publishing+1PMC+1
日米欧におけるICHガイドライン準拠度の比較
地域 規制対象 ICHガイドラインへの準拠度 備考 🇯🇵 日本 GCTP(再生医療等製品) 限定的 独自の基準を採用しつつ、部分的にICHの考え方を参考。 🇺🇸 アメリカ HCT/Ps(Section 361) 低い cGTPのみ適用、ICHガイドラインの直接的適用なし。 🇺🇸 アメリカ HCT/Ps(Section 351) 中程度 GMPおよびICHガイドラインに準拠。 🇪🇺 欧州連合 ATMP(先進医療製品) 高い ICHガイドラインを広範に適用し、ATMP特有のガイドラインも整備。
まとめ
日本 では、GCTPとして独自の基準が設けられており、ICHガイドラインへの直接的な準拠は限定的です。ただし、臨床試験に関してはICH E6(GCP)に準拠しています。アメリカ では、製品のリスク分類に応じて、ICHガイドラインの適用範囲が変わります。高リスク製品にはICHガイドラインが適用されますが、低リスク製品には適用されません。欧州 では、ATMPに対してICHガイドラインが広範に適用されており、さらにATMP特有のガイドラインも整備されています。
このように、日米欧での再生医療等製品に関する規制は、それぞれの地域の特性やリスク評価に基づいており、ICHガイドラインへの準拠度にも差異があります。
日米欧における再生医療等製品の規制とICHガイドラインの関係
European Medicines Agency (EMA)
Guidelines relevant for advanced therapy medicinal products – EMA
5,582 日前 U.S. Food and Drug AdministrationRegulation of HCT/Ps – Small Entity Compliance Guide – FDA923 日前 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構Regenerative Medical Products – PMDA
GCTP(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)におけるリスクアプローチ Q : GCTPでのリスクアプローチは,伝統的またはリスクベースのどちらを基本としているのか?
ChatGPT:
結論:GCTPは「伝統的リスクアプローチ」が基本です。
GCTPは、日本独自の基準であり、再生医療等製品(細胞治療製品、遺伝子治療製品、組織工学製品)に特化しています。
その基本的なリスクアプローチは、「伝統的リスクアプローチ」と呼ばれるものであり、リスクは異常・逸脱が発生した際に対処 するスタイルが基本です。
1. 伝統的リスクアプローチの特徴
事後対応型
異常・逸脱が発生した場合、その都度是正措置・予防措置(CAPA)を講じる。
製造記録や品質試験での逸脱を確認後に、原因調査し、対策を実施。
記録中心
逸脱発生時は、逸脱報告書を作成し、是正措置・予防措置を文書化。
製造記録は各工程ごとに作成し、問題発生時に参照。
経験ベースのリスク評価
リスクは製造責任者や品質管理責任者の経験に依存する。
逸脱の再発防止策は、過去の事例をもとに構築。
標準作業手順(SOP)による対応
無菌操作手順、ドナー適格性評価、トレーサビリティ確保はSOPで管理。
SOP逸脱が確認されると是正措置が求められる。
2. なぜリスクベースアプローチではなく伝統的リスクアプローチが採用されるのか?
GCTPはGMPとは異なり、細胞・組織に特化
細胞や組織の取り扱いは個別性が高く、標準的なリスク評価が困難。
例えば、ドナーの健康状態は個別に評価され、製造工程でのリスクも各細胞タイプで異なる。
過去の経験や手順が重視される
細胞培養や遺伝子改変は専門的な知識が必要であり、経験豊富な作業者の判断が重視される。
事前リスク評価が困難
細胞・組織は性質が多様であり、製造中の挙動が一定しないことが多い。
事前にリスク評価を行っても、実際の製造で想定外の問題が発生する可能性が高い。
3. 例:GCTPでの伝統的リスクアプローチの運用 ドナー適格性評価
伝統的アプローチ: ドナー採取後、感染症スクリーニングを実施。異常が確認された場合はその都度評価し、適格性を確認。
製造中の無菌性保証
伝統的アプローチ: 製造工程で環境モニタリングを実施し、異常が確認された場合は清掃手順を見直し、無菌操作手順を修正。
細胞培養における品質管理
伝統的アプローチ: 細胞培養中に汚染が発生した場合は、そのバッチを廃棄し、原因調査を実施。再発防止策は製造記録をもとに評価。
4. 例外:リスクベースアプローチも導入可能
GCTPは伝統的リスクアプローチを基本としていますが、リスクベースアプローチ(ICH Q9準拠)も採用は可能 です。
例:ドナー適格性評価をリスク評価に基づき、感染症リスクを数値化し、リスクの高いドナーは追加検査を実施。
例:製造工程の無菌性を事前にリスク評価し、交差汚染のリスクをFMEA(Failure Mode and Effects Analysis)で評価。
5. まとめ GCTPは細胞・組織の個別性を重視し、標準化が難しい領域であり、経験に基づくリスク対応が重視されています。
GCTPは基本的に「伝統的リスクアプローチ」を採用し、異常・逸脱に対する事後対応が基本です。
ただし、リスクベースアプローチ(ICH Q9準拠)も採用は可能であり、製造施設が希望すれば事前にリスク評価を行い、リスク低減策を導入できます。
参考 GMPについて
GMPと一言で言うと一つの完全な基準のように考えがちだが,実際には,日米欧におけるGMP内容は違いがあると思われるので内容にどれくらいの違いがあるのか解説して.
ChatGPT: GMP(Good Manufacturing Practice)は、医薬品の製造における品質と安全性を確保するための基本的な枠組みですが、日米欧それぞれの地域で具体的な規制内容や運用には違いがあります。以下に、各地域のGMPの特徴とその違いを解説します。
🇯🇵 日本:GMPの特徴
法的根拠 :「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づき、厚生労働省令「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準(GMP省令)」が定められています。規制内容 :製造所の設備、製造工程、品質管理、文書管理、教育訓練など、製造および品質管理に関する詳細な要件が規定されています。特徴 :日本のGMPは、製造管理と品質管理を明確に区分し、それぞれに対して責任者の配置を求めるなど、責任体制が明確にされています。
🇺🇸 アメリカ:cGMPの特徴
法的根拠 :連邦規則集(CFR)Title 21 Part 210および211に基づき、FDA(食品医薬品局)が規制を行っています。規制内容 :製造施設の設計、設備、製造工程、品質管理、文書管理、従業員の資格など、製造全般にわたる要件が定められています。特徴 :「current(最新の)」という概念を強調し、技術や科学の進歩に応じてGMPの要件も進化することを前提としています。また、リスクベースのアプローチを重視し、製品のリスクに応じた管理が求められます。ウィキペディア
🇪🇺 欧州連合(EU):EU-GMPの特徴
法的根拠 :EU指令2003/94/ECおよび規則(EC)No 1252/2014に基づき、各加盟国の規制当局がGMPの遵守を監督しています。規制内容 :EudraLex Volume 4として知られるGMPガイドラインに、製造管理、品質管理、文書管理、教育訓練、自己点検などの要件が詳細に記載されています。特徴 :「Qualified Person(QP)」制度が導入されており、製品の出荷前にQPがGMPの遵守を確認することが義務付けられています。また、ATMP(先進医療製品)に対しては、特別なGMP Annexが適用されます。L-Università ta’ Malta
日米欧のGMPの主な違い
項目 日本 アメリカ 欧州連合(EU) 法的根拠 薬機法およびGMP省令 CFR Title 21 Part 210/211 EU指令2003/94/ECおよび規則No 1252/2014 規制当局 厚生労働省、PMDA FDA 各加盟国の規制当局(例:EMA) 責任体制 製造管理責任者と品質管理責任者を明確に区分 品質部門の責任者が全体を統括 Qualified Person(QP)が出荷を承認 リスクアプローチ 伝統的なアプローチ リスクベースのアプローチを重視 リスクベースのアプローチを採用 文書管理 詳細な文書管理が求められる 文書管理の柔軟性が高い 文書管理が厳格で、詳細な記録が求められる 特記事項 GMPとGCTPが併存 GMPとcGTPが製品のリスクに応じて適用 ATMP向けの特別なGMP Annexが存在
まとめ
GMPは国際的に共通の理念を持ちながらも、各地域の法制度や医薬品産業の特性に応じて具体的な要件や運用が異なります。日本ではGMPとGCTPが併存し、再生医療等製品に対する特有の規制が存在します。アメリカではリスクベースのアプローチが強調され、製品のリスクに応じてGMPやcGTPが適用されます。欧州連合では、QP制度やATMP向けの特別なGMP Annexなど、厳格な品質保証体制が整備されています。これらの違いを理解し、各地域の規制要件に適切に対応することが、国際的な医薬品製造・供給において重要です。
日本のGMPにおける伝統的リスクアプローチと欧米のリスクベースアプローチの違い Q: 日本では伝統的なリスクアプローチがとられているとあるが,欧米のリスクベースでのアプローチと比較してどのような点で違いがあるのか解説して
ChatGPT: GMP(Good Manufacturing Practice)におけるリスクアプローチは、各地域で異なる特徴を持っています。日本は「伝統的リスクアプローチ」、欧米(特にアメリカと欧州)は「リスクベースアプローチ」を強調しています。これらの違いを具体的に比較しながら解説します。
1. リスクアプローチの基本概念 視点 日本:伝統的リスクアプローチ 欧米:リスクベースアプローチ リスクの定義 品質や安全性へのリスクは「逸脱・異常」として捉える 品質や安全性へのリスクは「確率 × 影響度」として評価 リスク評価のタイミング 逸脱が発生した際に評価(事後対応) 製造工程設計時に事前に評価(事前対応) リスク管理の対象 逸脱や異常に対する是正措置(CAPA) 全製造工程(設計、実施、監視)に対するリスク制御 リスクの文書化 逸脱報告書、是正措置報告書として記録 リスクマネジメント計画、リスク評価報告書、モニタリング記録 リスク評価ツール 特定のツールは明確でない(経験に基づく評価が多い) ICH Q9に基づくリスクマネジメントツール(FMEA, HACCP)
2. 日本のGMP:伝統的リスクアプローチ ✔️ 特徴
事後対応型: リスクは「逸脱」や「異常」として捉えられ、問題が発生した際に初めて是正措置が講じられる。記録重視: 製造記録や試験記録に異常が見つかった場合、是正措置・予防措置(CAPA)を文書で記録。管理責任者の役割: 製造管理責任者および品質管理責任者が各部門でリスク管理を担当。経験重視: 製造経験に基づく問題解決が重視され、リスク評価は各担当者の経験に依存。
実例:製造中の異常対応
異常発生: 無菌製造中に環境モニタリングで細菌が検出。対応: 異常報告書を作成 → 原因調査 → 是正措置(清掃手順変更) → 予防措置(定期的な教育訓練)。リスク評価: この異常に関するリスクは、発生後に評価されるため、事前のリスク予測は行われない。
3. 欧米のGMP:リスクベースアプローチ 特徴
事前対応型: 製造工程を設計する段階でリスク評価(リスクアセスメント)を実施し、潜在リスクを特定。リスクマネジメントシステム: ICH Q9(Quality Risk Management)に基づき、リスクマネジメントを体系的に運用。継続的モニタリング: 製造中のリスクもモニタリングし、リアルタイムでリスク評価が行われる。科学的アプローチ: リスク評価ツール(FMEA, HACCP, Fishbone Diagram)を使用し、数値的にリスクを評価。
実例:製造中のリスク管理
リスクアセスメント: 無菌製造工程を設計する際、以下をリスク評価:
環境微生物の汚染リスク(確率:高 / 影響:重大)
製造エリアの清掃手順不備リスク(確率:中 / 影響:中)
リスク低減策: 無菌操作手順を設計し、清掃手順を標準化。継続的モニタリング: 無菌エリアの環境モニタリングデータをリアルタイムで記録し、異常を自動的に通知。
4. リスクアプローチにおける日米欧の比較 項目 日本:伝統的リスクアプローチ アメリカ:リスクベースアプローチ 欧州:リスクベースアプローチ リスク評価のタイミング 逸脱・異常発生後に評価 製造設計段階でリスク評価(事前対応) 製造設計段階+継続的モニタリング リスクマネジメントツール 明確なツールは指定されない ICH Q9:FMEA, HACCP, Fishbone Diagram ICH Q9に加え、各製造エリアごとのリスク評価 記録管理 逸脱報告書、是正措置・予防措置記録 リスク評価計画、リスク評価報告書、CAPA記録 リスク評価計画、リスク評価報告書、QPによる確認 監査および評価 規定違反時に評価(PMDA監査) リスクに基づく監査(FDA監査) リスクに基づく監査(EMAまたは各国規制当局) リスク対応 逸脱時の是正措置が中心 事前にリスク低減策を導入 事前リスク低減+監視リスク対応 リスク責任者 製造管理責任者、品質管理責任者 品質部門責任者(リスク管理担当) Qualified Person(QP)がリスク確認
5. まとめ
日本のGMP は、問題発生時の対応(事後対応)が中心であり、リスクは「逸脱」として扱われ、経験ベースでの評価が行われます。**欧米のGMP(アメリカ・欧州)**は、事前にリスクを予測し、リスク低減策を設計時から組み込みます。リスク評価は継続的に行われ、科学的アプローチが重視されます。
**ICH Q9(Quality Risk Management)**は欧米では広く適用されていますが、日本では必須ではなく、伝統的なリスク対応が優先されています。
追加で確認したいこと
~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
日本のGMPでリスクベースアプローチを採用することは可能か? Q: 日本のGMPでのリスクアプローチは伝統的な内容となっているが,一方で三極対応でるICHではリスクベースのアプローチが記載されている.従って,日本でもリスクベースのアプローチを取る事は可能と考えるが正しいか?.しかし,製造販売承認申請で提出するCTDにおいて,伝統的リスクアプローチとリスクベースアプローチの何れも記載可能なのかについても解説して.
ChatGPT:
結論:可能です。 理由
ICHガイドラインへの準拠 :日本はICH(国際医薬品規制調和会議)のメンバーであり、ICH Q9(Quality Risk Management)を採択しています。このガイドラインは、リスクベースアプローチの実施方法を示しており、日本でも適用可能です。PMDAの理解 :PMDA(医薬品医療機器総合機構)は、製造所の適格性調査(GMP調査)において、リスクベースアプローチを採用したリスク評価が行われた場合、その妥当性を確認します。リスクベースアプローチの実施事例 :近年、日本でも製造業者がICH Q9に準拠し、FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)やHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)を使用してリスク評価を行い、リスク低減策を導入しています。
製造販売承認申請(CTD)におけるリスクアプローチの記載は可能か? 結論:伝統的リスクアプローチもリスクベースアプローチも、どちらもCTDに記載可能です。
CTD(Common Technical Document) は、製造販売承認申請で使用される国際標準の書式であり、日本、アメリカ、欧州で共通の構成(モジュール1~5)を持っています。CTD内のリスクアプローチ記載箇所 :
Module 3(品質に関する情報) :製造方法(3.2.P.3)、製造管理(3.2.P.3.5)、品質リスクマネジメント(3.2.P.5.6)Module 2(概要と総括) :品質概要(2.3.QOS)でリスク評価のサマリーを記載可能
CTDでの伝統的リスクアプローチとリスクベースアプローチの具体的な記載例 項目 伝統的リスクアプローチ リスクベースアプローチ リスク評価方法の記載 「異常発生時に是正措置を講じる」 「製造工程設計時にリスク評価を実施。FMEAで評価」 製造工程でのリスク管理 「異常検知後、原因を特定し対策を講じる」 「製造工程中に無菌性リスク評価を実施。交差汚染防止策を導入」 リスク低減策の記載 「異常発生後に清掃手順を修正」 「事前にリスク評価を行い、清掃手順を標準化。定期的に見直し」 リスクマネジメント計画 記載しないことが多い リスクマネジメント計画を作成し、CTDに添付可能 品質試験でのリスク評価 「異常発生時に再試験を実施」 「リスク評価に基づき、試験パラメータを決定。逸脱は事前に特定」
リスクベースアプローチを採用する場合のCTD記載方法(例) 1. Module 3.2.P.3.5(製造管理および工程管理)
伝統的アプローチ例: リスクベースアプローチ例:
作業者の動線を制限し、交差汚染リスクを低減。
クリーンルームの清掃手順を標準化し、無菌性を確保。
リアルタイム環境モニタリングを導入し、異常を迅速に検知。」
2. Module 3.2.P.5.6(品質リスクマネジメント)
伝統的アプローチ例: リスクベースアプローチ例:
📌 なぜリスクベースアプローチを採用するべきか? 国際的な規制調和:
ICH Q9(Quality Risk Management)は日米欧で採択されており、リスクベースアプローチは国際的に推奨されています。
製造効率の向上:
リスクベースアプローチは、事前にリスクを特定し、適切な管理策を導入するため、逸脱発生時の対応が迅速化します。
PMDAの理解と対応:
日本でもPMDAはリスクベースアプローチを理解しており、適切なリスク評価がCTDで示されれば、評価に問題はありません。
医薬品品質の向上:
製造工程の設計段階でリスク評価を行うため、品質と安全性が一貫して確保されます。
まとめ
日本では伝統的なリスクアプローチが標準的ですが、リスクベースアプローチ(ICH Q9準拠)も採用可能であり、CTDでその内容を記載できます。
CTDには、製造工程(3.2.P.3.5)や品質リスクマネジメント(3.2.P.5.6)でリスク評価方法を明確に記載できます。
リスクベースアプローチは、国際的な規制調和を考慮し、採用を検討することが推奨されます。
追加で確認したいこと
~メンバー専用 ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↑ メンバー専用~
無料登録は右の握手ボタンからかできます.
編集履歴
2025/05/12 Mrはりきり(with 4o)
![[GMP] あるサイトの用語定義説明されている「GMP」について少し古いし違和感があったので — AI君に聞いてみた! [2025/05/17]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2023/06/IMG_8895.jpeg)
![[アニメ] 気になる作品二度見シリーズ : 「俺100」 100万の命の上に俺は立っている (2020年アニメ作品)- I’m standing on 1,000,000 lives.](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2025/05/IMG_2567.jpeg)
![Exsosome – 製造方法について調べてみた [2025/05/16]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2021/02/80F3D755-3019-49C6-BDAE-47D137C87826.jpeg)

![[GCTP] GCTPはGMPとは違うのか? GCTPまでの経緯や日米欧の比較 [2025/05/12]](https://harikiri.diskstation.me/myblog/wp-content/uploads/2024/01/IMG_2093.png)